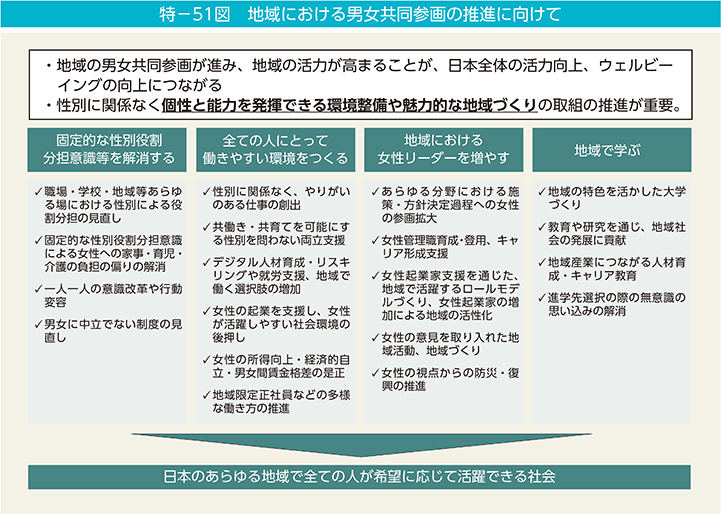本編 > 1 > 特集 > 第3節 魅力ある地域づくりに向けて
第3節 魅力ある地域づくりに向けて
我が国は、少子高齢化の進展や人口減少により、産業や地域活動など様々な局面で人手不足が顕在化しており、担い手として欠かせない女性の参画がこれまで以上に求められる状況にある。
そうした中で、第1節、第2節でみてきたように、近年、若い女性が地方から都市へ転出する傾向が強くなっている。進学先及び仕事の選択肢の豊富さや、雇用環境・労働条件における都市と地方の差異に加えて、地方では、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みなどにより、女性が個性や能力を発揮することが難しい状況に置かれており、閉塞感を感じやすい26ことなどが影響していると考えられる。
女性の都市への転出が続けば、地方の活力が低下すると同時に、地域によって男女別人口の不均衡が発生することから、未婚化や少子化の要因の一つともなり、将来的には、都市を含む日本全体の活力の低下につながる可能性がある。
また、女性活躍・男女共同参画の進捗には、地域間で差異がみられる。
女性の社会への参画が求められている一方で、依然として「家事・育児・介護は女性の仕事」といった固定的な性別役割分担意識は、特に地方において根強く残っており、若い女性が地方から都市へ転出し、地元へ戻らない要因の1つとなっていると考えられる(特-35図再掲)。
固定的な性別役割分担意識や伝統的価値観は、男性の生きづらさ27にもつながっており、若い男性が出身地域を離れる理由ともなっていると考えられる(特-27図再掲)。
若い世代の男女が、自らの希望する生き方を実現するために行う選択は、尊重されるべきであり、少子高齢化及び人口減少への対応や地域の活力向上は、老若男女が協力して取り組むべき課題である。
女性や若者の地方からの転出に歯止めをかけ、地域を活性化するためには、各地域で暮らしている女性や若者の待遇や環境を変えていくことが重要である。
全ての人が希望に応じて活躍できる社会の実現を目指し、全国津々浦々で地域における男女共同参画社会を実現することが重要である。
地域における男女共同参画社会の実現のためには、様々な政策課題があるが、特に、以下の4つが優先的に対応すべき事項と考えられる。
第一に、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みの解消である。
第2節で確認したように、人々の暮らし方・働き方の根底には、女性にも男性にも、長年にわたり形成されてきた固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みがあると考えられる。
地方における暮らしやすさ・働きやすさの改善のためには、一人一人が自らの固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みに気付き、男女双方の意識改革に取り組むとともに、固定的な性別役割分担を前提とした制度や慣習を見直す必要がある。
現時点では、企業の管理職や地域のリーダーの多くが男性であることを踏まえると、そのような人々の意識改革や行動変容が重要である。オールド・ボーイズ・ネットワークに代表されるような男性中心の組織文化や人間関係においては、悪意なく、多数派である男性にとって快適な環境が構築され、結果的に男性に有利、女性に不利な慣習や制度が生まれやすく、その見直しには抵抗感を伴いやすい。意思決定権を持つ男性リーダー層に対するアプローチが特に重要であろう。
一方で、女性もまた、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みにより、自分自身あるいは家族や周囲の人々に対し、固定的な性別役割分担を押し付けたりしている可能性がある。
女性も男性も一人一人が自分ごととして認識し、自らの言動を振り返るとともに、そのような意識の醸成及び再生産をしないようにしていく必要がある。
そのための具体的な方策として、職場・学校・地域等のあらゆる場における固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みを解消するための学習・研修や意見交換などによる情報共有などが挙げられる。男女双方の意識改革・理解促進のための取組が必要であり、問題意識を持ち具体的な行動変容につなげていくことが重要である。
第二に、女性が活躍できる職場への改革と全ての人にとって働きやすい環境づくりである。
進学及び就職は、女性や若者が都市へ転出するきっかけや地元を離れる大きな理由となっている。
地方の女性が都市へ転出し、地元に戻らない理由の1つに、女性が「働きたい」と思える職場が少ないこと、女性の仕事の選択肢が限られていることなどが挙げられる。
東京圏以外から東京圏に転出した女性は、能力や学歴を活かせる仕事、キャリアアップ、収入の高さ、仕事と子育ての両立を求める割合が高く、仕事内容、昇進、給与等に男女の差異がないこと、ワーク・ライフ・バランスについて、満足している割合が高くなっており(特-33図、特-42図再掲)、若い女性が、より魅力的な仕事の場を求めて、都市へ転出していることがうかがえる。
女性のいわゆる「М字カーブ」はどの地域でもほぼ解消されているものの、正規雇用比率は、20代後半をピークに年代が上がるとともに低下するいわゆる「L字カーブ」を描いており、この時期に働き方を変えたり、キャリアを中断・断念したりする状況が残っていることがうかがえる(特-13図、特-14図再掲、第2分野2-2図)。
また、家事・育児・介護等と両立しながら、自分の都合のよい時間に働けるという点にメリットを感じ、柔軟な働き方として、自ら非正規雇用を選択している女性も一定の割合でみられる28。
しかしながら、非正規雇用労働者の年収水準は、正規雇用労働者の約7割29であり、年齢に伴う賃金の伸びがみられず、企業を通じた職業能力開発機会が乏しいだけでなく、自己啓発の実施割合も少ない状況にある30。
結婚や家族に関する意識が変化し、女性の人生が多様化している。長い人生の中で、女性が経済的困窮に陥ることなく、尊厳と誇りをもって人生を送るために、女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の一層の推進が重要である。
そのためにも、結婚・出産・子育て・介護などのライフイベントを契機とした女性の離職や非正規雇用への転換を減らす取組が必要であり、各企業において、地域限定正社員や短時間勤務など正社員としての雇用を維持しながら多様な働き方を実現する取組や、研修などにより女性管理職を増やす取組のほか、非正規雇用労働者については、同一労働同一賃金の考えに基づく公正な処遇など、待遇改善や希望に応じたキャリアアップ等に努めていく必要がある。
また、女性は、大学等への進学検討において、資格取得に有利な進学先を選ぶ傾向にある(特-29図、特-30図再掲)。これは、将来の出産・子育てによる労働市場からの離脱を想定しての選択であるとも考えられる。
仮に、結婚や出産などのターニングポイントで労働市場からいったん退出したとしても、いつでも労働市場に参入し、退出時と同等の処遇を得るための一助として、女性の就業に直結するリスキリングの機会の提供やリカレント教育等も重要である。
近年の急速なデジタル化の進展は、省力化や生産性の向上等、労働力人口の減少が見込まれる我が国に大きなメリットをもたらすと予測される一方で、定型的な作業の割合が高い女性労働者の方が、AI(Artificial Intelligence)に代替されるリスクにより多く直面しており、またAIのメリットは教育水準の高い労働者に偏る可能性があると指摘されている31。
一方で、デジタル分野における就労は、テレワークなど柔軟な働き方が実現しやすく、育児や介護等のライフステージや生活スタイルに応じた女性の就労機会の創出にもつながる。また、デジタル分野は就労場所の制約が少なく、地域において働きやすいという特徴もある。このため、就労に直結するデジタルスキルを身につけ、就業獲得や所得向上32に向けた取組を進めていくことも重要である33。
なお、これらの取組は、管理職比率及び勤続年数の差異が主な要因と言われている男女間賃金格差の是正にもつながる。
男女間賃金格差の背景には、コース別雇用管理の下で男女の労働者の役割分担が定着していることや、女性の活躍を阻む無意識の思い込みが根深く存在していること等が指摘されている。
また、都道府県ごとに状況は異なるが、女性の管理職割合が低く、勤続年数の男女差が大きい県ほど賃金格差が大きい傾向にあり、男女間賃金格差が若い女性の地方からの転出につながる可能性等も指摘されている34。このため、男女間賃金格差の是正は、地域経済の長期的な持続性の向上にも寄与するであろう。
他方、働く女性が増える一方で、依然として、家事・育児・介護等の負担が女性に偏っていること及び長時間労働の慣行が変わっていないことが、我が国の女性の社会での活躍が遅れている一因であると考えられている35。
我が国の未来を担う若い世代の、家庭でも社会でも活躍したいという希望が叶えられる社会を作ることは極めて重要であり、女性が仕事を継続できるだけでなく、しっかりとキャリア形成ができるような環境を整えることが必要である。
現在は自ら非正規雇用を選択している者であっても、柔軟な働き方の推進や、家事・育児・介護等のサポートが充実すれば、正規雇用労働者として働くことができる可能性が高まる。
そのためには、現在の雇用慣行を改め、長時間労働を是正し、柔軟な働き方を浸透させることに加え、男女間で家事・育児・介護等を公平に分担することも重要である。
また、ワーク・ライフ・バランス等の実現に向けて、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)第24条等に基づき、国等の調達においてワーク・ライフ・バランス等推進企業(女性活躍推進法に基づくえるぼし認定企業や、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づくくるみん認定企業等)を加点評価する取組を実施しているが、各認定の取得企業比率を都道府県別にみても、東京都の企業の取得率が突出して高くなっている36。今後は、大都市・大企業だけでなく、地方・中小企業にも取組を広げていく必要がある。
地方においても、女性が活躍し、経済的に十分に自立できるだけの収入を得られる雇用の場を作っていくことが重要である。
同時に、女性が働きたいと思える仕事を、女性自身が切り開いていくことも必要である。
地域の伝統的な文化や産業などの資産、地域の社会的課題に着目して、自ら事業を起こそうと考えている女性は日本各地に存在する。男女問わず生き生きと働ける職場を女性自ら作っていくことも必要であり、それぞれの地域で、女性の起業の支援や、その前提となる女性が活躍しやすい社会の環境づくりを後押ししていくことも重要である37。
第三に、あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大である。
政策・方針決定過程への女性の参画を拡大することは、社会の多様性と活力を高め、我が国の経済が力強く発展していく観点や、男女間の実質的な機会の平等を担保する観点からも極めて重要である。
女性就業率は上昇し、女性の参画が拡大してきているものの、企業の管理職や地域のリーダーなどの指導的役割に就く女性はいまだ少ない。
多様化・複雑化した地域の課題を解決に導くためには、住民のニーズを的確に捉え、個々の住民の利害や立場の違いを乗り越えて、地域の在り方について広い見地から議論が行われる必要がある。このため、政治分野における女性の参画拡大は非常に重要である。多様な人材が参画することで、地方における施策の活性化につながることが期待できる。
企業における女性の登用の加速化は、社内の多様性の向上を通じて事業変革を促し、企業価値を高めることにつながることから、日本経済の今後の成長にとっても喫緊の課題である。管理職、更には役員へ、という女性の人材の育成・登用に向けた取組を着実に進めていく必要がある。
地域において女性の起業家を増やすことは、当該女性起業家による、地域の女性が働きやすい雇用環境の創出や、女性のニーズを踏まえた商品・サービスの開発や地域課題の発見・解決等の促進につながることに加え、活躍する女性起業家自身がロールモデルとなって地域における意識改革を促し、起業を含む女性のチャレンジを一層推進する力となることが考えられる。
自治会及び農林水産業を始めとする地域活動において、女性リーダーを増やすことは、地域活動や地域づくりのプロセスに、男女共同参画の視点及び女性の意見を取り入れ、反映することにつながるであろう。
また、防災・復興における意思決定の場への女性の参画を進め、男女共同参画の視点からの災害対応の取組を進めていくことも重要である。
市区町村の常備備蓄を例にとると、市区町村防災会議において、女性委員がゼロの市区町村と比べ、女性委員が10%以上の市区町村の方が、女性用品、乳幼児用品、介護用品の常備備蓄割合が高く、多様なニーズに対応されていることがわかる38。
指導的役割に就く女性の増加により、女性の視点が反映されにくい状況が好転し、地域における女性の暮らしにくさ・生きづらさの改善が見込まれ、女性にとって魅力的な地域へと発展を遂げることが期待できる。
第四に、地域で学ぶ選択肢の増加である。
大学等への進学時に多くの若者が地方から転出している状況を踏まえると、若者にとって地域の大学等での学びが魅力を持つに至っていない可能性が示唆される。
地域において多様な学びの選択ができるようにすること、そして地域で学びを活かす場を作っていくことは、全国のあらゆる地域で女性が活躍していくためにも重要である39。
地域産業の担い手となり、地域に定着する人材を育成することや、地域から出てグローバルに活躍し、その恩恵を地域にもたらす人材を育成することも重要である。また、大学等の魅力によって日本全国や世界各国から学生が集まり、キャンパスで過ごす中で、その大学等を育んだ地域の魅力を知り、その地域への愛着が醸成され、卒業後も地域に関わり続けるようになることも考えられる。
また、進路選択において、理系を選択する女子の割合が低い(第4分野4-1図)ことは、科学技術の発展のために男女が共に参画し、多様な視点や発想を取り入れていくために解決すべき課題である。女性研究者・技術者を増やすべく前段階となる大学等の専攻分野において、「女性は理系に向いていない」という固定観念を打破し、女子中高生、保護者、教員等の進路への興味関心や理解を深め、女性の理系進路選択を促進していくことも重要である。
女性も男性も固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みにとらわれることなく、学びの内容を自ら選択できるようにする必要がある。
我が国には、全国各地に多様で豊かな文化が息づいており、各地域がそれぞれの特性を踏まえ、持続的な地域社会を実現することが重要である。
他方で、地域の伝統的価値観や環境に順応できる者だけが地域に残り、その価値観に馴染めない者が離れていく地域であっては、人々の移動は一方通行となり、その活力は衰退の一途を辿ることとなるだろう。
都市では、地方に比べて様々な機会や選択肢が豊富にあることは事実である。しかしながら、地方から都市に転出した者でも、出身地域へ愛着を持っている者は多い(特-44図再掲)。また、現住地域以外に住みたいと考えている者も一定数おり(特-46図再掲)、今後、各地域への移住の可能性も十分あると考えられる。都市や世界で、様々な経験を積み、知見を得た人材が、いずれ地元に戻り、地元に還元することが、地方の活力にもつながり得る。一たび地元を離れた者が、「帰りたい」と思える地域への変革が必要である。また、地方への移住だけでなく、特定の地域に継続的に多様な形で関わる関係人口の増加など人々の流れを創ることも重要である。
地域に住む人々の意識が変わらなければ、人々は地域に戻らない。また、地域の男女共同参画が進み、地域の活力が高まることが、日本全体の活力向上、ウェルビーイングの向上につながる。
そのためにも、多様な生き方・価値観が尊重され、全ての人が性別にかかわらず、個性と能力を十分に発揮できる環境整備や魅力的な地域づくりの取組の推進が重要であり、そのような地域が、女性や若者にも選ばれる地域となるだろう。
26 国土交通省「企業等の東京一極集中に関する懇談会とりまとめ 市民向け国際アンケート調査結果」(令和3(2021)年1月29日)では、「東京圏流入者の移住の背景となった地元の事情として、男性は『仕事』や『進学先』関係の、女性は『地域の閉塞感』や『利便性』関係の割合が高い」と分析されている。
27 内閣官房「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査(令和5年人々のつながりに関する基礎調査)」(令和6(2024)年3月)では、孤独感が「しばしばある・常にある」と回答した人の割合は、男性が5.3%、女性が4.2%となっている。男女、年齢階級別にみると、男性では30代及び40代で、女性では20代で高くなっている。
28 総務省「労働力調査(詳細集計)」によると、令和6(2024)年時点で、女性の非正規の職員・従業員についた主な理由は、「自分の都合のよい時間に働きたいから」とした者の割合が36.0%と最も高く、次いで「家計の補助・学費等を得たいから」(20.6%)、「家事・育児・介護等と両立しやすいから」(15.5%)の順となっている。
29 女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム中間取りまとめ「男女間賃金格差の解消に向けた職場環境の変革」(令和6(2024)年6月5日)
30 厚生労働省「公的職業訓練の在り方に関する研究会報告書 働きながらでも学びやすい職業訓練の具体的な制度設計に関するとりまとめ」(令和5(2023)年9月5日)
31 内閣府「世界経済の潮流2024年I AIで変わる労働市場」(令和6(2024)年7月)
32 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、産業別にみた賃金(男女計)は、女性の就労の多い医療・福祉(306.4千円)より、情報通信業(391.0千円)の方が高くなっている。
33 内閣府「令和6年度地域における女性活躍・男女共同参画に関する調査」(令和6年度内閣府委託調査)(18~39歳が対象)によると、デジタルスキルについて、男女ともに5割以上が「今後、仕事で活用したい」と回答している。
34 「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム報告」(令和7(2025)年3月26日)
35 内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」(令和6(2024)年9月調査)によると、「総務省の『令和3年社会生活基本調査』によると、夫婦共働き世帯において1日の中で費やす時間を男女別に比較すると、育児・介護・家事に費やす時間は女性の方が長く、仕事に費やす時間は男性の方が長い現状となっています。このように、育児・介護・家事に女性の方がより多くの時間を費やしていることが、職業生活における女性の活躍が進まない要因の一つだという意見がありますが、あなたはこの意見について、どう思いますか。」と聞いたところ、女性の89%、男性の79%が「そう思う」又は「どちらかといえばそう思う」と回答している。
36 内閣府「地域の経済2023-地域における人手不足問題の現状と課題-」(令和5(2023)年12月)
37 政府では、起業に関心を持っている全国の女性を後押ししていくため、女性の起業に必要なサポートなどを話し合う「地域で輝く女性起業家サロン」を全国各地で開催している。
38 内閣府「地方公共団体における男女共同参画の視点からの防災・復興に係る取組状況について フォローアップ調査結果(概要)」(令和6(2024)年6月)
39 内閣府「地域課題分析レポート(2024年秋号)-ポストコロナ禍の若者の地域選択と人口移動-」(令和6(2024)年12月)では、地方に立地する大学の取組について紹介している。