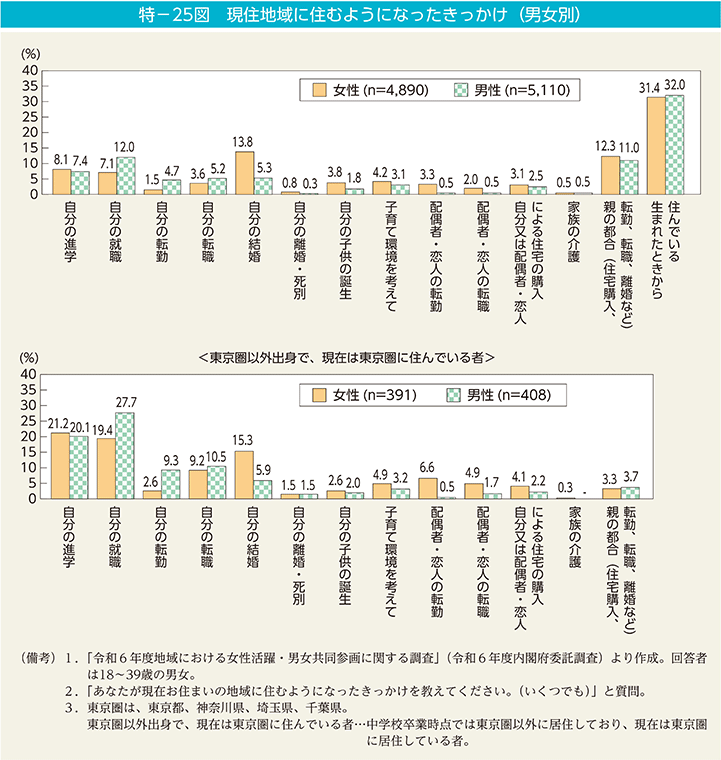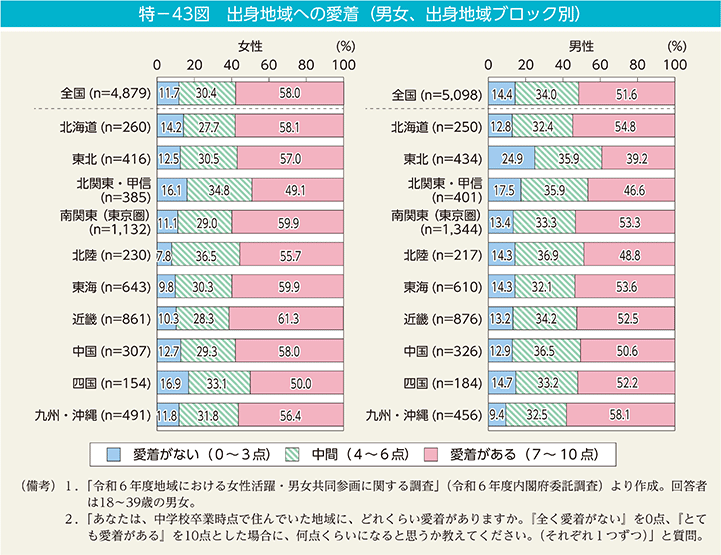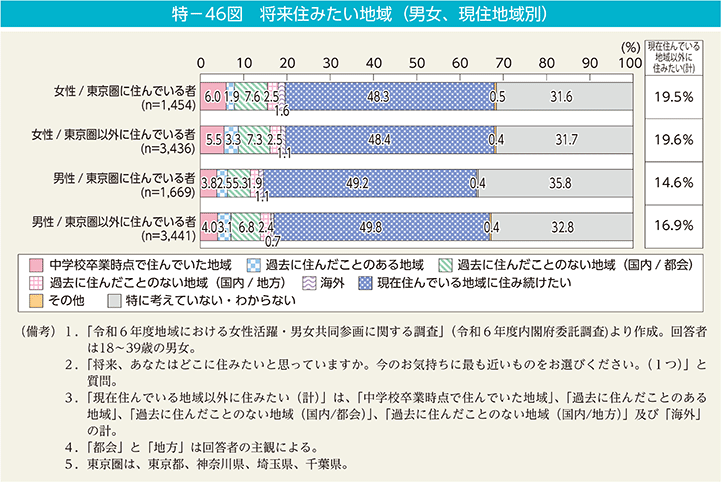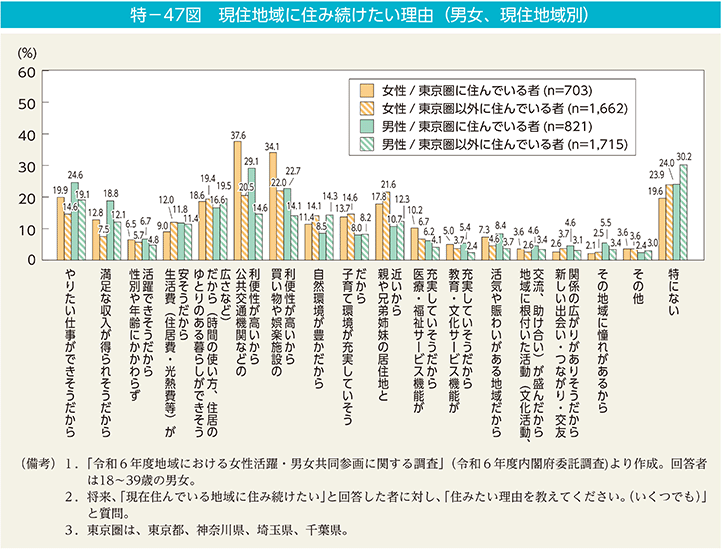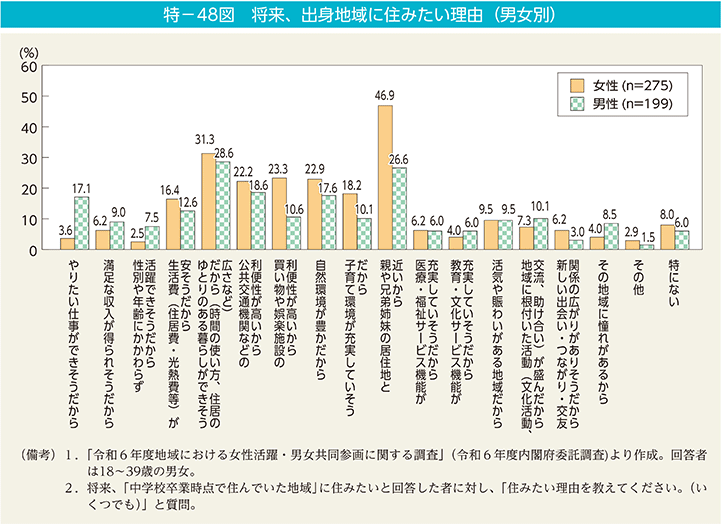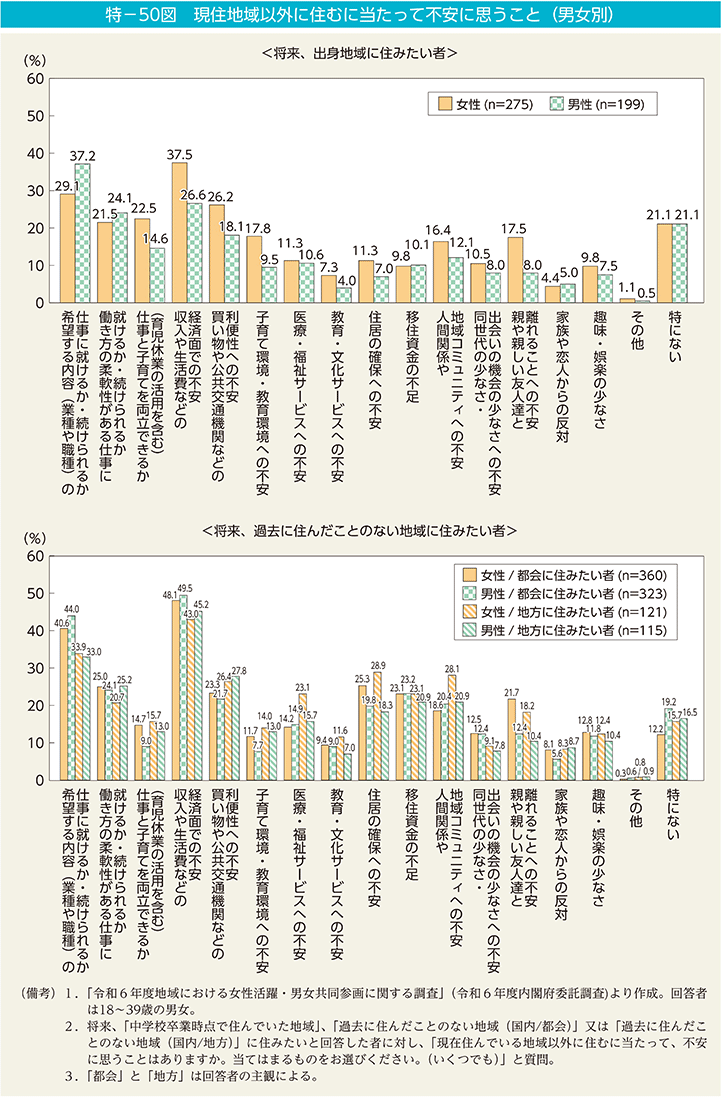本編 > 1 > 特集 > 第2節 若い世代の視点から見た地域への意識
第2節 若い世代の視点から見た地域への意識
本節では、内閣府の意識調査(国内在住の18~39歳の男女1万人が回答)22結果等を基に、若い世代の男女の意識、特に東京圏23以外から東京圏へ転出した者の意識に着目して、考察を深める。
22 内閣府「令和6年度地域における女性活躍・男女共同参画に関する調査」(令和6年度内閣府委託調査)。回答者は、国内在住の18~39歳のインターネット・モニター男女1万人(調査の概要は96頁を参照。)。以下、本文中に具体的な調査名がなく、「調査」と記載してあるものは、全て同調査の結果を引用している。
23 東京圏は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県。
1.若い世代の男女が出身地域を離れる理由
(1)出身地域を離れる理由
(現住地域に住むようになったきっかけ)
第1節で、近年、若い世代の女性が東京圏へ転出した後、東京圏に留まり、地元に戻らない傾向が強くなっていることを確認した(特-7図再掲)。
内閣府の調査で、若い世代が現住地域に住むようになったきっかけをみると、男女ともに「生まれたときから住んでいる」を挙げる者が3割、「親の都合(住宅購入、転勤、転職、離職など)」が1割となっている。それ以外の理由では、女性は「自分の結婚」が13.8%と高く、次いで、「自分の進学」、「自分の就職」の順となっている。一方、男性は、「自分の就職」が12.0%と高く、次いで、「自分の進学」、「自分の結婚」の順となっている。
東京圏以外出身24で、現在は東京圏に住んでいる者についてみると、女性は、「自分の進学」が21.2%と高く、次いで、「自分の就職」、「自分の結婚」の順となっている。一方、男性は、「自分の就職」が27.7%と高く、次いで、「自分の進学」、「自分の転職」の順となっている(特-25図)。
男女ともに、進学や就職が、東京圏への転出の大きなきっかけとなっていることが分かる。
24 調査では、現在住んでいる地域を「現住地域」、中学校卒業時点で住んでいた地域を「出身地域」としている。
(出身地域を離れた理由)
自分の都合で出身地域を離れた者について、出身地域を離れた理由をみると、「希望する進学先が少なかったから」を挙げる者の割合が、男女ともに最も高くなっている。特に、自分の都合で都会へ転居した女性では、35.0%と高くなっている。
都会へ転居した女性では、次いで、「やりたい仕事や就職先が少なかったから」、「地元から離れたかったから」の順となっている。一方、都会へ転居した男性では、次いで、「やりたい仕事や就職先が少なかったから」、「学校や職場に通いづらかったから」の順となっている。
都会へ転居した女性は、都会へ転居した男性に比べて、「地元から離れたかったから」、「希望する進学先が少なかったから」、「親や周囲の人の干渉から逃れたかったから」、「若者が楽しめる場所や施設が少なかったから」、「出会いやチャンスが少なそうだったから」が高くなっている(特-26図)。
特-26図 出身地域を離れた理由(男女、転居先別)(自分の都合で出身地域を離れた者)![]()
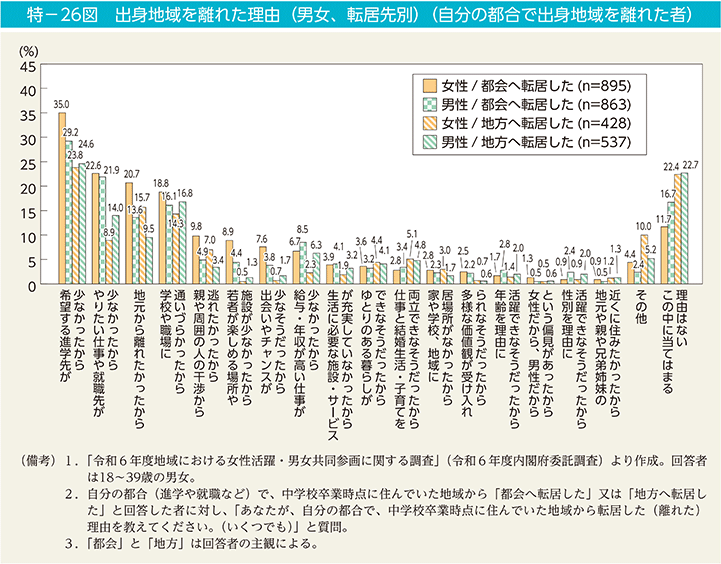
東京圏以外出身で、現在は東京圏に住んでいる者についてみると、男女ともに、「希望する進学先が少なかったから」が最も高く(女性42.1%、男性29.7%)、次いで、「やりたい仕事や就職先が少なかったから」、「地元から離れたかったから」の順となっている。
女性は、男性に比べて、「希望する進学先が少なかったから」、「地元から離れたかったから」、「親や周囲の人の干渉から逃れたかったから」等が高くなっている。一方、男性は、女性に比べて、「仕事と結婚生活・子育てを両立できなそうだったから」、「性別を理由に活躍できなそうだったから」が高くなっている(特-27図)。
特-27図 出身地域を離れた理由(男女別)(東京圏以外出身で、現在は東京圏に住んでいる者のうち、自分の都合で出身地域を離れた者)![]()
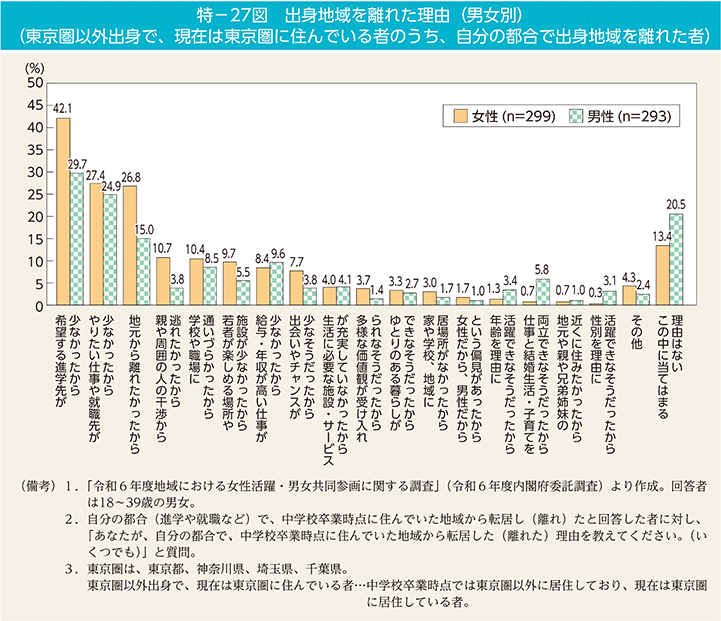
東京圏に転出した女性が、仕事や就職先の少なさと並んで「地元から離れたかったから」を理由として挙げていることは、特筆すべきことであると考えられる。
出身地域を離れた理由のうち、「地元から離れたかったから」に着目し、同理由を選択した者と選択していない者について、他の理由の選択状況を比べると、「地元から離れたかったから」を選択した者は、男女ともに、「親や周囲の人の干渉から逃れたかったから」、「若者が楽しめる場所や施設が少なかったから」、「出会いやチャンスが少なそうだったから」、「家や学校、地域に居場所がなかったから」、「生活に必要な施設・サービスが充実していなかったから」の選択割合が高くなっている。また、女性では、「多様な価値観が受け入れられなそうだったから」、「給与・年収が高い仕事が少なかったから」も高くなっている。
なお、「地元から離れたかったから」を選択した女性は、同理由を選択した男性に比べて、「親や周囲の人の干渉から逃れたかったから」、「給与・年収が高い仕事が少なかったから」、「多様な価値観が受け入れられなそうだったから」の選択割合が高くなっている(特-28図)。
特-28図 出身地域を離れた理由(男女、「地元から離れたかったから」の選択状況別)(自分の都合で出身地域を離れた者)![]()
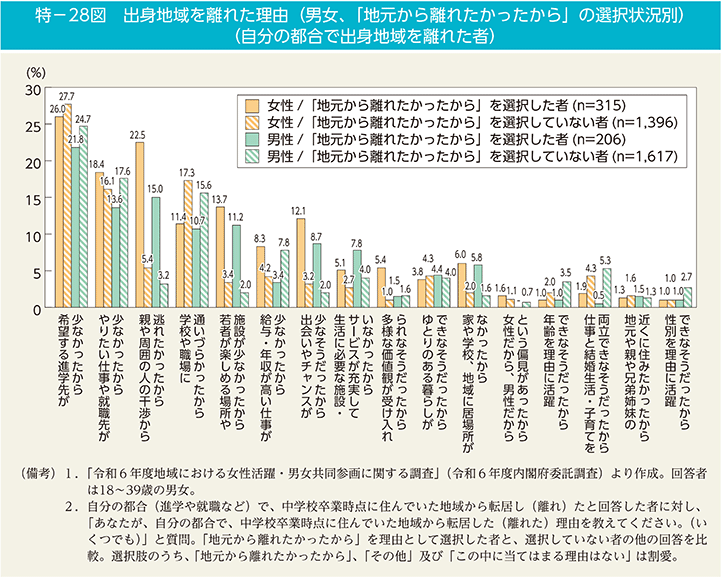
若い世代が出身地域を離れるきっかけや理由は、男女ともに、進学や就職を挙げる者の割合が高くなっている。しかしながら、それ以外にも、男女ともに、固定的な性別役割分担意識や伝統的な価値観が残る地元に生きづらさを感じて他の地域、特に都会へと転出していることがうかがえる。
以降では、若い世代が進学先や就職先の選択の際に重視していることや、若い世代の男女が感じている固定的な性別役割分担意識等について、深掘りしていく。
(大学等への進学を検討した際に重視したこと)
進学は、若い世代の男女が東京圏へ転出する大きなきっかけ・理由となっている。そこで、東京圏以外出身者のうち、大学等への進学者について、進学を検討した際に重視したことを確認する。
現在は東京圏に住んでいる者では、男女ともに、「学びたい学部・学科・コース」を重視した者の割合が最も高く、次いで、「偏差値・レベル」、「学生生活が楽しめそうか」の順となっている。
現在も東京圏以外に住んでいる者でも、男女ともに、「学びたい学部・学科・コース」を重視した者の割合が最も高いが、女性は、次いで、「学生生活が楽しめそうか」、「親や家族の意見」、「そのとき住んでいた家から通える範囲にあるか」の順、男性は、次いで、「偏差値・レベル」、「学生生活が楽しめそうか」、「学生生活にかかる費用(学費・交通費・生活費など)」の順となっている。
現在は東京圏に住んでいる女性は、現在も東京圏以外に住んでいる女性に比べて、「偏差値・レベル」、「家を出ることができるか・一人暮らしができるか」、「知名度、ブランド力」、「学びたい学部・学科・コース」が高く、現在も東京圏以外に住んでいる女性は、現在は東京圏に住んでいる女性に比べて、「そのとき住んでいた家から通える範囲にあるか」、「資格取得に有利か」、「学生生活にかかる費用(学費・交通費・生活費など)」等が高くなっている。
一方、現在は東京圏に住んでいる男性は、現在も東京圏以外に住んでいる男性に比べて、「家を出ることができるか・一人暮らしができるか」、「知名度・ブランド力」、「偏差値・レベル」が高く、現在も東京圏以外に住んでいる男性は、現在は東京圏に住んでいる男性に比べて、「そのとき住んでいた家から通える範囲にあるか」が高くなっている(特-29図)。
特-29図 大学等への進学を検討した際に重視したこと(男女・現住地域別)(東京圏以外出身者のうち、大学等への進学者)![]()
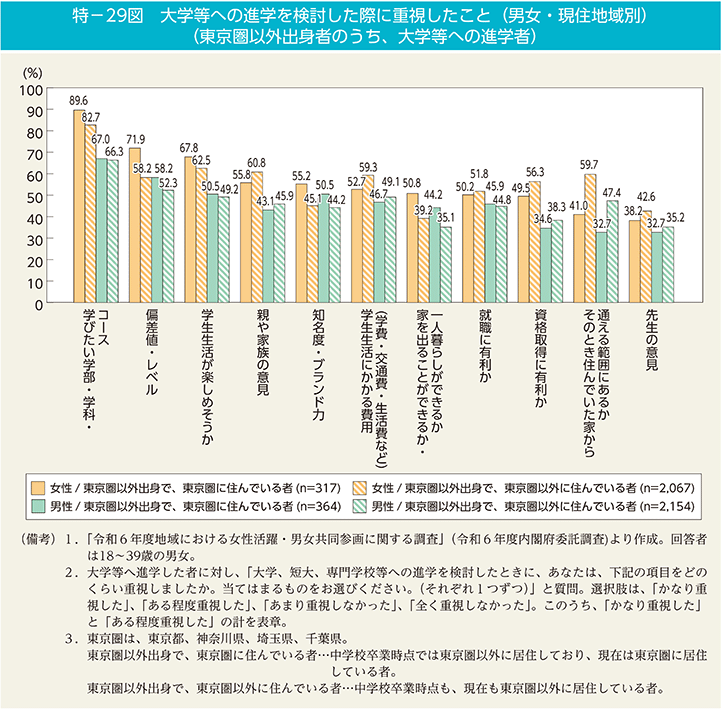
(大学等への進路の検討に関する意見)
東京圏以外出身者について、大学等の進路の検討に関する意見を確認する。
女性は、現在は東京圏に住んでいる者、現在も東京圏以外に住んでいる者のいずれも、「地域を問わず、希望する学校に進学した方がよい」でそう思う者の割合が最も高く、次いで、「資格取得に有利な学校に進学した方がよい」、「できるだけ偏差値が高い学校を目指した方がよい」の順となっている。
一方、現在は東京圏に住んでいる男性では、「できるだけ偏差値が高い学校を目指した方がよい」が最も高く、次いで、「地域を問わず、希望する学校に進学した方がよい」、「国公立の学校に進学した方がよい」の順、現在も東京圏以外に住んでいる男性では、「地域を問わず、希望する学校に進学した方がよい」が最も高く、次いで、「資格取得に有利な学校に進学した方がよい」、「できるだけ偏差値が高い学校を目指した方がよい」の順となっている。
現在は東京圏に住んでいる女性は現在も東京圏以外に住んでいる女性に比べて、「できるだけ偏差値が高い学校を目指した方がよい」、「都会の学校に進学した方がよい」、「地域を問わず、希望する学校に進学した方がよい」等が高く、現在も東京圏以外に住んでいる女性は、現在は東京圏に住んでいる女性に比べて、「地元の学校に進学した方がよい」が高くなっている。
一方、現在は東京圏に住んでいる男性は、現在も東京圏以外に住んでいる男性に比べて、「できるだけ偏差値が高い学校を目指した方がよい」、「希望する学校と違っても、現役で進学した方がよい」、「国公立の学校に進学した方がよい」等が高くなっている(特-30図)。
特-30図 大学等への進路の検討に関する意見(男女・現住地域別)(東京圏以外出身者)![]()
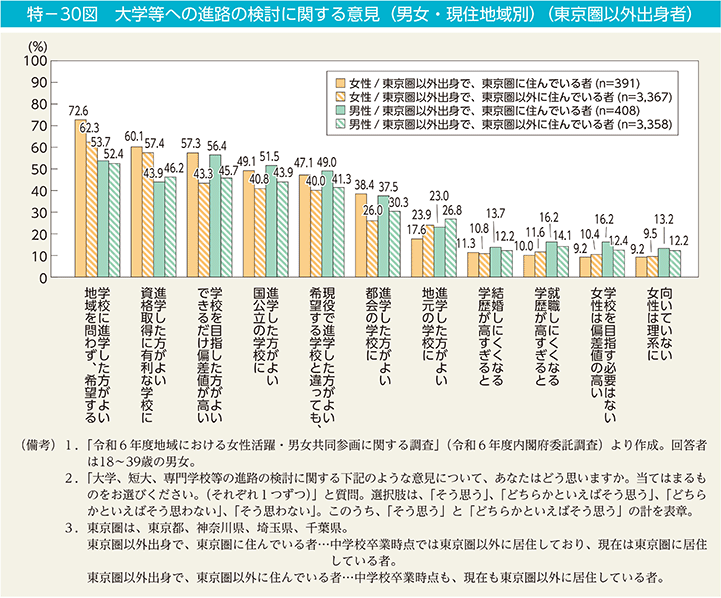
(進路選択に影響を与えるもの)
内閣府の世論調査で、一般的に進路選択に影響を与えると思うものについてみると、男女ともに、「母親」を挙げる者の割合が最も高く、次いで、「父親」となっており、両親からの影響が非常に大きいことがわかる。
なお、女性は、男性に比べて、「母親」、「学校での職場体験」、「塾や習い事など、学校以外の先生」が高くなっている。一方、男性は、女性に比べて、「友人や先輩」が高くなっている(特-31図)。
特-31図 進路選択に影響を与えるもの(男女別・令和6(2024)年)![]()
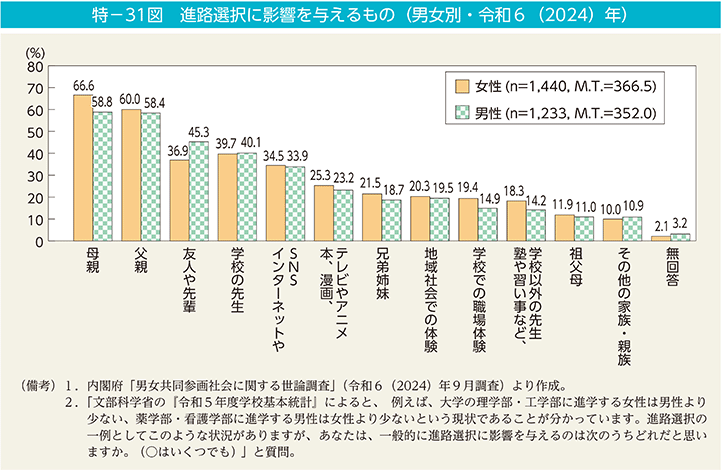
(仕事に就く際に重視したこと)
仕事や就職先もまた、若い世代の男女が東京圏へ転出する大きなきっかけ・理由となっている。そこで、東京圏以外出身者のうち、働いたことがある者について、仕事に就くに当たって重視したことを確認する。
現在は東京圏に住んでいる者、現在も東京圏以外に住んでいる者のいずれも、男女ともに「仕事内容が自分の希望にあっているか」を重視した者の割合が最も高くなっている。
現在は東京圏に住んでいる女性では、「給与や収入が自分の希望にあっているか」が2番目に高く、次いで、「労働時間が自分の希望にあっているか」、「自分の学んだことや能力を活かせそうか」の順、現在も東京圏以外に住んでいる女性では、「労働時間が自分の希望にあっているか」が2番目に高く、次いで、「給与や収入が自分の希望にあっているか」、「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」の順となっている。
一方、現在は東京圏に住んでいる男性では、「給与や収入が自分の希望にあっているか」が2番目に高く、次いで、「労働時間が自分の希望にあっているか」、「自分の学んだことや能力を活かせそうか」及び「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」の順、現在も東京圏以外に住んでいる男性では、「給与や収入が自分の希望にあっているか」が2番目に高く、次いで、「労働時間が自分の希望にあっているか」、「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」、「自分の学んだことや能力を活かせそうか」の順となっている。
現在は東京圏に住んでいる女性は、現在も東京圏以外に住んでいる女性に比べて、「親元を離れて自立できそうか」、「自分の学んだことや能力を活かせそうか」、「仕事内容が自分の希望にあっているか」、「仕事を通じて自分が成長できそうか」が高く、現在も東京圏以外に住んでいる女性は、現在は東京圏に住んでいる女性に比べて、「実家や住んでいる家から通いやすいか」が高くなっている。
一方、現在は東京圏に住んでいる男性は、現在も東京圏以外に住んでいる男性に比べて、「自分の学んだことや能力を活かせそうか」、「仕事内容が自分の希望にあっているか」、「親元を離れて自立できそうか」、「給与や収入が自分の希望にあっているか」が高く、現在も東京圏以外に住んでいる男性は、現在は東京圏に住んでいる男性に比べて、「実家や住んでいる家から通いやすいか」が高くなっている(特-32図)。
特-32図 仕事に就くに当たって重視したこと(男女、現住地域別)(東京圏以外出身者のうち、働いたことがある者)![]()
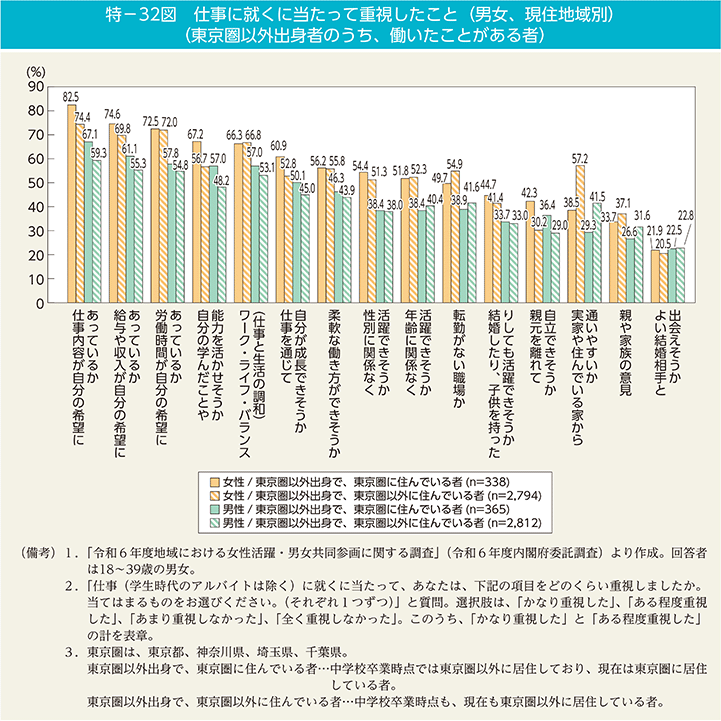
(仕事や就職先の検討に関する意見)
東京圏以外出身者について、仕事や就職先の検討に関する意見を確認する。
現在は東京圏に住んでいる者、現在も東京圏以外に住んでいる者のいずれも、男女ともに「安定した仕事に就いた方がよい」でそう思う割合が最も高くなっている。
現在は東京圏に住んでいる女性では、「収入が高い仕事に就いた方がよい」が2番目に高く、次いで、「残業がない又は少ない仕事に就いた方がよい」、「家庭や子育てと両立しやすい仕事に就いた方がよい」の順、現在も東京圏以外に住んでいる女性では、「残業がない又は少ない仕事に就いた方がよい」が2番目に高く、次いで、「家庭や子育てと両立しやすい仕事に就いた方がよい」、「収入が高い仕事に就いた方がよい」の順となっている。
一方、現在は東京圏に住んでいる男性では、「収入が高い仕事に就いた方がよい」が2番目に高く、次いで、「家庭や子育てと両立しやすい仕事に就いた方がよい」の順、現在も東京圏以外に住んでいる男性でも、「収入が高い仕事に就いた方がよい」が2番目に高く、次いで、「残業がない又は少ない仕事に就いた方がよい」の順となっている。
現在は東京圏に住んでいる女性は、現在も東京圏以外に住んでいる女性に比べて、「都会で働いた方がよい」、「能力や学歴を活かせる仕事に就いた方がよい」、「キャリアアップを目指した方がよい」、「収入が高い仕事に就いた方がよい」等が高く、現在も東京圏以外に住んでいる女性は、現在は東京圏に住んでいる女性に比べて、「地元や親の近くで働いた方がよい」が高くなっている。一方、男性は、女性ほど大きな差はないものの、「都会で働いた方がよい」は、現在は東京圏に住んでいる者の方が高くなっている(特-33図)。
特-33図 仕事や就職先の検討に関する意見(男女、現住地域別)(東京圏以外出身者)![]()
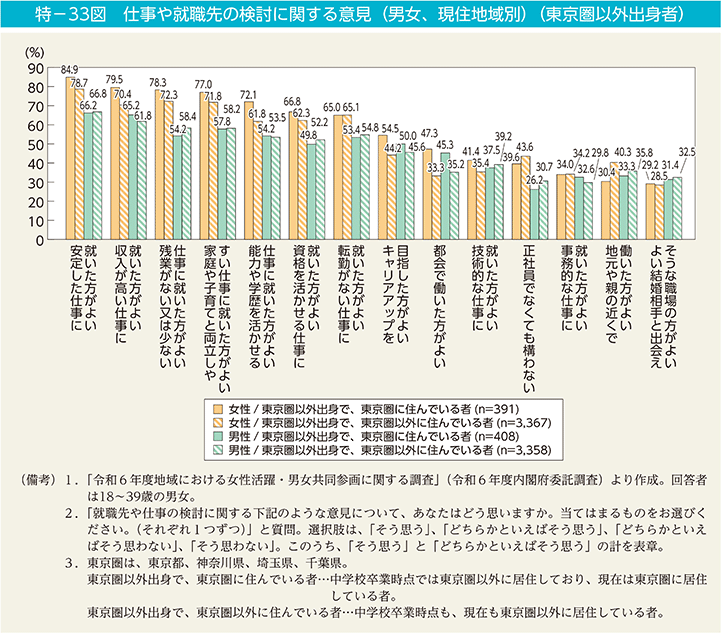
(2)固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みの現状
(夫は仕事、妻は家庭という考え方に関する意識)
内閣府の世論調査によると、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方については、男女ともに「賛成(計)」(「賛成」と「どちらかといえば賛成」の計。)とする者の割合(女性29.3%、男性37.5%)よりも、「反対(計)」(「反対」と「どちらかといえば反対」の計。)とする者の割合(女性69.2%、男性59.7%)の方が高くなっている。なお、「反対(計)」とする者の割合は、女性の方が高く、「賛成(計)」とする者の割合は男性の方が高くなっている。
男女ともに全ての年代で「反対(計)」が「賛成(計)」を上回っているが、若い年代の方が「反対(計)」とする者の割合が高い傾向にあり、18~29歳では女性の79.7%、男性の70.2%が「反対(計)」としている。
また、調査方法が異なるため、令和元(2019)年以前の結果と直接比較はできないものの、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に、「賛成(計)」とする者の割合は低下し、「反対(計)」とする者の割合は上昇する傾向にある(特-34図)。
特-34図 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に関する意識(男女別・令和6(2024)年)![]()
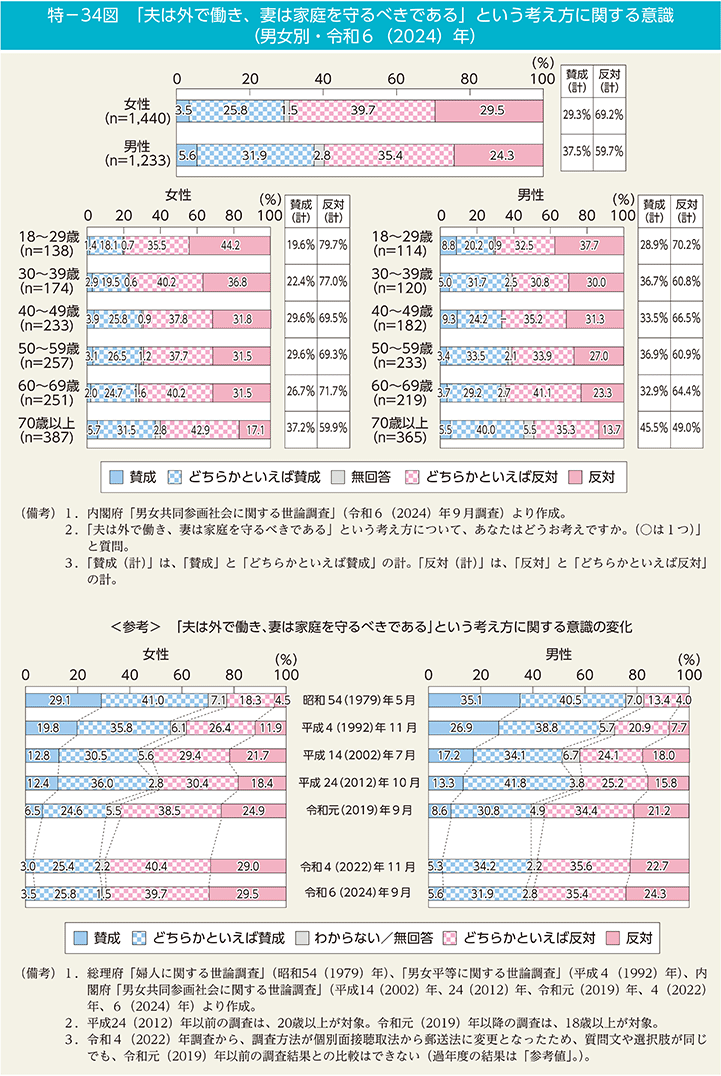
(現住地域における固定的な性別役割分担意識等の有無)
内閣府の調査で、現住地域や勤務先における固定的な性別役割分担意識等の有無についてみると、「ある(計)」(「よくある」と「時々ある」の計。)と感じている者の割合は、全ての項目で、女性の方が高くなっている。
項目別にみると、女性では、「家事・育児・介護は女性の仕事」が24.9%と最も高く、次いで、「地域や親戚の集まりでの食事の準備やお茶出しは女性の仕事」、「職場でのお茶出しや事務などのサポート業務は女性の仕事」の順となっている。
一方、男性では、「自治会などの重要な役職は男性の仕事」が16.6%と最も高く、次いで、「個人の価値観よりも世間体が大事」、「地域や親戚の集まりでの食事の準備やお茶出しは女性の仕事」及び「家を継ぐのは男性がよい」の順となっている。
男女差(女性-男性)をみると、「家事・育児・介護は女性の仕事」、「職場でのお茶出しや事務などのサポート業務は女性の仕事」、「地域や親戚の集まりでの食事の準備やお茶出しは女性の仕事」、「子供が生まれたら、女性は仕事を控えめにした方がよい」の順で差が大きくなっている。
なお、現住地域ブロック別にみると、女性では、ほとんどの項目で、南関東(東京圏)で「ある(計)」と感じている者の割合が最も低くなっている(特-35図)。
特-35図 現住地域や勤務先における固定的な性別役割分担意識等の有無(男女、現住地域ブロック別)![]()
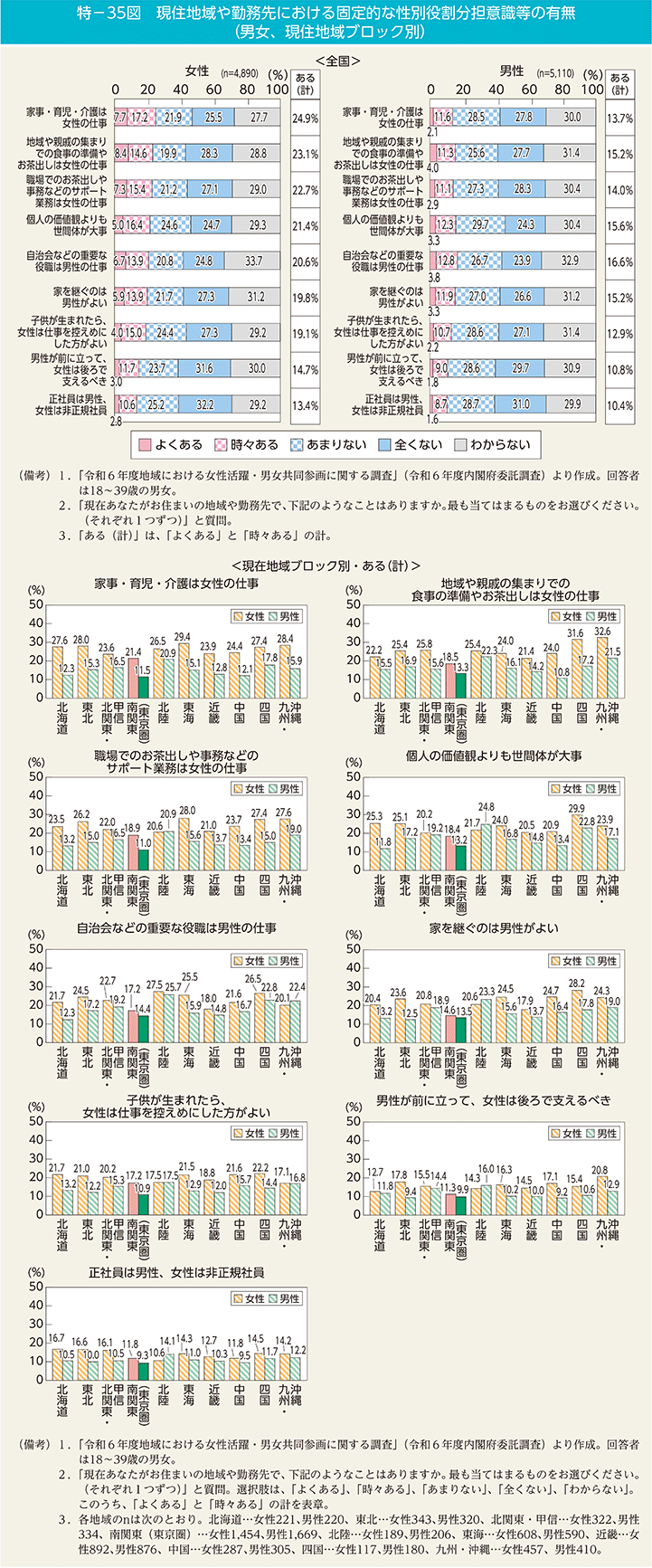
(出身地域における固定的な性別役割分担意識等の有無)
出身地域における固定的な性別役割分担意識等の有無についてみると、「あった(計)」(「よくあった」と「時々あった」の計。)と感じている者の割合は、全ての項目で、女性の方が高くなっている。
項目別にみると、女性では、「地域や親戚の集まりでの食事の準備やお茶出しは女性の仕事」が30.0%と最も高く、次いで、「家事・育児・介護は女性の仕事」、「職場でのお茶出しや事務などのサポート業務は女性の仕事」の順となっている。
一方、男性では、「地域や親戚の集まりでの食事の準備やお茶出しは女性の仕事」が20.4%と最も高く、次いで、「自治会などの重要な役職は男性の仕事」、「家を継ぐのは男性がよい」の順となっている。
男女差(女性-男性)をみると、「家事・育児・介護は女性の仕事」、「地域や親戚の集まりでの食事の準備やお茶出しは女性の仕事」、「職場でのお茶出しや事務などのサポート業務は女性の仕事」、「個人の価値観よりも世間体が大事」の順で差が大きくなっている。
なお、出身地域ブロック別にみると、女性では、ほとんどの項目で、南関東(東京圏)で「あった(計)」と感じている者の割合が最も低くなっている(特-36図)。
特-36図 出身地域における固定的な性別役割分担意識等の有無(男女、出身地域ブロック別)![]()
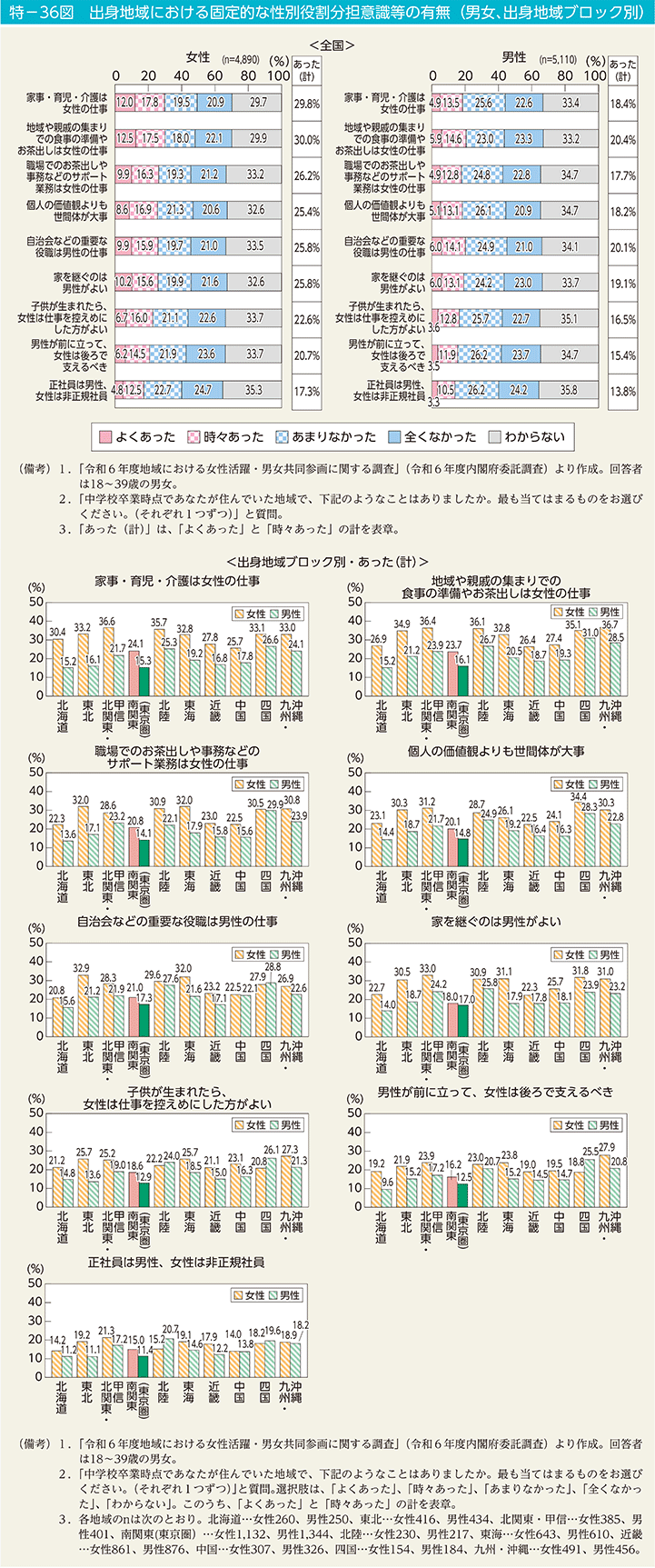
また、東京圏以外出身者についてみると、現在は東京圏に住んでいる女性は、現在も東京圏以外に住んでいる女性に比べて、出身地域において、固定的な性別役割分担意識等があったと感じている割合が顕著に高くなっている。特に、「家事・育児・介護は女性の仕事」、「家を継ぐのは男性がよい」、「地域や親戚の集まりでの食事の準備やお茶出しは女性の仕事」、「個人の価値観よりも世間体が大事」等で差が大きくなっている。
一方、男性は、現在は東京圏に住んでいる者と、現在も東京圏以外に住んでいる者で、固定的な性別役割分担意識等があったと感じている割合にあまり差がない。
また、現在も東京圏以外に住んでいる者の男女差(女性-男性)をみると、「家事・育児・介護は女性の仕事」、「地域や親戚の集まりでの食事の準備やお茶出しは女性の仕事」、「職場でのお茶出しや事務などのサポート業務は女性の仕事」等で差が大きくなっている(特-37図)。
特-37図 出身地域における固定的な性別役割分担意識等(男女、現住地域別)(東京圏以外出身者)![]()
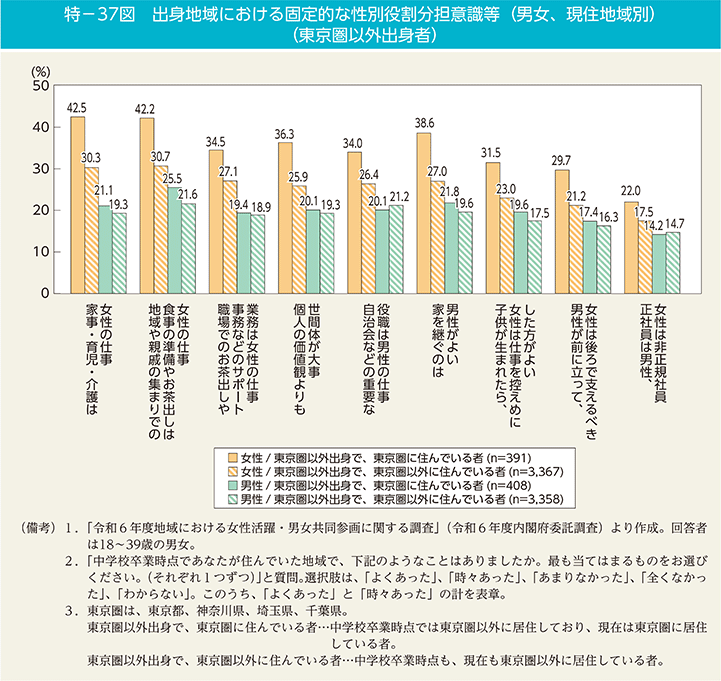
東京圏以外出身者について、出身地域及び現住地域における固定的な性別役割分担意識等の有無を比較すると、女性では、現在は東京圏に住んでいる者の方が、出身地域であったと感じている割合が高く、現住地域であると感じている割合が低くなっている。
時代による意識の変化などもあり、現在も東京圏以外に住んでいる女性も、出身地域にあったと感じている割合よりも、現住地域にあると感じている割合の方が低くなっているが、現在は東京圏に住んでいる女性ではその差がより顕著になっている。
男性も同様の傾向にあるものの、女性に比べると出身地域と現住地域の差及び東京圏と東京圏以外の差は小さくなっている(特-38図)。
特-38図 出身地域と現住地域における固定的な性別役割分担意識等(男女、現住地域別)(東京圏以外出身者)![]()
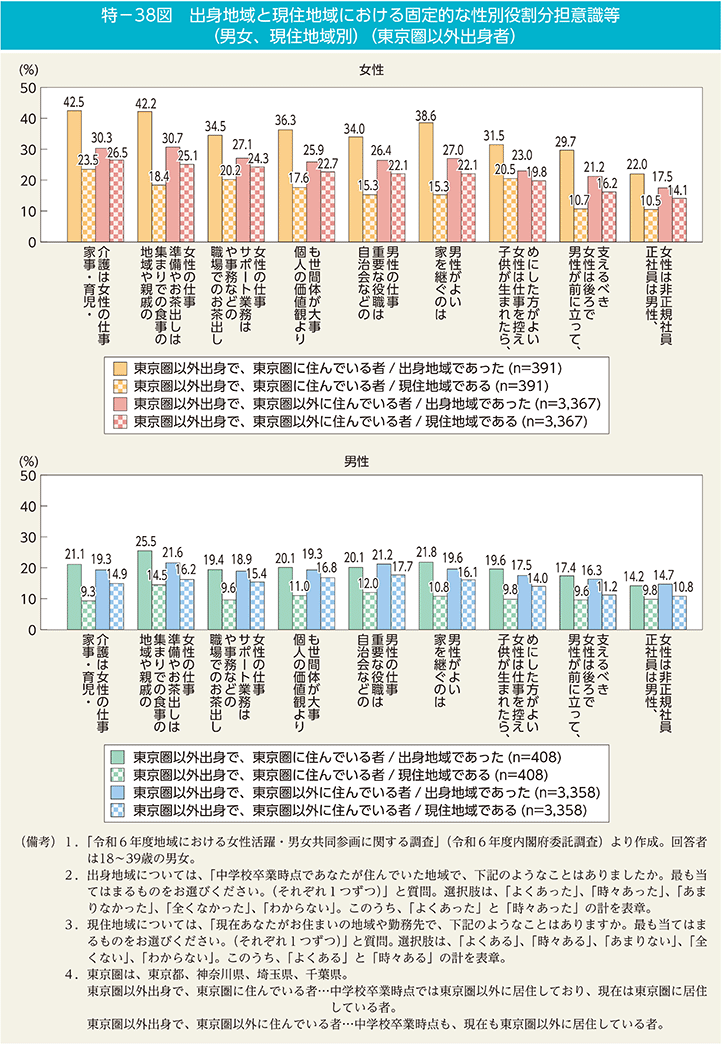
前述のとおり、女性は、出身地域を離れた理由として、「地元から離れたかったから」を挙げる割合が高くなっている(特-26図、特-27図再掲)。
そこで、自分の都合で出身地域を離れた者について、出身地域を離れた理由として、「地元から離れたかったから」を選択した者と、選択していない者を比較すると、「地元から離れたかったから」を選択した女性は、出身地域における固定的な性別役割分担意識等があったと感じている者の割合が顕著に高くなっている。
「地元から離れたかったから」を選択した女性と、選択していない女性を比べると、「個人の価値観よりも世間体が大事」で最も差が大きく、次いで、「家事・育児・介護は女性の仕事」、「地域や親戚の集まりでの食事の準備やお茶出しは女性の仕事」、「家を継ぐのは男性がよい」の順で差が大きくなっている。
男性についてみても、「地元から離れたかったから」を選択した者は、選択していない者に比べて、出身地域における固定的な性別役割分担意識等があったと感じている者の割合が高くなっているが、女性と比べると差が小さくなっている。
固定的な性別役割分担意識等の存在は、若い世代の男女の「地元から離れたい」という意識に大きく影響していると推測される(特-39図)。
特-39図 出身地域における固定的な性別役割分担意識等と地元から離れたいという意識の関係(男女、「地元から離れたかったから」の選択状況別)(自分の都合で出身地域を離れた者)![]()
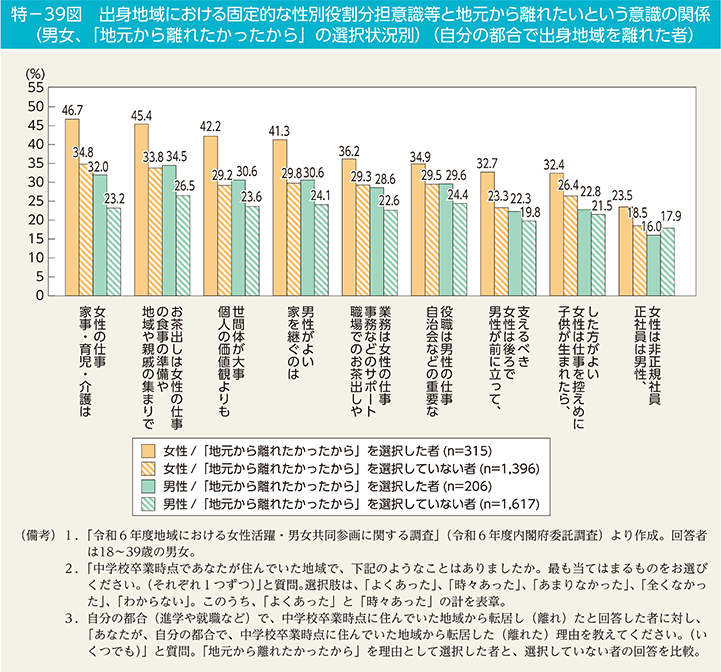
このように、若い世代の女性が、地方から都会へ移動する背景の一つに出身地域における固定的な性別役割分担意識等が関係していることがうかがえる。また、出身地域における固定的な性別役割分担意識等が強いと感じている女性ほど、出身地域への愛着が低くなる傾向があるとの指摘もあり25、進学等で東京圏へ転出した女性が、地元に戻ることへの心理的な障壁となっている可能性がある。
また、若い世代の人々が、現在も依然として、都市でも地方でも、固定的な性別役割分担意識等があると感じている一方で、男女によって認識に差があり、同じような環境・場面に遭遇していても、男性はその存在に気付いていなかったり、無関心に過ごしていたりする可能性がある。
25 内閣府「令和6年度地域における女性活躍・男女共同参画に関する調査」(令和6年度内閣府委託調査)調査検討委員会 高見 具広委員(独立行政法人労働政策研究・研修機構主任研究員)による分析結果より。詳細は、同調査の報告書を参照。
2.若い世代の男女が住みたいと思う地域とは
(1)現住地域や仕事に満足しているか
(現住地域に満足しているか)
現住地域に満足している者(「満足」と「どちらかといえば満足」の計。)の割合をみると、女性では、南関東(東京圏)で最も高く、次いで、東海、近畿の順となっている。一方、男性では、南関東(東京圏)が最も高く、次いで、東海、北海道、近畿の順となっている。
満足していない者(「どちらかといえば不満」と「不満」の計。)の割合をみると、女性では、四国が最も高く、次いで、東北、北陸、北関東・甲信の順となっている。一方、男性では、東北が最も高く、次いで、中国、四国、北関東・甲信の順となっている。
項目別にみると、「仕事の選択肢の豊富さ」、「仕事による収入の妥当性」、「公共交通機関などの利便性」、「買い物や娯楽施設の利便性」、「性別・年齢にかかわらず活躍できる環境」、「多様な生き方・価値観の尊重」、「新しい出会いやつながり・交友関係の広がり」等は、南関東(東京圏)で高くなっている(特-40図)。
特-40図 現住地域に満足している者の割合(男女、現住地域ブロック別)![]()
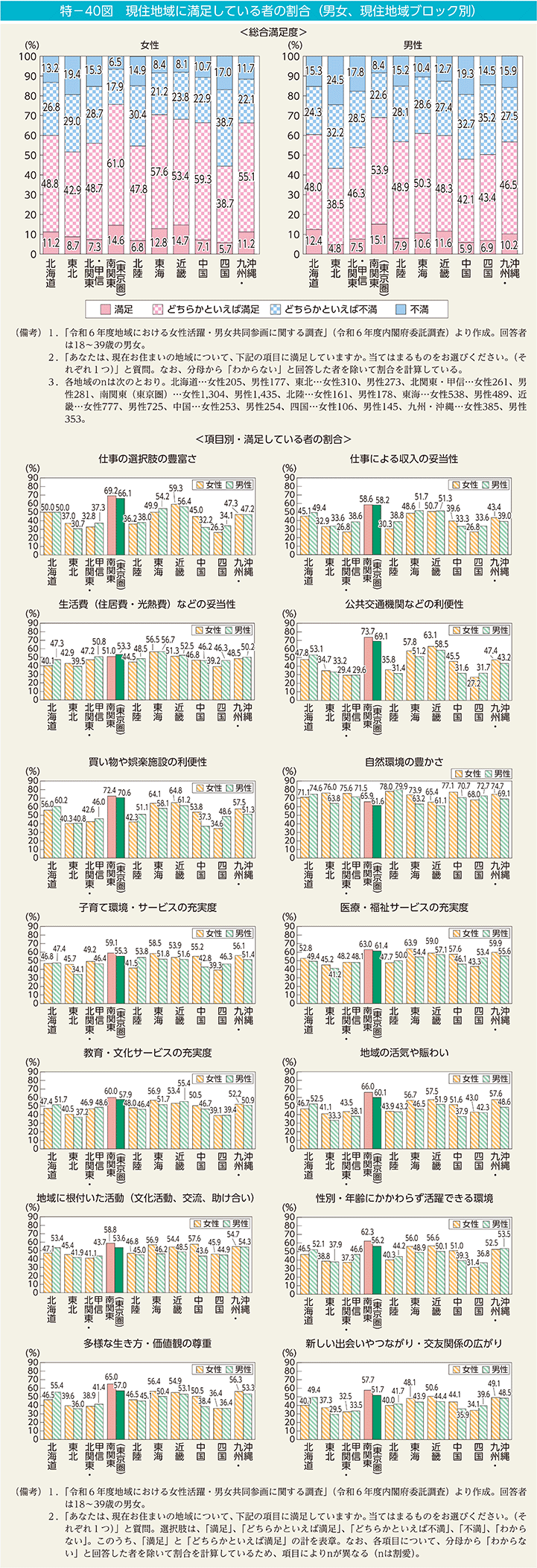
東京圏以外出身者について、現住地域に満足している者の割合をみると、総合では、現在は東京圏に住んでいる女性が77.2%と最も高くなっている。
現在は東京圏に住んでいる者と現在も東京圏以外に住んでいる者を比べると、男女ともにほとんどの項目で現在は東京圏に住んでいる者の方が満足している者の割合が高くなっている。特に、「仕事の選択肢の豊富さ」、「公共交通機関などの利便性」、「買い物や娯楽施設の利便性」、「仕事による収入の妥当性」、「地域の活気や賑わい」等で差が大きくなっている。なお、女性では、「多様な生き方・価値観の尊重」、「新しい出会いやつながり・交友関係の広がり」、「性別・年齢にかかわらず活躍できる環境」等でも差が大きくなっている。
一方、「自然環境の豊かさ」は、男女ともに、現在も東京圏以外に住んでいる者の方が、満足している者の割合が高くなっている。
また、現在は東京圏に住んでいる者についてみると、女性は、男性に比べて、「性別・年齢にかかわらず活躍できる環境」、「多様な生き方・価値観の尊重」、「新しい出会いやつながり・交友関係の広がり」等で満足している者の割合が高くなっている(特-41図)。
特-41図 現住地域に満足している者の割合(男女、現住地域別)(東京圏以外出身者)![]()
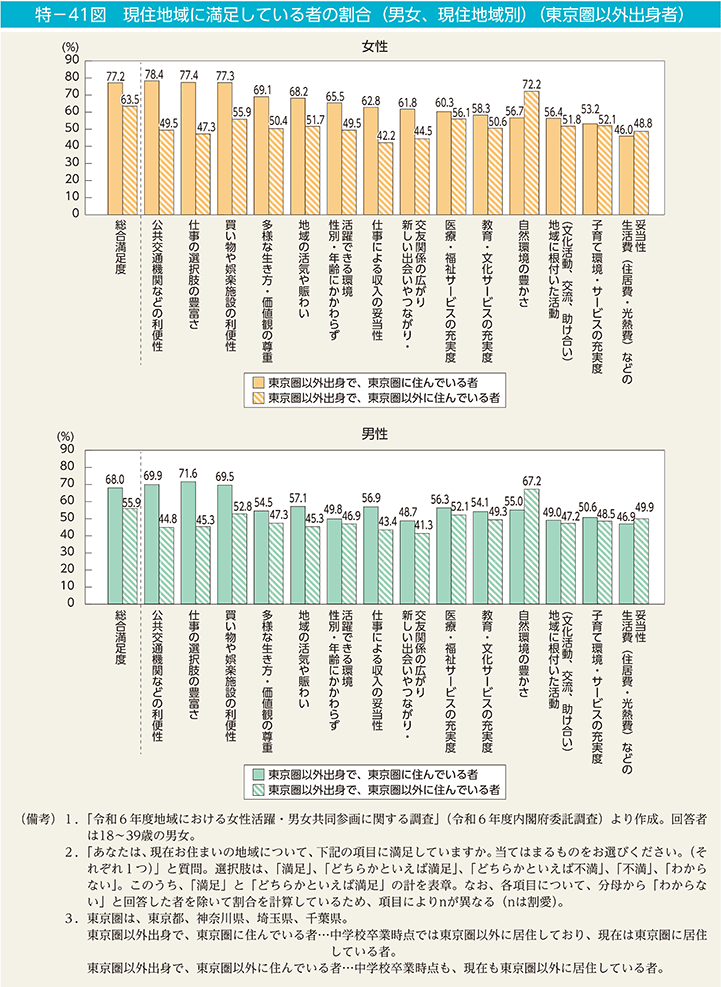
(現在の仕事に満足しているか)
東京圏以外出身で働いている者について、現在の仕事に満足している者の割合をみると、総じて、現在も東京圏以外に住んでいる女性よりも現在は東京圏に住んでいる女性の方が高くなっている。
現在は東京圏に住んでいる女性は、現在も東京圏以外に住んでいる女性に比べて、「仕事内容について、男女の差異がないか」、「昇進や給与等について、男女の差異がないか」、「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」で満足している者の割合が高くなっている。
男性は、現在は東京圏に住んでいる者と現在も東京圏以外に住んでいる者で、あまり差はない(特-42図)。
特-42図 現在の仕事に満足している者の割合(男女、現住地域別)(東京圏以外出身者のうち、働いている者)![]()
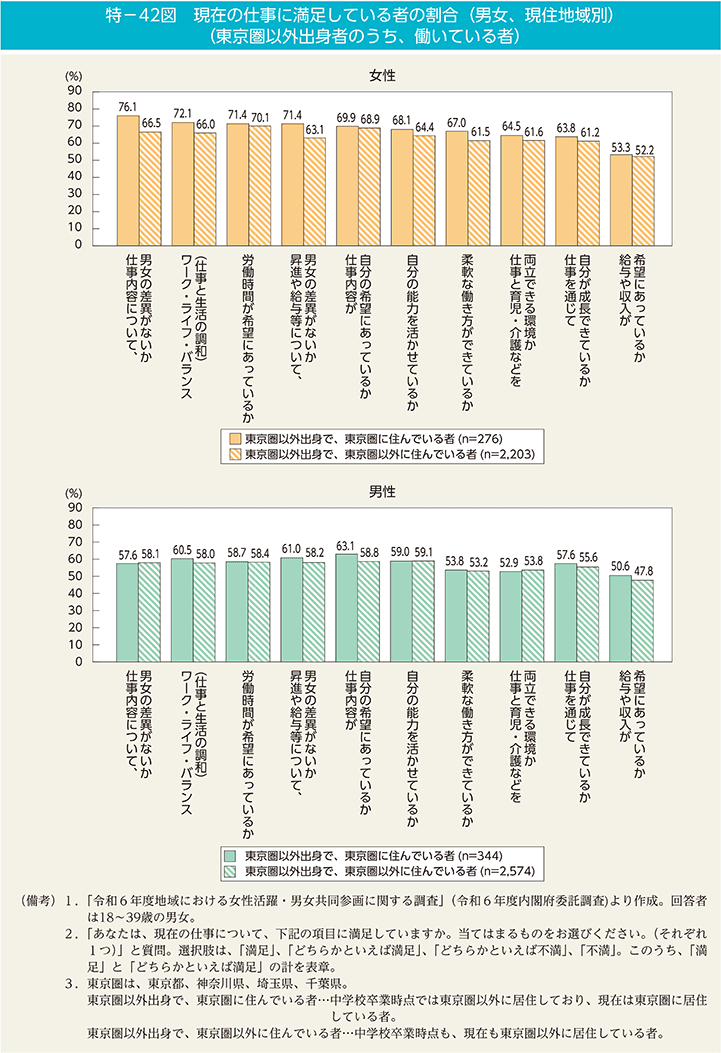
東京圏には、企業の本社や大企業が多いことから、仕事内容や昇進等における男女平等や、ワーク・ライフ・バランス実現のための取組が進んでおり、東京圏以外に比べて、仕事で女性が活躍しやすい環境が整っており、女性の仕事における満足感につながっている可能性がある。
(2)地域への愛着
(出身地域への愛着)
出身地域に「愛着がある(7~10点)」とする者の割合は、男性(51.6%)に比べて、女性(58.0%)の方が高くなっている。
「愛着がある(7~10点)」とする者の割合を地域ブロック別にみると、女性は、近畿で61.3%と最も高く、次いで、南関東(東京圏)及び東海の順となっている。一方、男性は、九州・沖縄で58.1%と最も高く、次いで、北海道、東海の順となっている。
「愛着がない(0~3点)」とする者の割合をみると、女性は、四国で16.9%と最も高く、次いで、北関東・甲信、北海道の順となっている。一方、男性は、東北で24.9%と最も高く、次いで、北関東・甲信、四国の順となっている(特-43図)。
(出身地域と現住地域への愛着)
東京圏以外出身で現在は東京圏に住んでいる者について、地域に「愛着がある(7~10点)」とする者の割合をみると、現住地域への愛着よりも、出身地域への愛着の方が高くなっている。
特に女性では、現住地域に「愛着がある(7~10点)」とする者の割合が37.6%であるのに対し、出身地域に「愛着がある(7~10点)」とする者の割合は62.9%となっている。
また、現在も東京圏以外に住んでいる女性よりも、現在は東京圏に住んでいる女性の方が、出身地域に「愛着がある(7~10点)」とする者の割合が高くなっている(特-44図)。
特-44図 出身地域及び現住地域への愛着(男女、現住地域別)(東京圏以外出身者)![]()
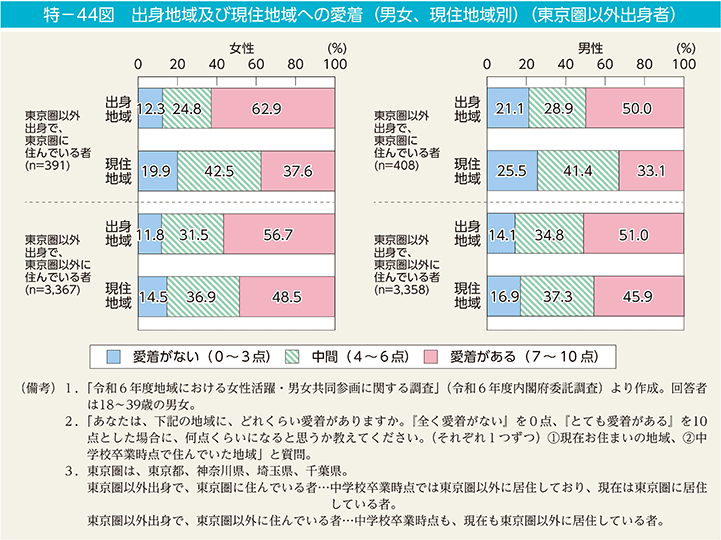
(3)将来の居住地域への希望と不安
都道府県・市町村の移住相談窓口等において受けた相談件数は、コロナ下であった令和2(2020)年度を除き、年々増加しており、令和5(2023)年度は40万8,435件と過去最多となっている(特-45図)。
特-45図 移住相談窓口等における相談受付件数(令和5(2023)年度)![]()
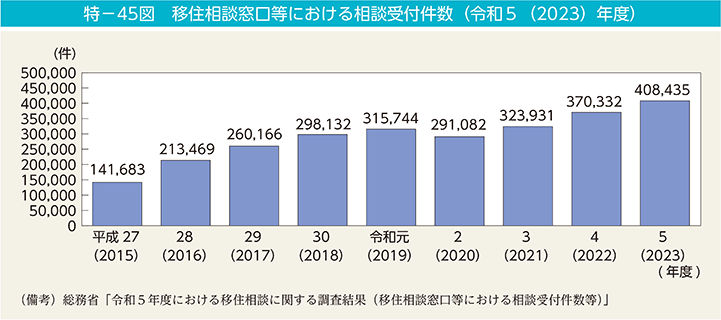
(将来住みたい地域)
内閣府の調査で、将来住みたい地域についてみると、「現在住んでいる地域に住み続けたい」とする者の割合が男女ともに5割となっている。
一方、「現在住んでいる地域以外に住みたい(計)」とする割合は、東京圏に住んでいる女性では19.5%、東京圏以外に住んでいる女性では19.6%、東京圏に住んでいる男性では14.6%、東京圏以外に住んでいる男性では16.9%と、女性の方が高くなっている(特-46図)。
(現住地域に住み続けたい理由)
将来も現在住んでいる地域に住み続けたい理由をみると、東京圏に住んでいる者では、男女ともに「公共交通機関などの利便性が高いから」を挙げる割合が最も高くなっている(女性37.6%、男性29.1%)。女性は、次いで、「買い物や娯楽施設の利便性が高いから」、「やりたい仕事ができそうだから」の順となっている。一方、男性は、次いで、「やりたい仕事ができそうだから」、「買い物や娯楽施設の利便性が高いから」の順となっている。
東京圏以外に住んでいる女性では、「買い物や娯楽施設の利便性が高いから」を挙げる割合が22.0%と最も高く、次いで、「親や兄弟姉妹の居住地と近いから」、「公共交通機関などの利便性が高いから」の順となっている。一方、東京圏以外に住んでいる男性では、「ゆとりのある暮らしができそうだから(時間の使い方、住居の広さなど)」を挙げる割合が19.5%と最も高く、次いで、「やりたい仕事ができそうだから」、「公共交通機関などの利便性が高いから」の順となっている。
東京圏に住んでいる女性は、男性に比べて、「買い物や娯楽施設の利便性が高いから」、「公共交通機関などの利便性が高いから」、「親や兄弟姉妹の居住地と近いから」、「子育て環境が充実していそうだから」、「医療・福祉サービス機能が充実していそうだから」が高くなっている。一方、男性は、女性に比べて、「満足な収入が得られそうだから」、「やりたい仕事ができそうだから」、「その地域に憧れがあるから」等が高くなっている。
東京圏以外に住んでいる女性は、男性に比べて、「親や兄弟姉妹の居住地と近いから」、「買い物や娯楽施設の利便性が高いから」、「子育て環境が充実していそうだから」、「公共交通機関などの利便性が高いから」、「医療・福祉サービス機能が充実していそうだから」、「教育・文化サービス機能が充実していそうだから」が高くなっている。一方、男性は、女性に比べて、「満足な収入が得られそうだから」、「やりたい仕事ができそうだから」が高くなっている(特-47図)。
(将来、出身地域に住みたい理由)
将来、出身地域に住みたい理由についてみると、女性では、「親や兄弟姉妹の居住地と近いから」を挙げる割合が46.9%と最も高く、次いで、「ゆとりのある暮らしができそうだから(時間の使い方、住居の広さなど)」、「買い物や娯楽施設の利便性が高いから」、「自然環境が豊かだから」の順となっている。一方、男性では、「ゆとりのある暮らしができそうだから(時間の使い方、住居の広さなど)」が28.6%と最も高く、次いで、「親や兄弟姉妹の居住地と近いから」、「公共交通機関などの利便性が高いから」、「自然環境が豊かだから」の順となっている。
女性は、男性に比べて、「親や兄弟姉妹の居住地と近いから」、「買い物や娯楽施設の利便性が高いから」、「子育て環境が充実していそうだから」が高くなっている。一方、男性は、女性に比べて、「やりたい仕事ができそうだから」、「性別や年齢にかかわらず活躍できそうだから」、「その地域に憧れがあるから」が高くなっている(特-48図)。
(将来、住んだことのない地域に住みたい理由)
将来、過去に住んだことのない地域に住みたい理由についてみると、都会に住みたい者では、男女ともに「公共交通機関などの利便性が高いから」(女性52.5%、男性49.5%)が最も高く、次いで、「買い物や娯楽施設の利便性が高いから」、「やりたい仕事ができそうだから」の順となっている。
地方に住みたい者では、男女ともに「ゆとりのある暮らしができそうだから(時間の使い方、住居の広さなど)」(女性37.2%、男性35.7%)が最も高く、次いで、「自然環境が豊かだから」が高くなっている。
都会に住みたい者では、女性は、男性に比べて、「買い物や娯楽施設の利便性が高いから」が高くなっている。一方、男性は、女性に比べて、「ゆとりのある暮らしができそうだから(時間の使い方、住居の広さなど)」が高くなっている。
地方に住みたい者では、女性は、男性に比べて、「新しい出会い・つながり・交友関係の広がりがありそうだから」、「子育て環境が充実していそうだから」、「医療・福祉サービス機能が充実していそうだから」が高くなっている(特-49図)。
特-49図 将来、過去に住んだことのない地域に住みたい理由(男女別)![]()
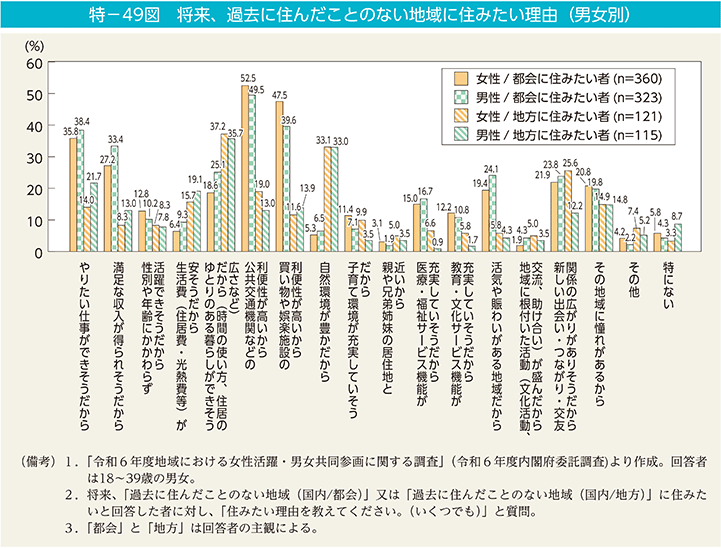
(現住地域以外に住むに当たって不安に思うこと)
将来、現在住んでいる地域以外に住むに当たって不安に思うことについてみると、将来、出身地域に住みたい女性では、「収入や生活費などの経済面での不安」が37.5%と最も高く、次いで、「希望する内容(業種や職種)の仕事に就けるか・続けられるか」、「買い物や公共交通機関などの利便性への不安」の順となっている。一方、男性では、「希望する内容(業種や職種)の仕事に就けるか・続けられるか」が37.2%と最も高く、次いで、「収入や生活費などの経済面での不安」、「働き方の柔軟性がある仕事に就けるか・続けられるか」の順となっている。
女性は、男性に比べて、「収入や生活費などの経済面での不安」、「親や親しい友人達と離れることへの不安」、「子育て環境・教育環境への不安」、「買い物や公共交通機関などの利便性への不安」、「仕事と子育てを両立できるか(育児休業の活用を含む)」が高くなっている。
将来、過去に住んだことのない地域に住みたい者についてみると、都会に住みたい者、地方に住みたい者のいずれも、男女ともに「収入や生活費などの経済面での不安」が最も高く、次いで、「希望する内容(業種や職種)の仕事に就けるか・続けられるか」が高くなっている。
都会に住みたい者と地方に住みたい者を比較すると、女性は、地方に住みたい者の方が、「人間関係や地域コミュニティへの不安」、「医療・福祉サービスへの不安」が高くなっている。一方、男性は、都会に住みたい者の方が、「希望する内容(業種や職種)の仕事に就けるか・続けられるか」が高くなっている(特-50図)。