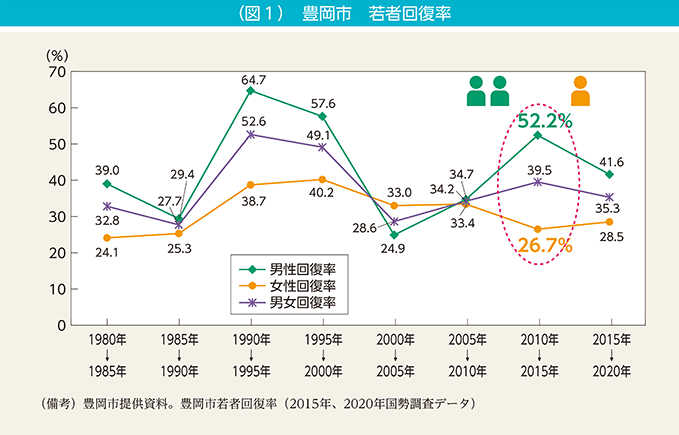本編 > コラム4 女性にも選ばれる地域づくりに向けた取組の事例![]()
コラム4
女性にも選ばれる地域づくりに向けた取組の事例
女性の「回復」を目指した先進的な取組 ─兵庫県豊岡市の事例
地域における女性の活躍を推進し、地域を女性にとって魅力あるものにしていくことは、地方創生などの観点からも重要な課題である。各地方公共団体においては、近年、DXの進展を踏まえ、国からの各種の支援も受けつつ、多様な取組が積極的に進められているところである。それらの中から、代表的な事例を3つ紹介する。
最初に、早い時期から女性の転出超過に対する取組を開始した兵庫県豊岡市の事例である。
〇 主な経緯・概要
豊岡市は、平成27(2015)年国勢調査結果に基づく若者回復率(10代の転出超過数に対して20代の転入超過数の占める割合。豊岡市が独自に定義した指標。)が、女性で26.7%であり、進学や就職で転出した若者のうち戻ってくる(入ってくる)割合が男性(52.2%)の半分しかないという事実に大きな危機感を持った(図1)。
同市では、家庭・職場・地域に根深く残るジェンダーギャップが、女性が能力を発揮する機会を奪い、魅力を失わせ、地域社会や地域経済に大きな損失をもたらしているのではないかとの仮説を立て、平成30(2018)年度からその解消を市の主要施策に位置付けて取組を開始した。
同市は、平成31(2019)年1月に市内事業所向けの「豊岡市ワークイノベーション戦略」を策定し、まず職場を対象とする取組を始めた。次いで、専門家や有識者らを招き、多様な立場の市民の参加を得て協議や検討を重ねてきた。令和元(2019)年12月の「『豊岡市ジェンダーギャップ解消戦略(仮)』策定に向けた提言」を受け、令和3(2021)年3月に「豊岡市ジェンダーギャップ解消戦略」を策定し、まち全体を対象とする取組を進めている。主な内容は以下のとおりである。
〇「豊岡市ワークイノベーション推進会議」の設立 ─トップのコミットメントを通じた改革
危機感を共有した経営者有志により、平成30(2018)年10月、豊岡市ワークイノベーション推進会議が、市内の16事業所(市役所を含む。)により設立された。この組織は、女性も男性も働きやすく、働きがいのある職場へと変革を進め、人手不足を解消し、多様な人材の活躍による生産性向上などを目指しており、最新の動向などを学ぶ講演会や研修会の開催、他社の取組紹介、事例共有、会員事業所の職場見学会、意見交換会などを行っている。
同会議の代表(令和6(2024)年度から共同代表制に変更)は、豊岡商工会議所会頭が務めており、代表自身の声かけにより、取組に賛同する事業所が増え、令和7(2025)年2月末現在、122事業所の参加を得ている。
〇「あんしんカンパニー」の表彰など ─従業員の視点を踏まえた推進
「豊岡市ワークイノベーション戦略」に基づき、市内事業所の経営者、管理職、人事担当者、女性従業員などの対象ごとに無意識の偏見や思い込みに気づくワークショップやキャリア形成支援、スキルアップ・リーダーシップ研修などを実施しており、そのKPIとして「女性従業員の3分の2以上が『働きやすくて働きがいがある』と評価している事業所の数」を設定し、10年間で50社を目指している。
この指標は、全従業員に対する意識調査を基に算出されており、この調査の結果、女性従業員・男性従業員双方の3分の2以上、かつ、全従業員の3分の2以上が働きやすく、働きがいのある職場であると評価している事業所を「とりくみカンパニー」として認定している。さらに、従業員の総純労働時間が適正か、育児休業等の取組実績があるかなどその他の項目を審査し、一定の基準を満たした事業所を「あんしんカンパニー」として表彰し、働きやすく、働きがいのある職場づくりへの取組を宣言した企業を「せんげんカンパニー」として登録、公表するなどしている。
〇 各種研修・ワークショップの開催など ─地域等における取組
豊岡市では、「豊岡市ジェンダーギャップ解消戦略」に沿って、地域、家庭、学校などの分野における取組も進めている。
この中で、地域については、おおむね小学校区単位にある地域コミュニティ組織29地区の会長・役員・地域マネージャーや行政区(自治会)359区の区長等役員、教員、保育士・保育教諭などを対象に、専門家による研修・ワークショップを実施し、まずは無意識の偏見や思い込み、固定観念に気付くことから、意識・行動変革を促している。

(豊岡市区長連合会における研修会の様子)
令和6(2024)年度の取組では、地域コミュニティ組織で、女性のよるカフェ(夜×寄る)を開催し、ワークショップや意見交換を行い、ジェンダーギャップに関する理解を深め、明日から取り組みたいことなどについて意見交換を行った。