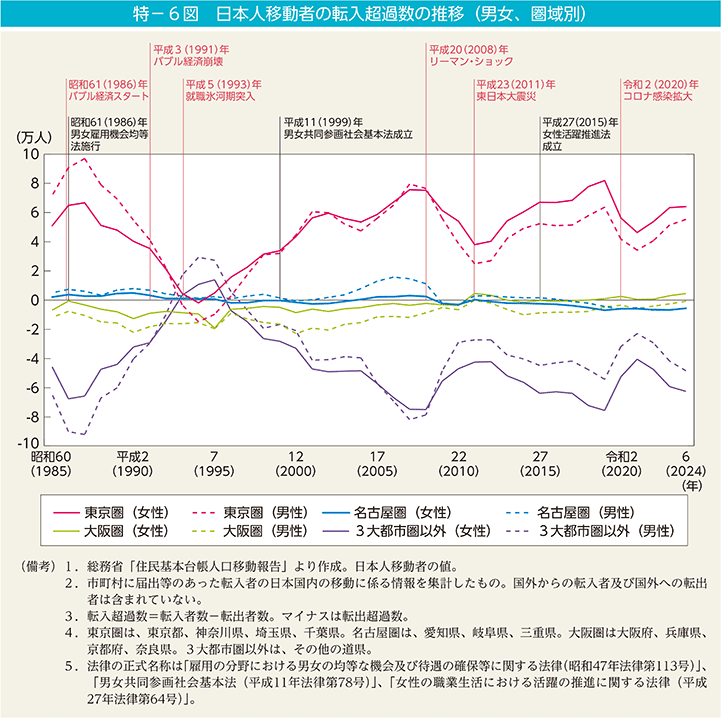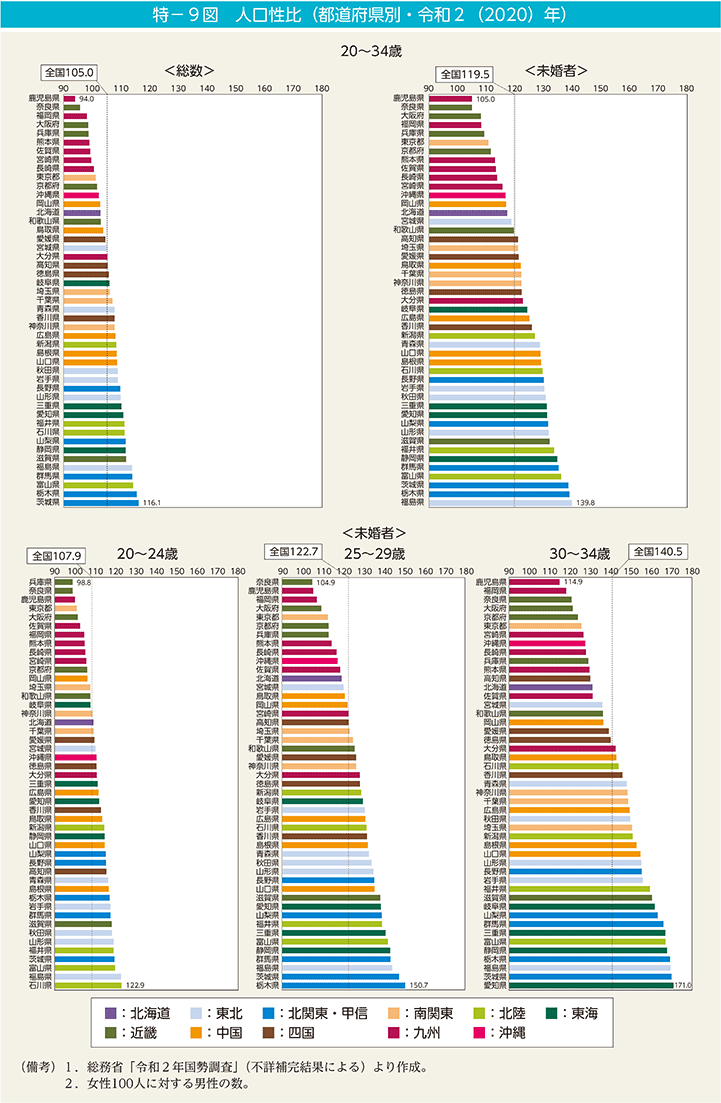本編 > 1 > 特集 > 第1節 人の流れと地域における現状と課題
第1節 人の流れと地域における現状と課題
本節では、政府統計等を用いて、地域における人口構造及び人口移動の状況を、男女、年代、地域別に整理した上で、地域によって異なる教育環境、就業・雇用環境及び生活環境等について概観する。
1.人口構造と人口移動の状況
日本の人口は、減少局面を迎えている。平成20(2008)年に1億2,808万4千人でピークを迎えた総人口は、令和6(2024)年時点で1億2,380万2千人まで減少しており、令和32(2050)年には、1億468万6千人まで減少すると予測されている。
生産年齢人口(15~64歳の人口)については、平成7(1995)年の8,726万人をピークに減少が始まっており、令和6(2024)年時点で7,372万8千人となっている。令和32(2050)年には、5,540万2千人まで減少すると予測されている4。
本項では、各地域の人口構造、人口移動等の状況について確認していく。
4 総務省「人口推計」(各年10月1日現在の人口)及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)出生中位(死亡中位)推計」。
(1)人口減少と都市への集中
(人口増減の状況)
令和5(2023)年10月から令和6(2024)年9月の人口増減の状況を、都道府県別にみると、男女ともに人口が増加したのは東京都のみとなっている。また、埼玉県と大阪府では女性のみがわずかに増加している。
人口が減少している道府県についてみると、男女ともに、秋田県、青森県、岩手県、高知県などで減少率が高くなっており、少子高齢化の影響も大きいとみられる。
男性と比べ、女性の方が人口減少率が高い県は、長崎県、香川県、愛媛県、山口県、富山県などとなっている。
一方、大阪府、千葉県、奈良県などでは、男性の方が人口減少率が高くなっている(特-1図)。
特-1図 人口増減率(男女、都道府県別・令和6(2024)年)![]()
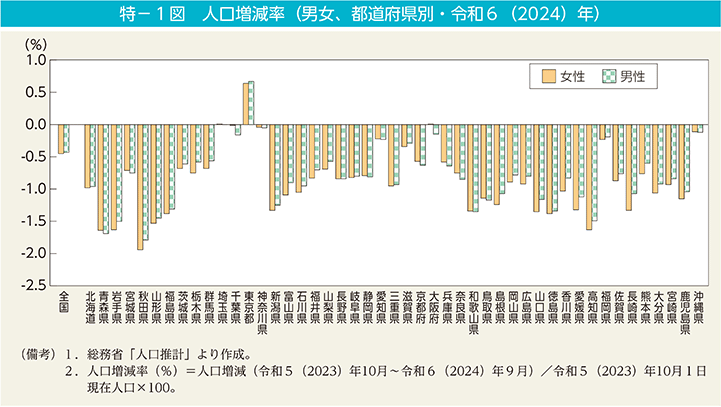
令和5(2023)年10月から令和6(2024)年9月の自然増減(出生児数-死亡者数)の状況を都道府県別にみると、全ての都道府県で、死亡者数が出生児数を上回る自然減少となっている。なお、男女ともに秋田県で自然減少率が最も高くなっている。
同期間の社会増減(転入者数及び入国者数-転出者数及び出国者数5)の状況をみると、都市を中心に、女性は23都道府県、男性は29都道府県で社会増加(転入・入国超過)、それ以外の県では、社会減少(転出・出国超過)となっている。
特に女性は、都市では社会増加、地方では社会減少という傾向が顕著に現れており、地方においては、自然減少に加え、社会減少によって、人口の減少が更に深刻化している(特-2図)。
特-2図 人口増減率・自然増減率・社会増減率(男女、都道府県別・令和6(2024)年)![]()
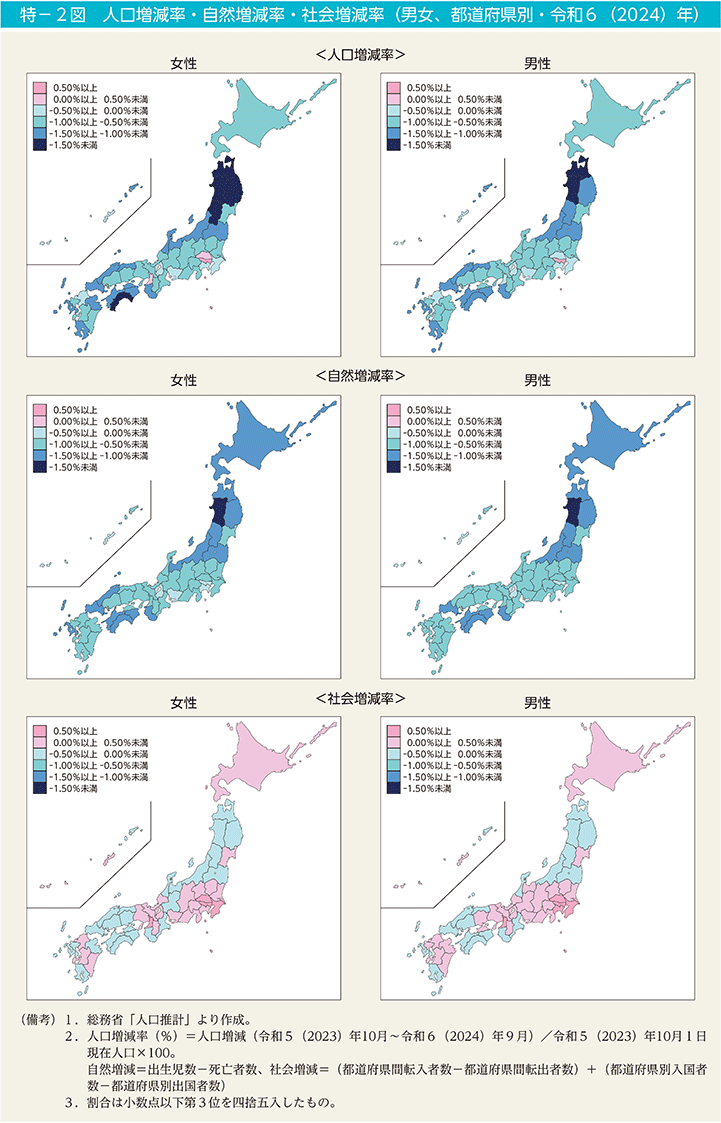
5 本節では、都道府県の区域内に、他の都道府県から住所を移した者の数を「転入者数」、都道府県の境界を越えて他の都道府県へ住所を移した者の数を「転出者数」としている。
(将来の人口)
将来の人口についてみると、令和2(2020)年を100とした令和32(2050)年の3大都市圏の人口の指数は、男女ともに90程度、3大都市圏以外の人口は、男女ともに75程度にまで減少すると推計されている。
年齢3区分別にみると、0~14歳人口は、男女ともに3大都市圏では76程度、3大都市圏以外では62程度、15~64歳人口は、3大都市圏では、男女ともに80程度、3大都市圏以外では、女性は64.8、男性は67.8にまで減少すると推計されている。65歳以上人口は、3大都市圏では、女性は116.7、男性は119.1と増加が予測されている一方、3大都市圏以外では女性96.4、男性101.5になると推計されている(特-3図)。
特-3図 将来推計人口(男女、年齢3区分別)(3大都市圏・3大都市圏以外)![]()
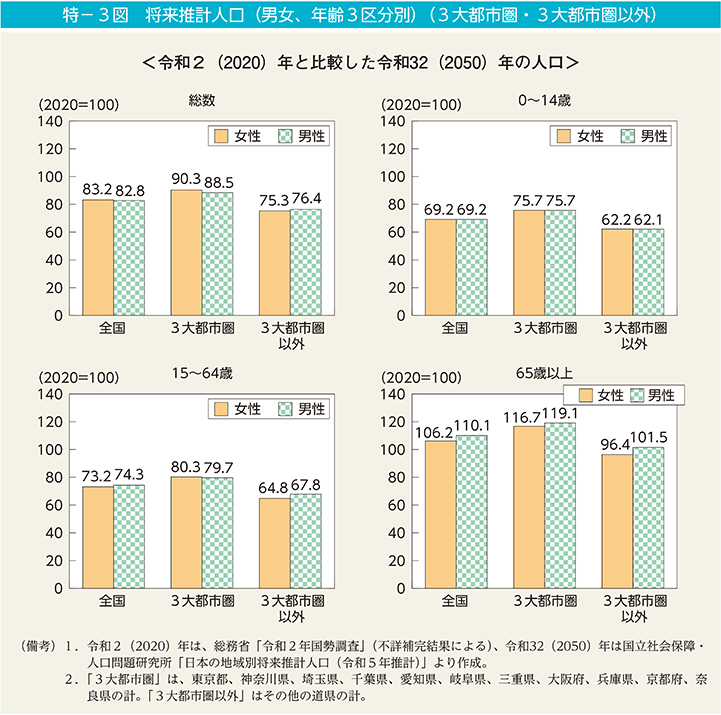
我が国の少子高齢化は、深刻なスピードで進展しており、特に地方でその影響は大きい。
他方、後述するように、都道府県間の人口移動は10代後半から20代が中心となっている。
社会減少となっている地域では、若い世代の人々の転出により出生数が減少することで、自然減少が更に加速し、地域によって人口減少の速度に差異が生じるものと推測される。
地方の人口減少を緩和し、地方の活力を維持するために、女性や若者が都市へ転出する理由や背景を明らかにする必要がある。
(2)人口移動の状況
(転入(転出)超過の状況)
令和6(2024)年の都道府県の転入超過数(マイナスは転出超過数)を男女別にみると、女性は、東京都で4.2万人と最も多く、次いで、神奈川県、大阪府、埼玉県、千葉県、福岡県、滋賀県の順となっており、これらの7都府県のみが転入超過、他の40道府県は転出超過となっている。
男性の転入超過数は、東京都で3.7万人と最も多く、次いで、神奈川県、埼玉県、大阪府、福岡県、千葉県、山梨県、栃木県の順となっており、これらの8都府県のみが転入超過、他の39道府県は転出超過となっている。
転入超過数の男女差(女性-男性)をみると、千葉県、東京都、大阪府などでは女性の方が転入超過数が多く、神奈川県及び埼玉県では男性の方が多くなっている。一方、北海道や栃木県などでは女性の方が転出超過数が多く、愛知県や京都府では男性の方が多くなっている。
これらのことから、東京圏などの都市に人口が移動しており、女性の方が、よりその傾向が強いことがわかる(特-4図)。
特-4図 転入超過数(男女、都道府県別・令和6(2024)年)![]()
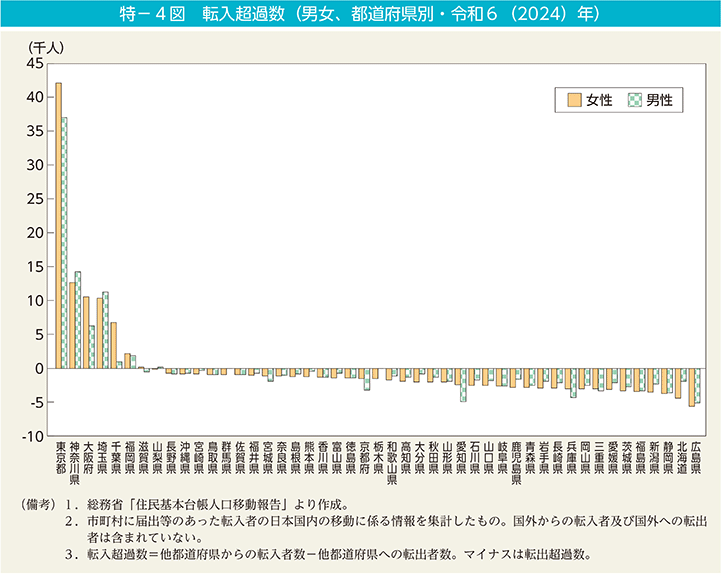
(人口移動のタイミング)
都道府県間移動率(都道府県を越えて移動した者の都道府県別人口に占める割合)をみると、男女とも22歳をピークに、18歳から20代で高くなっており、その後、年齢が上がるにつれて、徐々に低下している。大学等への進学、就職、結婚や子育てを機に転居をしている者が多いものとみられる(特-25図)。
最も移動率が高い22歳については、女性は14.20%、男性は15.22%となっている。
次に移動率が高い24歳については、女性に比べ、男性の方が2.70%ポイント高くなっている。24歳の移動率の高さについては様々な理由が想定されるが、男女差については、一因として、男性の方が大学院(修士課程)修了後の就職による転居が多くなっている6ことが考えられる。
23歳以降の移動率については、おおむね女性よりも男性の方が高くなっている。男性は、就職後も転勤や転職等で移動しているとみられるのに対し、女性は、男性に比べるとその後はあまり移動しない傾向がある(特-5図)。
特-5図 都道府県間移動率(男女、年齢各歳別・令和6(2024)年)![]()
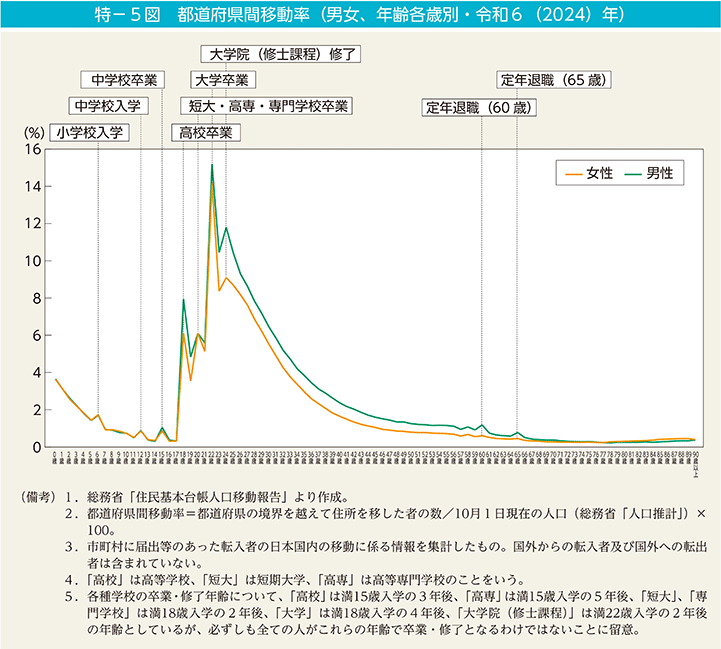
6 24歳人口に占める当該年齢での修士課程修了者の割合は、女性1.6%、男性3.9%となっている(文部科学省「学校基本統計(令和6年度)」及び総務省「人口推計」(令和6(2024)年10月1日現在)から、内閣府男女共同参画局にて算出。算出方法は、令和5(2023)年度間に修士課程を修了した者のうち24歳の者(年齢は令和6(2024)年5月1日時点)/令和6(2024)年10月1日時点の24歳人口×100。)。
(転入(転出)超過数の推移)
日本人の3大都市圏への転入超過数(マイナスは転出超過数)の推移をみると、東京圏では1990年代後半から男女ともに転入超過が続いている。名古屋圏では、近年は、男女ともに転出超過が続いている。大阪圏では、男性は転出超過が続いているが、近年、女性は転入超過へ転じている。
また、東京圏は、平成21(2009)年以降、女性の転入超過数が男性の転入超過数を上回って推移している。
なお、東京圏の転入超過数については、男女ともに、平成20(2008)年のリーマン・ショック以降及び令和2(2020)年の新型コロナウイルス感染症(以下「コロナ」という。)感染拡大以降は、一時的に減少傾向にあったが、それぞれ平成24(2012)年及び令和4(2022)年以降は、再び増加に転じている。
東京圏及び3大都市圏以外の転入超過数の推移をみると、男女ともに、転入超過数ゼロを境として対称的な形となっており、極めて強い負の相関(女性-0.99、男性-0.98)がみられる。
名古屋圏及び大阪圏の転入超過数の増減にかかわらず、東京圏の転入超過数が増減すると、3大都市圏以外の転入超過数は反対の動きをとっている(特-6図)。
(若い世代の転出入の状況)
前述のとおり、都道府県間の移動率は、男女ともに、22歳をピークに18歳から20代にかけて高くなっている(特-5図再掲)。
また、東京圏は転入超過が続いている(特-6図再掲)が、転入超過数を年代別にみると、10代後半から20代の若者が大宗を占めている7。
15~24歳の東京圏の転入者数及び転出者数の状況をみると、男女ともに転入者数に比べて、転出者数が少ないため、転入超過となっている。
転入者数及び転出者数について、男女別にみると、女性に比べて男性の方が東京圏への転入者数は多いものの、東京圏からの転出者数も男性の方が多いため、転入者数から転出者数を引いた転入超過数は、女性の方が多くなっている。
また、東京圏への転入者数を、東京圏からの転出者数で割った比率をみると、女性は2.9倍、男性は2.2倍と女性の方が高くなっている。
若者の東京圏への転入は男性の方がやや多いものの、女性の方が東京圏に留まる傾向が強いと考えられる(特-7図)。
特-7図 日本人移動者の東京圏の転出入者数の推移(男女別・15~24歳)![]()
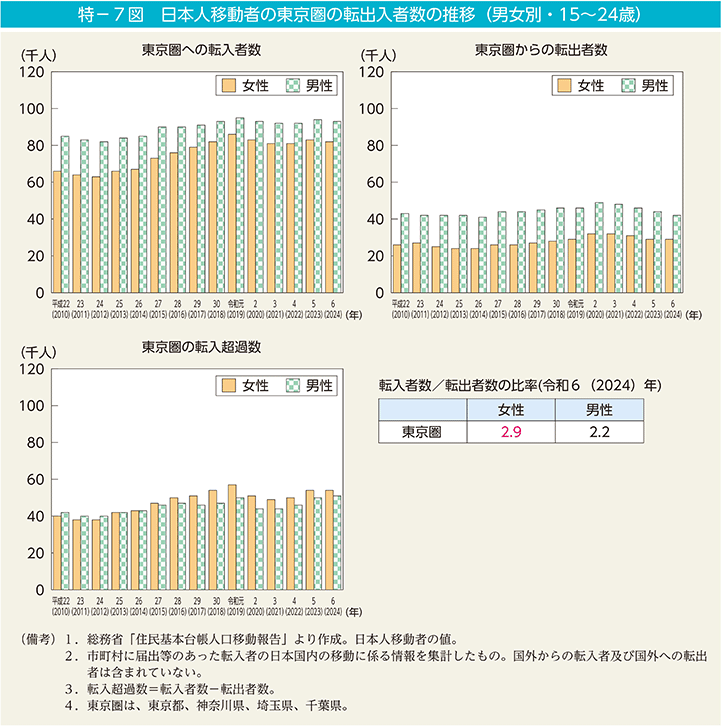
7 総務省「住民基本台帳人口移動報告」
(転入(転出)超過と雇用環境の関係)
東京圏の転入超過数を男女別にみると、20代女性は、令和6(2024)年を除き、20代男性を上回って推移している。
東京圏の有効求人倍率と、東京圏の転入超過数の推移の関係をみると、男女ともに正の相関がある。20代女性で最も強い相関(r=0.88)がみられ、次いで、30代男性(r=0.79)、20代男性(r=0.78)でも強い相関がみられる。
若い世代の東京圏への移動には、雇用環境が関係しており、特に20代女性はその関係が強いことが推測される。
一方、女性は30代及び40代では男性に比べて相関係数が低くなっており、結婚や子育てなど、雇用環境以外の要因と移動の関係が強くなっている可能性が示唆されている(特-8図、特-25図)。
特-8図 東京圏の転入超過数と有効求人倍率の推移(男女、年代別・20~50代)![]()
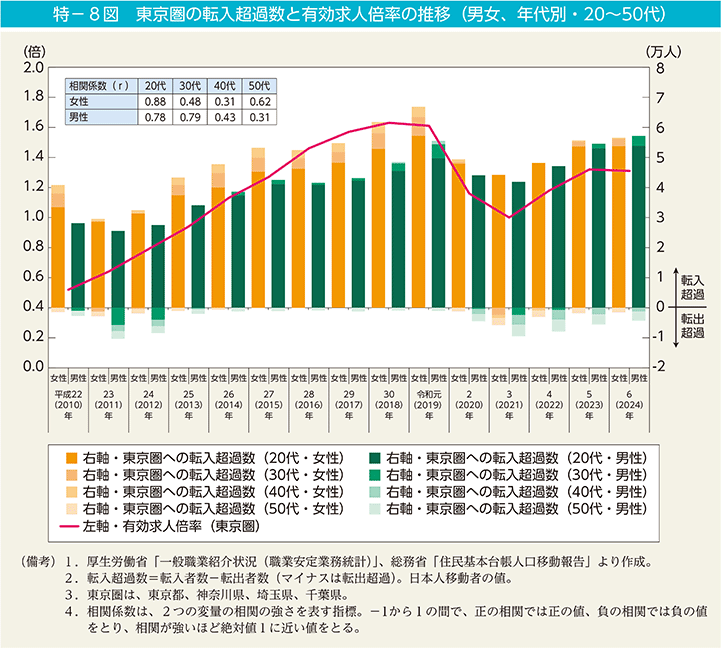
(3)地域別にみた人口構造
(男女別人口の不均衡)
我が国における出生時の人口性比(女性100人に対する男性の数)は105程度8となっている。15~19歳の人口性比を都道府県別にみても、最も人口性比が低い福岡県が103.0であるのに対し、最も高い島根県でも112.3であり9、人口の男女比に大きな偏りはみられない。
一方、20~34歳の人口性比を都道府県別にみると、最も低い鹿児島県が94.0であるのに対し、最も高い茨城県は116.1となっており、都道府県間で大きな差がある。
近畿、九州などの西日本及び東京都、北海道、宮城県などで人口性比が低い傾向となっている。
これらの状況から、進学・就職等を機に若者が地方から都市に転出する一方、その後の都市から地方への移動状況に男女で違いがあること等から、地域の男女別人口に不均衡が発生している可能性が考えられる。
全国の未婚者の人口性比について5歳階級別にみると、20~24歳では107.9、25~29歳では122.7、30~34歳では140.5となっており、年代が上がるにつれて、同じ年齢階級の男女の未婚者数に差が生じていることが確認できる。
20~34歳の未婚者の人口性比を都道府県別にみると、最も低い鹿児島県が105.0であるのに対し、最も高い福島県は139.8となっており、34.8ポイントの差が生じている。20~34歳全体の人口性比に比べて、未婚者では、更に都道府県間の差が大きくなっている。
未婚者の人口性比について年齢5歳階級別にみると、20~24歳では、最も人口性比が低い兵庫県(98.8)と最も高い石川県(122.9)の差が24.1ポイントであるのに対し、25~29歳では、最も低い奈良県(104.9)と最も高い栃木県(150.7)の差が45.8ポイント、30~34歳では、最も低い鹿児島県(114.9)と最も高い愛知県(171.0)の差が56.1ポイントとなっており、年代が上がるにつれて、都道府県間の差が拡大している(特-9図)。
8 厚生労働省「人口動態統計」
9 総務省「令和2年国勢調査」(不詳補完結果による)
2.地域における現状と課題
前述のとおり、都道府県間移動率は、男女ともに10代後半から20代にかけて高くなっており、大学等への進学、就職、結婚や子育てを機とした移動が多いものとみられる(特-5図再掲)。また、近年は15~24歳女性の東京圏への転入超過数が、15~24歳男性を上回って推移している(特-7図再掲)。
地域により女性や若者を取り巻く状況や環境が異なっていることが、女性や若者の都市への転出や若い女性が大学等を卒業した後も地方に戻らないことにつながっている可能性がある(特-40図)。
本項では、地域により異なる教育環境、就業・雇用環境、生活環境及び女性の社会への参画状況等を確認する。
(1)教育・学びの進展
(大学進学状況)
大学進学率を男女別にみると、男女ともに東京圏、大阪圏、山梨県及び茨城県で高く、地方で低い傾向にあり、都道府県によって大きな差が生じている。
女性は、東京都で77.6%と最も高く、次いで、京都府、山梨県の順で高くなっている。一方、宮崎県で38.7%と最も低く、次いで、福島県、大分県の順となっている。
男性は、山梨県で83.3%と最も高く、次いで、東京都、京都府の順となっている。一方、宮崎県で42.9%と最も低く、次いで、岩手県、秋田県の順となっている。
女性と男性の大学進学率の差(男性-女性)を都道府県別にみると、山梨県で15.6%ポイントと最も差が大きく、次いで、滋賀県、北海道、埼玉県の順で差が大きくなっている。
自県内大学進学率は、男女ともに都市で高く、地方で低い傾向にある。一方、県外大学進学率(大学進学率-自県内大学進学率)は、東京都の周辺地域や地方で高く、都市(東京都の周辺地域を除く。)で低い傾向にある。
他方、男女差についてみると、男性の方が大学進学率は高いものの、自県内大学進学率は、女性の方が高い傾向がみられる。この背景には、女性の方が男性より、自宅から通学可能な大学を希望する傾向があったり、進学先の決定に家族の意見の影響を強く受けやすいなど、様々な可能性が考えられる(特-10図、特-29図)。
特-10図 大学進学率(男女、都道府県別・令和6(2024)年度大学(学部)入学生)![]()
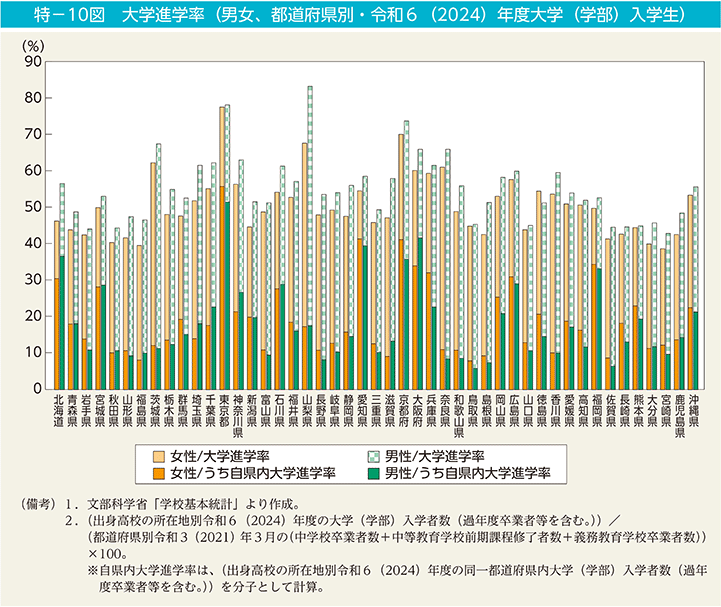
(大学入学定員数)
大学入学定員数を都道府県別にみると、地域によって差があり、都市で多い傾向にある。
特に、入学定員数に占める私立大学の入学定員数の割合をみると、東京都では93.1%、神奈川県では92.4%、埼玉県では92.1%、千葉県では90.3%と、東京圏ではいずれも9割を超えており、大阪府(87.6%)、京都府(86.6%)、愛知県(86.1%)、兵庫県(83.6%)、栃木県(80.5%)でも8割を超えている。
また、各都道府県の18歳人口に対する入学定員数の比率についてみると、東京都で164.5%と最も高く、次いで京都府で158.4%となっており、18歳人口を超える入学定員数となっている。
その他、大阪府(74.3%)、石川県(66.3%)、愛知県(60.8%)など、都市を中心に高い傾向となっている(特-11図)。
特-11図 大学入学定員数及び18歳人口に対する入学定員数比率(都道府県別・令和5(2023)年度)![]()
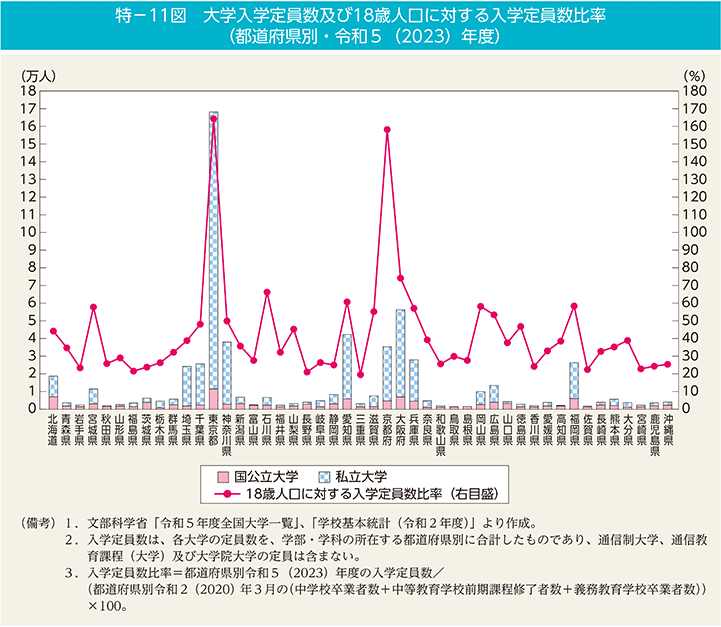
(大学進学に伴う移動状況)
大学進学時の各都道府県における流入者・流出者数10をみると、流入超過は9都府県、流出超過は38道県となっている。
男女計でみると、東京都には7.8万人、京都府には1.9万人、大阪府には1.1万人が流入している一方、茨城県からは1.0万人、静岡県からは0.9万人、埼玉県からは0.8万人が流出している。
大阪府及び神奈川県は男性の流入が多く、兵庫県は男性、千葉県は女性の流出が多くなっている(特-12図)。
特-12図 大学進学時の流入・流出者数(男女、都道府県別・令和6(2024)年度)![]()
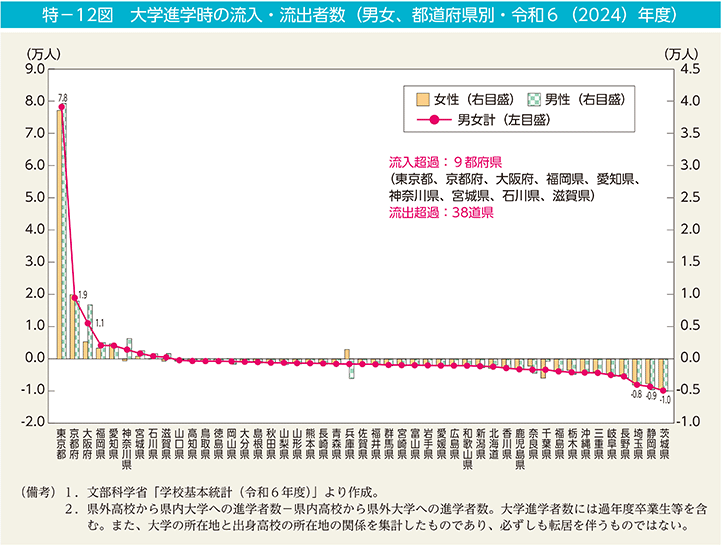
自県内大学進学率(特-10図再掲)と各都道府県の18歳人口に対する入学定員数の比率(特-11図再掲)の相関をみると、男女とも強い正の相関を示しているが、男性(r=0.78)と比べて、女性(r=0.82)の方がより強い相関を示している。
また、大学進学時の流入者・流出者数が流入超過となっている9都府県についてみると、いずれの都府県も18歳人口に対する入学定員数比率が50.0%以上となっている。
18歳人口に対する入学定員数比率が低い地域では、その地域の大学で学びたいと思っていても、自県内には進学先がないため、県外に進学している者が多くいる可能性がある。全ての地域の人が、自らの希望に応じて学ぶことができる環境の整備が重要である。
10 ここでいう「流入・流出」は、進学した大学の所在地と出身高校の所在地の関係を表したものであることに留意が必要。しがたって、必ずしも転居を伴うものではなく、また、居住している都道府県と出身高校・進学大学のある都道府県は異なる場合もある。
(2)就業状況と雇用環境
![]() 就業状況
就業状況
女性の就業者数は令和6(2024)年時点で3,082万人と、10年前に比べて345万人増加している11。
今後更なる人口減少が予測されている中で、近年増加している女性の労働参加は、地域の活力の維持・向上のために必要不可欠である。女性が活躍できる職場への変革や、全ての人が働きやすい環境づくりが必要である。
11 総務省「労働力調査(基本集計)」
(有業率)
女性の年齢階級別有業率を地域別にみると、北陸でいわゆる「M字カーブ」の解消が最も進んでおり、25~29歳と35~39歳の差は1.7%ポイントとなっている。
一方、南関東では、25~29歳と35~39歳の女性有業率の差が9.8%ポイントと、最も大きくなっている(特-13図)。
特-13図 有業率(男女、地域、年齢階級別・令和4(2022)年)![]()
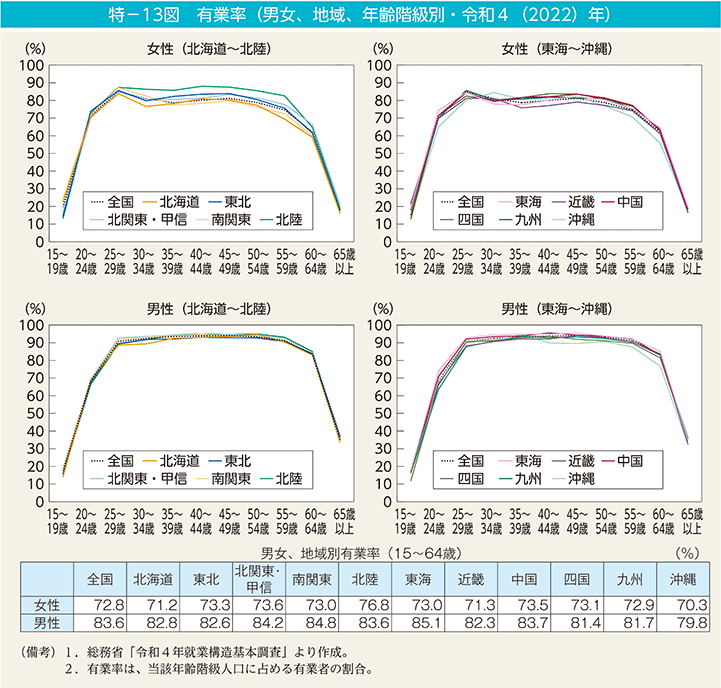
(正規雇用比率)
女性の正規雇用比率12を地域別にみると、沖縄を除くいずれの地域においても、25~29歳をピークに、年代が上がるとともに低下する、いわゆる「L字カーブ」があらわれている。
また、25~29歳の女性の正規雇用比率は、最も高い南関東で66.6%、最も低い沖縄で41.4%と、25.2%ポイントの地域差が生じている。
なお、北陸では55~59歳まで、東北及び四国では50~54歳まで女性の正規雇用比率が40%以上となっている(特-14図)。
特-14図 正規雇用比率(男女、地域、年齢階級別・令和4(2022)年)![]()
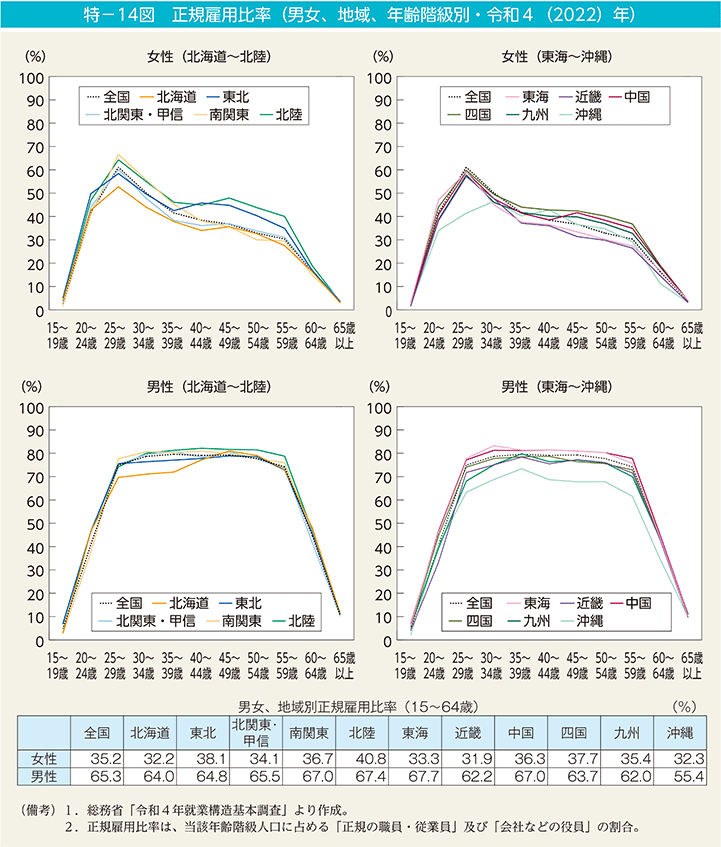
12 本特集では、特に注釈のない限り、当該年齢階級人口に占める「役員」と「正規の職員・従業員」の割合を「正規雇用比率」としている。
![]() 産業
産業
(有業者の産業及び雇用形態)
女性有業者数を産業別にみると、「医療、福祉」が最も多く、次いで、「卸売業、小売業」、「製造業」、「宿泊業、飲食サービス業」の順となっている。
女性有業者に占める非正規の職員・従業員の割合は47.7%となっているが、産業別にみると、女性有業者の多い「医療、福祉」では41.6%、「卸売業、小売業」では62.0%、「製造業」では43.2%、「宿泊業、飲食サービス業」では74.4%を、それぞれ非正規の職員・従業員が占めている。
女性有業者に占める役員及び正規の職員・従業員の割合を、有業者数50万人以上の産業別でみると、「情報通信業」で71.8%と最も高く、次いで、「金融業、保険業」(70.5%)、「建設業」(65.9%)の順で高くなっている。ただし、これらの産業に就いている女性は263万人(女性有業者の8.7%)と少ない。
男性有業者数を産業別にみると、「製造業」が最も多く、次いで、「卸売業、小売業」、「建設業」、「運輸業、郵便業」の順となっている。
男性有業者に占める非正規の職員・従業員の割合は、18.1%と女性に比べて低くなっているが、「宿泊業、飲食サービス業」では44.4%、「サービス業(他に分類されないもの)」では31.3%、「生活関連サービス業、娯楽業」では29.4%などと、他の産業に比べて高くなっている。
男女ともに有業者の多い「卸売業、小売業」について、役員又は正規の職員・従業員の割合をみると、男性は68.2%であるのに対し、女性は32.7%となっている。
「製造業」でも同様に、男性は役員又は正規の職員・従業員の割合が83.5%であるのに対し、女性は52.0%となっており、同じ産業であっても、男女で雇用形態に違いがある(特-15図)。
特-15図 有業者数及び割合(男女、産業、従業上の地位・雇用形態別・令和4(2022)年)![]()
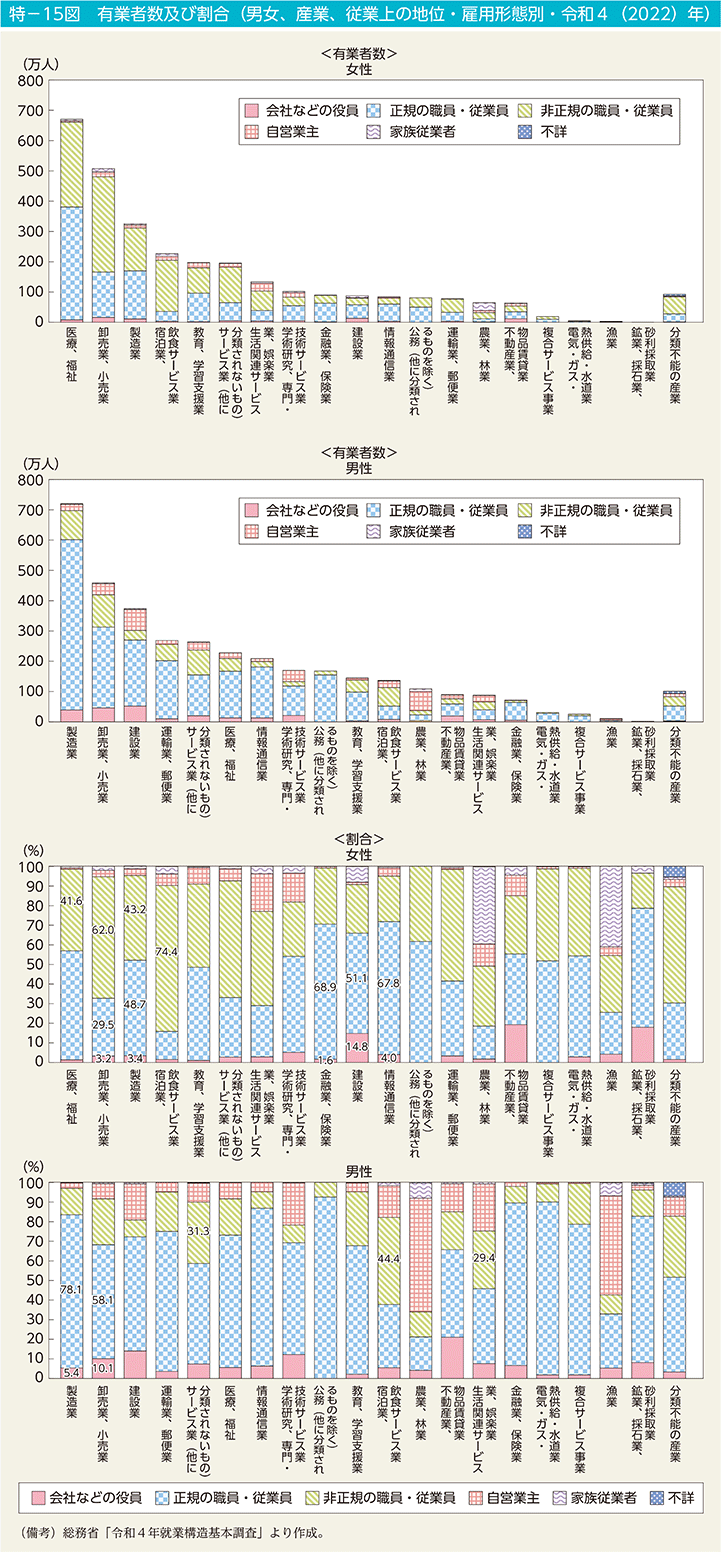
(「医療、福祉」、「製造業」の正規の職員・従業員の状況)
正規の職員・従業員の産業別割合をみると、女性では「医療、福祉」が30.0%と最も高くなっている。都道府県別にみると、長崎県で42.5%と最も高く、北海道並びに中国、四国及び九州の県で35%以上の県が多くなっている。一方、男性は、多くの県で1割以下となっている。
男性では、正規の職員・従業員のうち、「製造業」の割合が24.6%と最も高く、都道府県別にみると、一部例外はあるが、北関東・甲信、東海、北陸などで高くなっている。「製造業」については、女性も同様の傾向にあるが、男性と比べると割合は低くなっている(特-16図)。
特-16図 正規の職員・従業員に占める「医療、福祉」、「製造業」の割合(男女、都道府県別・令和4(2022)年)![]()
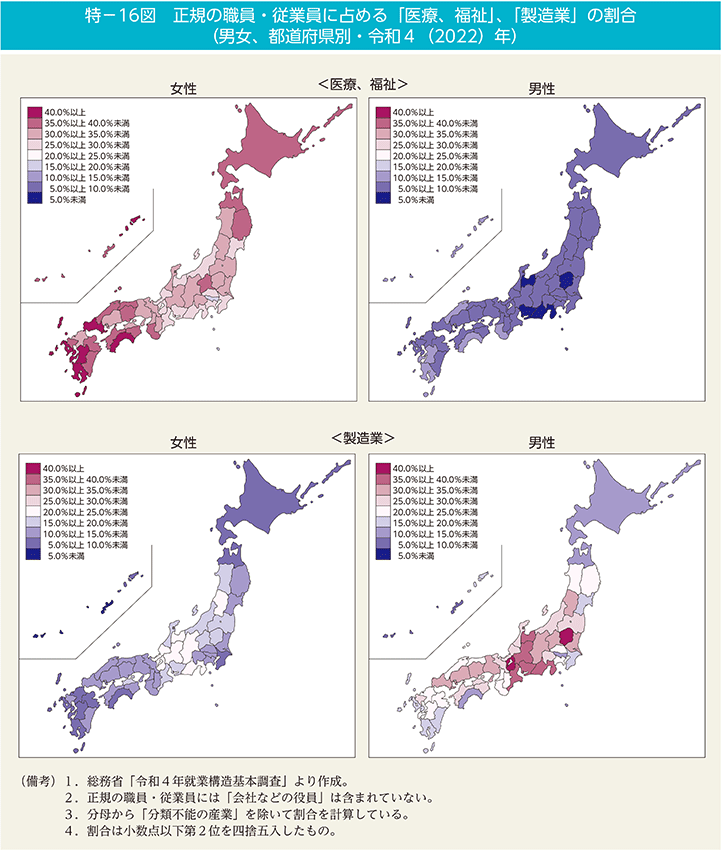
(3)生活・労働環境
![]() 賃金・物価
賃金・物価
(賃金状況)
一般労働者の所定内給与額をみると、全国平均では、女性27.5万円、男性36.3万円、男女間賃金格差(男性を100とした場合の女性の給与)は、75.8となっている。
所定内給与額を都道府県別にみると、男女ともに東京都(女性33.8万円、男性44.1万円)が最も高く、女性では青森県が22.4万円、男性では沖縄県が28.7万円と最も低くなっている。
所定内給与額は、男女ともに南関東、近畿などで高い傾向にある。
他方、男女間賃金格差は、静岡県で73.1(女性25.1万円、男性34.3万円)と最も大きく、沖縄県で83.4(女性23.9万円、男性28.7万円)と最も小さくなっている(特-17図)。
特-17図 所定内給与額(男女、都道府県別・令和6(2024)年)![]()
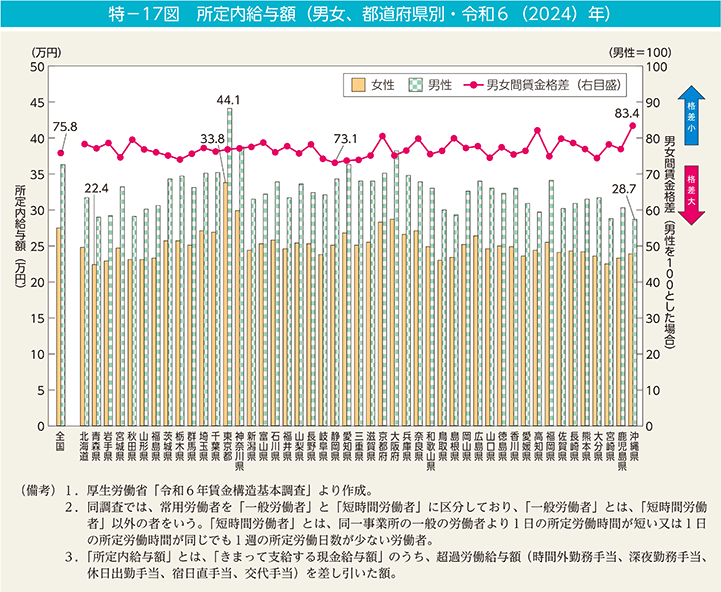
(物価の地域差)
消費者物価地域差指数(全国平均=100)13をみると、物価水準は東京都が104.5と最も高く、次いで神奈川県(103.1)などとなっている。
一方、物価水準は鹿児島県(95.9)で最も低く、次いで宮崎県(96.1)などとなっており、38府県で100.0未満となっている。
全国平均(100)との差(総合)に対する内訳として10大費目別寄与度についてみると、東京圏では「住居」、「教養娯楽」がプラスに寄与しており、特に東京都では「住居」の寄与度が大きくなっている。
他方、北海道、東北、中国では、「光熱・水道」、沖縄県では「食料」がそれぞれ大きくプラスに寄与している(特-18図)。
特-18図 消費者物価地域差指数(総合)及び全国との差に対する費目別寄与度(都道府県別・令和5(2023)年)![]()
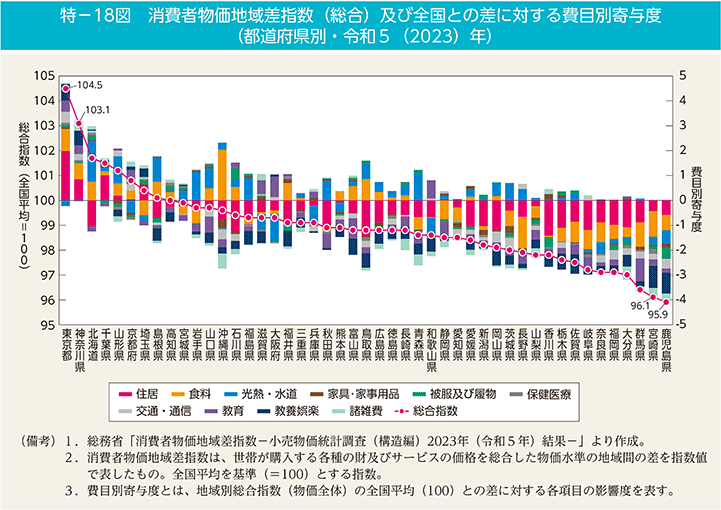
13 消費者物価地域差指数は、世帯が購入する各種の財及びサービスの価格を総合した物価水準の地域間の差を指数値で表したもの。全国平均を基準(=100)とする指数。
![]() 生活時間
生活時間
(仕事時間と家事時間)
6歳未満の子供のいる妻と夫の仕事関連時間及び家事関連時間についてみると、全ての都道府県で、家事関連時間は妻の方が210分以上、仕事関連時間は夫の方が180分以上長くなっている。
妻と夫の仕事関連時間の差が大きい都道府県ほど、妻と夫の家事関連時間の差も大きい傾向にある。
仕事関連時間と家事関連時間の合計について、妻と夫の差(妻-夫)をみると、山口県(124分)、富山県(107分)、石川県(100分)、福井県(99分)など、北陸などで差が大きい傾向にある。
一方、栃木県では40分、宮城県では33分、宮崎県では27分、夫の方が長くなっている(特-19図)。
特-19図 6歳未満の子供のいる妻と夫の仕事関連時間・家事関連時間(週全体)(都道府県別・令和3(2021)年)![]()
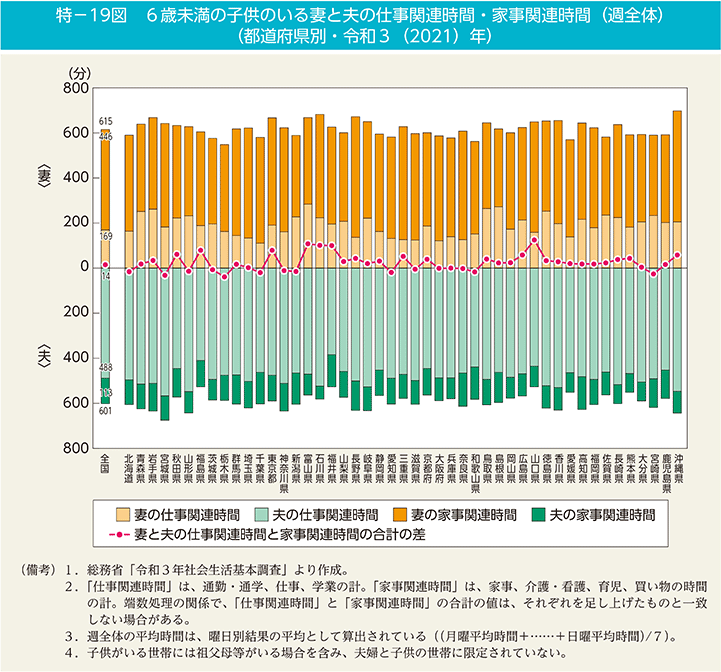
男性の家事・育児等への参画及び女性の社会での一層の活躍のためには、長時間労働の是正、テレワークなどを含む柔軟な働き方による仕事関連の負担軽減とともに、家事支援サービスの利用などによる家事関連の負担軽減が重要である。
(テレワークの実施状況)
有業者のうち、令和3(2021)年10月~令和4(2022)年9月に、テレワークを「実施した」者の割合をみると、女性は14.1%、男性は23.2%と、男性の方が高くなっている。
テレワーク実施率は都道府県によって差があり、女性は、東京都で34.0%と最も高く、次いで、神奈川県(21.4%)、千葉県(16.7%)、大阪府(15.2%)、埼玉県(15.1%)の順となっている。
男性は、東京都(45.4%)が最も高く、次いで、神奈川県(37.1%)、千葉県(30.1%)、埼玉県(27.2%)、大阪府(24.2%)の順となっている。
男女ともに、都市で実施率が高くなっており、柔軟な働き方がしやすい環境であることがうかがえる(特-20図)。
特-20図 有業者に占めるテレワークを実施した者の割合(男女、都道府県別・令和4(2022)年)![]()
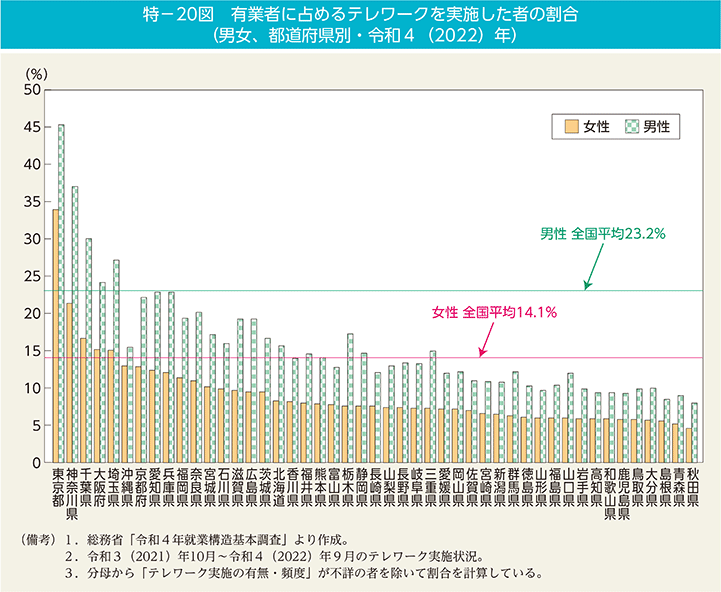
テレワークの導入状況は、企業規模や産業等によっても異なるため14、全ての者がテレワークの恩恵を受けているわけではないが、テレワークの実施は、主に男性の労働時間を減らし、家事・育児時間を増やす効果があることに加え、通勤時間を短縮した時間を余暇や睡眠時間に充てることで、心身の負担の軽減につながる可能性がある15。
14 従業者規模別、産業分類別等のテレワーク導入状況については、総務省「令和5年通信利用動向調査報告書(企業編)」を参照。
15 テレワークと生活時間については、「令和5年版男女共同参画白書 特集-新たな生活様式・働き方を全ての人の活躍につなげるために~職業観・家庭観が大きく変化する中、「令和モデル」の実現に向けて~」等を参照。
(4)各分野における女性参画の状況
![]() 政治分野
政治分野
(政治への参画状況)
令和6(2024)年12月31日時点で、都道府県知事における女性の割合は4.3%(47名中2名)、市区町村長における女性の割合は、3.7%(1,740名中64名)となっている16。
地方議会における女性議員の割合17は、都道府県議会、市議会、特別区議会及び町村議会のいずれにおいても、長期的に上昇している(第1分野1-4図)。
都道府県議会における女性議員の割合は、東京都が33.1%と最も高く、次いで、香川県(22.5%)、京都府(22.4%)、岡山県(21.8%)、鹿児島県(19.6%)の順となっている。
市区町村議会における女性議員の割合は、東京都が33.5%と最も高く、次いで埼玉県(26.3%)、大阪府(26.0%)、神奈川県(25.7%)、京都府(21.9%)の順となっており、3大都市圏で高くなっている(特-21図)。
特-21図 地方議会における女性議員の割合(都道府県別・令和6(2024)年)![]()
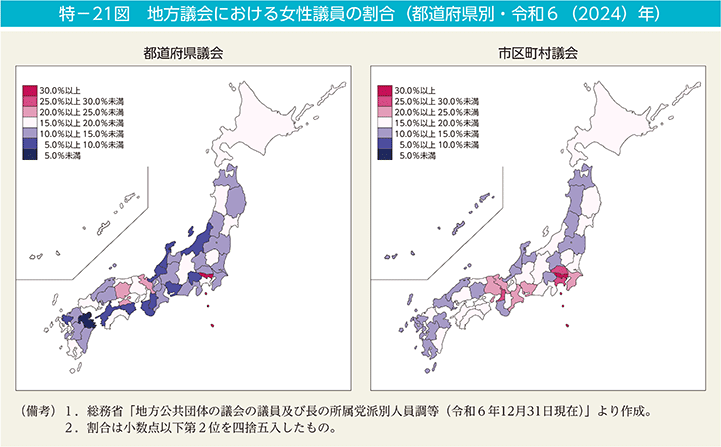
16 総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等(令和6年12月31日現在)」より。なお、市区町村長数については1名欠員あり。
17 第5次男女共同参画基本計画(令和2年12月25日閣議決定)において、統一地方選挙の候補者に占める女性の割合を、令和7(2025)年までに35%とすることが、目標として掲げられている。
※ 政府が政党等への要請、「見える化」の推進、実態の調査や好事例の横展開及び環境の整備等に取り組むとともに、政党を始め、国会、地方公共団体、地方六団体等の様々な関係主体と連携することにより、全体として達成することが期待される目標数値であり、各団体の自律的行動を制約するものではなく、また各団体が自ら達成を目指す目標ではない。
![]() 経済分野
経済分野
(管理職に占める女性の割合)
管理的職業従事者(会社役員、企業の課長相当職以上、管理的公務員等)に占める女性の割合18は、令和4(2022)年時点で15.3%となっている。
都道府県別にみると、徳島県(23.8%)が最も高く、次いで、鳥取県、高知県、佐賀県、青森県の順となっている。
地域別にみると、一部に例外はあるが、四国、中国、近畿や東北などで高く、南関東や北陸、沖縄などで低い傾向となっている(特-22図)。
特-22図 管理的職業従事者に占める女性の割合(都道府県別・令和4(2022)年)![]()
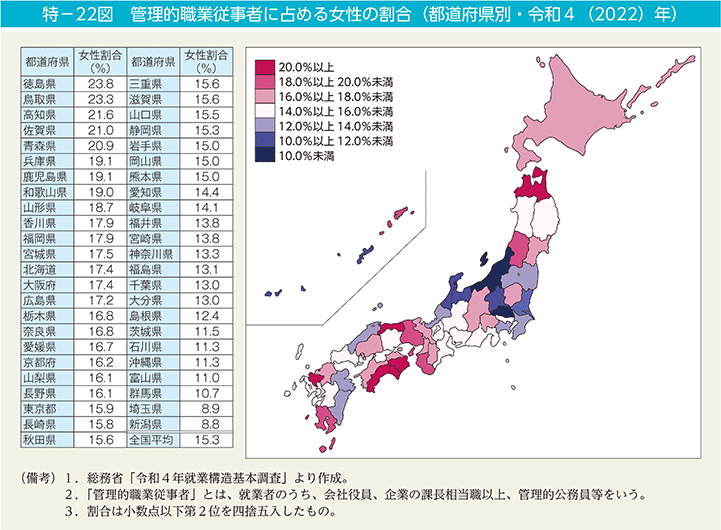
18 第5次男女共同参画基本計画において、各役職に占める女性の割合を、以下のとおりとすることが、成果目標として掲げられている(かっこ内は期限)。
東証プライム上場企業役員:19%(令和7(2025)年)
民間企業の部長相当職:12%(令和7(2025)年)、課長相当職:18%(令和7(2025)年)
国家公務員の指定職相当:8%(令和7(2025)年度末)、本省課室長相当職:10%(令和7(2025)年度末)
都道府県職員の本庁部局長・次長相当職:10%(令和7(2025)年度末)、本庁課長相当職:16%(令和7(2025)年度末)
市町村職員の本庁部局長・次長相当職:14%(令和7(2025)年度末)、本庁課長相当職:22%(令和7(2025)年度末)
(起業者に占める女性の割合)
起業者(今の事業を自ら起した者)に占める女性の割合19は、令和4(2022)年時点で22.3%となっている。
都道府県別にみると、沖縄県(25.8%)が最も高く、次いで、北海道、大阪府、三重県、高知県の順となっている。
地域別にみると、一部に例外はあるが、東京都、大阪府のほか、近畿、中国、四国、東北などで高く、北関東や北陸などで低い傾向となっている(特-23図)。
特-23図 起業者に占める女性の割合(都道府県別・令和4(2022)年)![]()
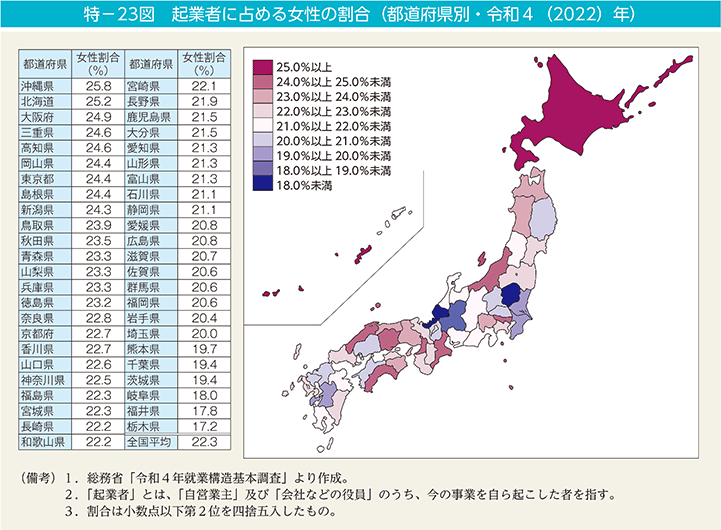
19 第5次男女共同参画基本計画において、起業家に占める女性の割合を、令和7(2025)年までに30%以上とすることが、成果目標として掲げられている。なお、本目標における起業家とは、過去1年間に職を変えた又は新たに職に就いた者で、現在は会社等の役員又は自営業主となっている者のうち、自分で事業を起こした者であり、特-23図で示されている起業者(現在は会社等の役員又は自営業主となっている者のうち、自分で事業を起こした者であり、職を変えた又は職に就いた時期は問わない)とは異なる点には注意が必要である。
![]() 地域分野
地域分野
(農協個人正組合員に占める女性の割合)
農協個人正組合員に占める女性の割合は、令和5(2023)年度時点で23.7%となっている。
都道府県別にみると、広島県(34.9%)が最も高く、次いで、山口県、和歌山県、京都府、兵庫県、高知県、神奈川県となっており、30%を超えている。
地域別にみると、一部例外はあるが、中国、四国、近畿、東海で高く、沖縄や東北などで低い傾向となっている(特-24図)。
特-24図 農協個人正組合員に占める女性の割合(都道府県別・令和5(2023)年度)![]()
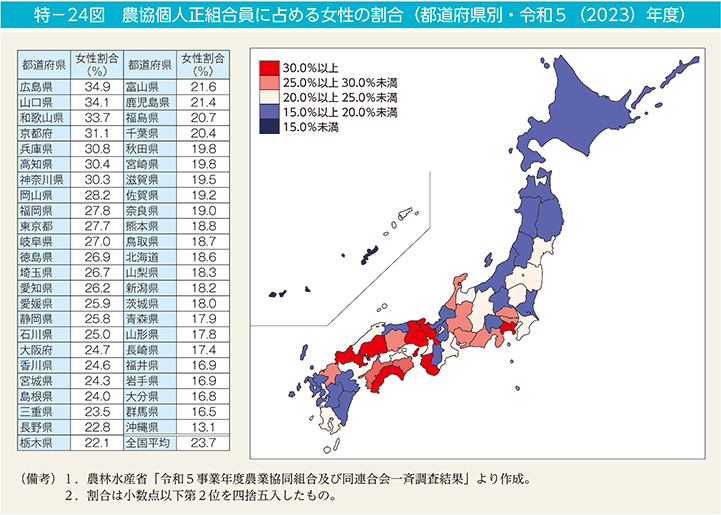
女性は、我が国の人口の51.3%20、有権者数の51.7%21を占めている。
政治、経済、社会などあらゆる分野において、政策・方針決定過程に男女が共に参画し、女性の活躍が進むことにより、様々な視点が確保され、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある持続可能な社会を生み出すとともに、あらゆる人が暮らしやすい社会の実現につながる。
企業や地域において活躍する女性人材の育成、企業の経営層・管理職、男女共同参画センターの職員を始めとする企業や地域における女性活躍・男女共同参画推進のリーダー・担い手の育成・専門性の向上など、「人材の育成」を軸とした取組が重要である。
20 総務省「人口推計」(令和6(2024)年10月1日現在)
21 総務省「令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調」
コラム1 農林水産業における女性の更なる活躍、就業に向けた施策・取組と活躍事例(![]() 施策・取組)
施策・取組)