本編 > コラム3 地域における「理工チャレンジ(リコチャレ)」の推進
コラム3
地域における「理工チャレンジ(リコチャレ)」の推進
我が国の女子学生が、理工系への進学を選択しない傾向が強いことが以前から課題となっている。このため、平成17(2005)年から、内閣府男女共同参画局が中心となって、女子中高生・女子生徒等が理工系分野に興味・関心を持ち、将来の自分をしっかりとイメージして進路選択(チャレンジ)することを応援するため、「理工チャレンジ(リコチャレ)」を推進しているところである。
そのうち、全国の各地域、中でも小規模自治体を対象に実施している取組を中心に紹介する。
● 女子の理工系進学に関する状況について
<諸外国と比べた日本の現状>
令和3(2021)年の経済協力開発機構(OECD)調査によると、大学など高等教育機関のいわゆる「STEM」(科学・技術・工学・数学)分野に入学した学生に占める女性の割合について、日本は「自然科学・数学・統計学」の分野で27%、「工学・製造・建築」で16%と、いずれも比較可能な36か国で最低となっている1。なお、令和3(2021)年時点における研究者に占める女性の割合(17.8%)も、OECD調査等によると他国と比べ群を抜いて低い2。
他方、同じくOECDの令和4(2022)年における「生徒の学習到達度調査」(PISA)によると、日本の女子学生の15歳時点における科学的リテラシー及び数学的リテラシーは、OECD諸国の男女の平均得点を大きく上回っており世界でトップクラスである3。
以上のことから、我が国の女性の理工系能力が十分活用されることなく、社会的・経済的な損失を招いているという指摘もなされている。
1 OECD “Education at a Glance 2021”
2 総務省「科学技術研究調査」(令和6(2024)年)
3 OECD “PISA 2022 Results”
<「理系的経験」の必要性を示す調査研究>
─「女子生徒等の理工系分野への進路選択における地域性についての調査研究」
内閣府はこの課題について継続的に調査分析を行っており、令和3(2021)年度においては、文部科学省「学校基本調査」の二次分析、高校生(4,594人)を対象とするモニター調査結果、その他各種統計データ等に基づいて、地域における実態の把握及び要因分析を行ったところである。
≪主な結果≫
女性の理工系分野への進路選択に影響を与える要因の一つとして、女性の理工学部志望者は、幼少期の科学館・博物館体験や大学や自治体のイベントへの参加経験等の理系的経験が多く、理工系分野に興味を持つきっかけとして、理系的経験が寄与している可能性がうかがえる。
他方で、理工系分野への女性の進学に関する地域性についての分析の結果、幼少期の科学館・博物館体験や、大学や自治体などが主催するイベントへの参加経験等の理系的経験は、人口が「5万人未満」の市町村で少なく(図1、2)、理工系に対する興味を深める機会が不足していることがうかがえる。また、保護者の学歴や家庭の暮らしの状況など、女性の4年制大学進学に影響を与える各種指標は、人口規模が小さいほど低い水準にある。
【幼少期の理系的な経験】
図1 人口規模別 「保護者に、科学館や博物館に連れていってもらうこと」があったか(女性):単数回答![]()
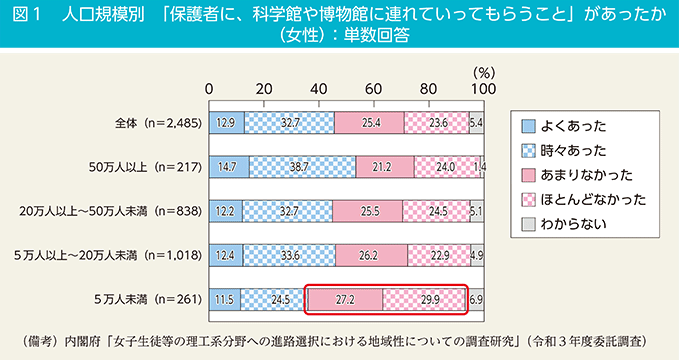
【大学や自治体などが主催するイベントへの参加経験】
図2 人口規模別 「大学や自治体などが主催する、理工系進学に関するイベント・シンポジウムに参加すること」があったか(女性):単数回答![]()
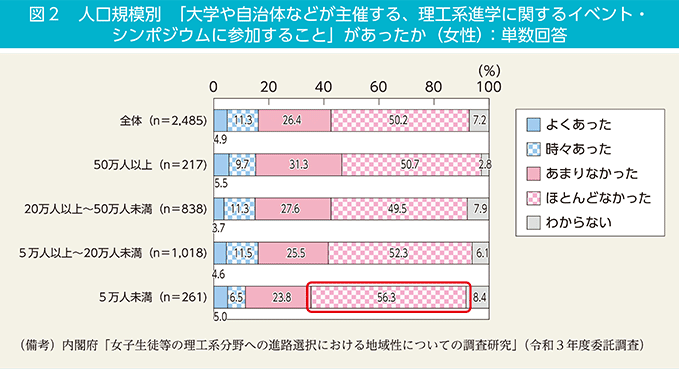
上記のことから、女子の理工系進学を促進する上で、人口「5万人未満」の地域は相対的に課題が大きく、今後重点的に取り組むべき地域と考えられるとともに、こうした地域において、理系的経験の機会を増やすことが重要であることが改めて明らかとなった。
● 地域における「リコチャレ」の更なる推進
「理工チャレンジ(リコチャレ)」においては、「夏のリコチャレ」、「STEM Girls Ambassadorsの派遣」など、大学、企業、学術団体等と連携しながら、全国各地において、理系的体験の機会を提供し、理工系分野で活躍する多様な女性の姿を示す活動を進めてきたところである。
以上の調査研究の結果も踏まえ、全国の各地域における女子生徒等の理工系分野への進路選択を更に支援するため、令和5(2023)年度から「若手理工系人材(ロールモデル)による出前授業」を新たに開始したところである。
<若手理工系人材(ロールモデル)による出前授業 ─人口5万人未満の市区町村を対象>
「若手理工系人材(ロールモデル)による出前授業」は、理系的体験の機会が相対的に少ないとされる人口5万人未満の市区町村を重点的に対策すべき地域と定め、それら地域における女子生徒の理系的体験の機会の創出と、地域におけるロールモデルの掘り起こしを目的として実施している。これまで、令和5(2023)年度に3か所、令和6(2024)年度に5か所、延べ8か所において実施し、延べ509名の参加を得ている。
令和6(2024)年度においては、人口5万人未満の市区町村から選定した全国5地域(栃木県那須町、長崎県雲仙市、宮城県東松島市、香川県小豆島町、岡山県新見市)において、小・中・高校女子生徒(男子生徒も可)・保護者・教員・地域住民等を対象に実施した。
派遣されたロールモデルは、当該地域の地元企業・大学・研究機関等で活躍する、理工系分野への従事期間が10年以内の若手の理工系人材等(1地域3名)である。ロールモデルの講演や専門分野に応じた実験等の体験(2~3時間程度)が行われた。
令和6(2024)年度の延べ参加者数は292名(うち、児童・生徒:174名、保護者・教員等:118名)であった。イベントを通じて理工系の魅力を感じた生徒等の割合は86%であった。



(令和6(2024)年度「若手理工系人材による出前授業」の様子)