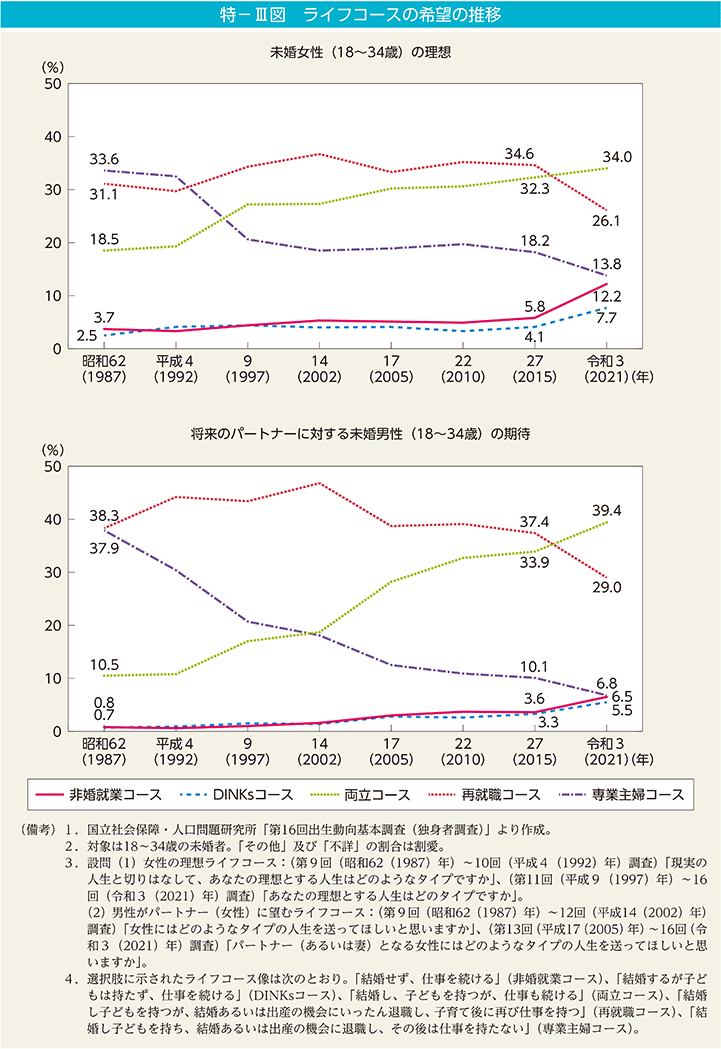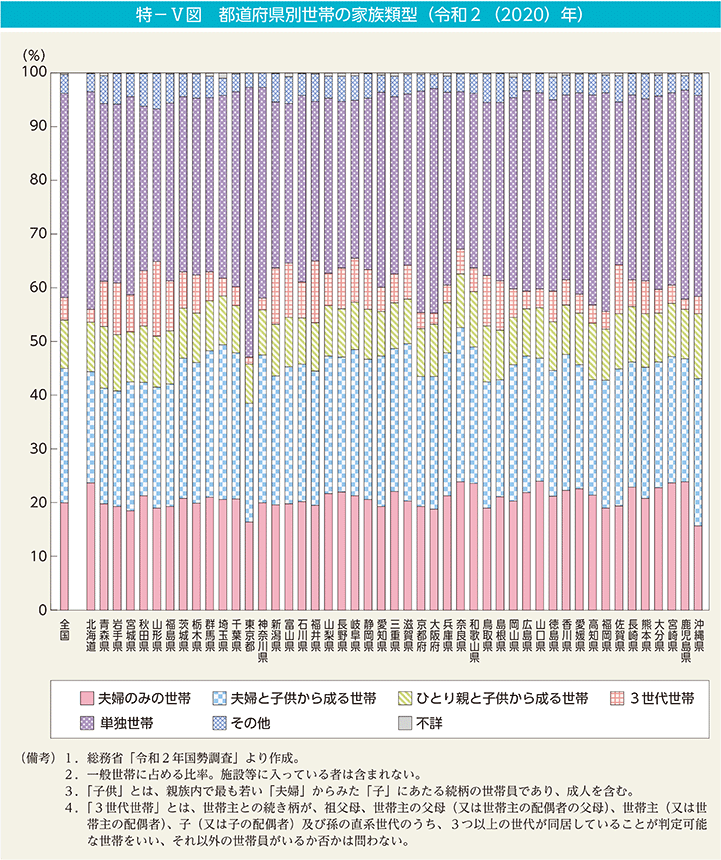本編 > 1 > 特集 男女共同参画の視点から見た魅力ある地域づくり
男女共同参画は、全ての人が生きがいを感じられる、多様性が尊重される社会を実現するとともに、我が国の経済社会の持続的な発展において不可欠な要素である。
急速に進行する少子高齢化や人口減少の中で、地域の活力の維持・向上のためにも、女性や若者の活躍がますます重要になっている。
令和6(2024)年時点で、共働き世帯数は専業主婦世帯数の3倍以上となっており、妻がフルタイムの共働き世帯数も増加傾向にある(特-I図、特-II図)。近年は、未婚女性の理想も、未婚男性の将来のパートナーに対する期待も、「両立コース」が「再就職コース」を上回る(特-III図)など、我が国において、男女を取り巻く環境や若い世代の理想とする生き方は変わってきている1。また、女性の正規雇用比率は、20代から40代を中心に上昇している2。
特-I図 共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移(妻が64歳以下の世帯)![]()
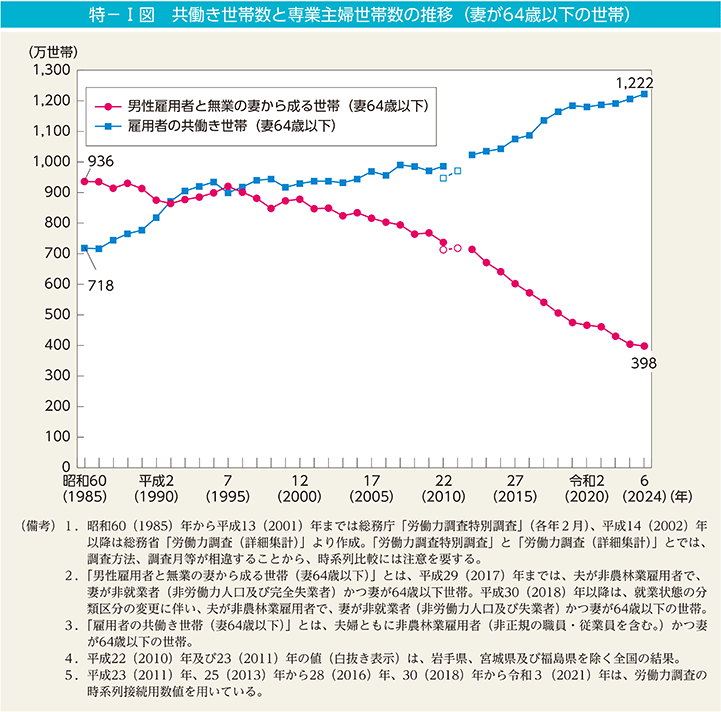
特-II図 妻の就業時間別共働き等世帯数の推移(妻が64歳以下の世帯)![]()
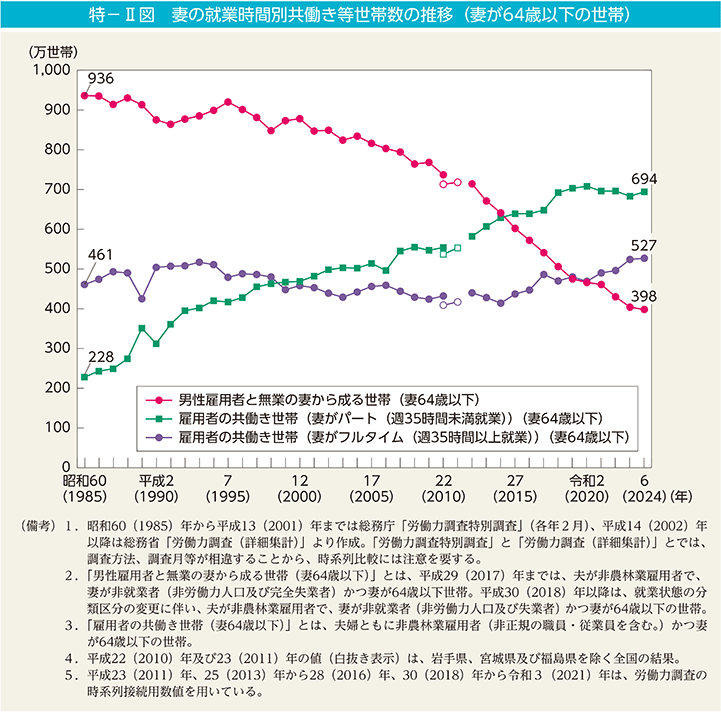
一方、令和6(2024)年の世論調査3において、社会全体として男女の地位が「平等になっている」と答えた人の割合は、女性で12%、男性で22%にすぎず、女性の参画が進んでいる分野がある一方で、進捗が遅れている分野もある(特-IV図)。また、男女共同参画に関する取組の進捗状況には、地域間で差異がみられる。都市においては、全ての人が希望に応じて、家庭でも仕事でも活躍できる社会、「令和モデル」が浸透しつつある一方、地方では、「男性は仕事」、「女性は家庭」の「昭和モデル」がいまだに残っているとの指摘もある。
特-IV図 男女の地位の平等感(男女、分野別・令和6(2024)年)![]()
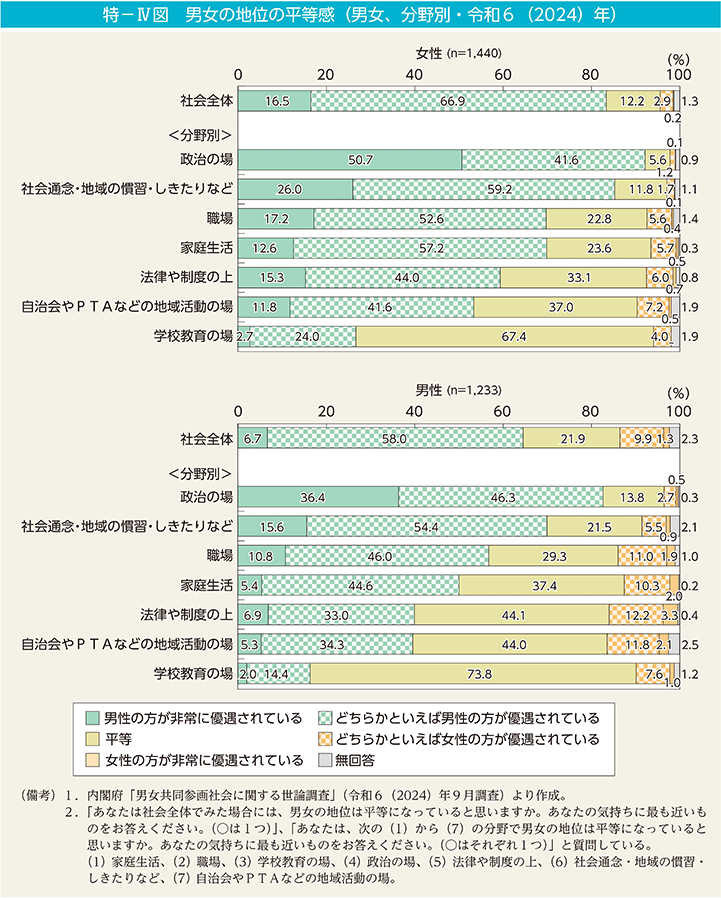
近年は、若い女性が地方から都市へ転出する傾向が強くなっている。女性や若者の都市への転出によって、地方の活力が低下すると同時に、地域によって男女別人口の不均衡が発生することから、未婚化や少子化の要因の一つともなり、将来的には、都市を含む日本全体の活力の低下につながることも懸念されている。
我が国の将来を見据えると、地方がその活力を高めていくためにも、男女共同参画を推進し、固定的な性別役割分担意識から解放され、都市に住む人も地方に住む人も、全ての人が希望に応じて、その個性と能力を十分に発揮することができる地域へと変革するための取組を推進することが、非常に重要である。
地域ごとに女性を取り巻く状況は異なっており(特-V図)、地域の実情を把握し、それに応じた形で全国各地における男女共同参画に関する取組を進めていく必要がある。
第1節、第2節では、地域における女性や若者を取り巻く状況について、政府統計などの各種データ及び内閣府で実施した意識調査結果等を中心に整理した上で、固定的な性別役割分担意識等に基づく地域における構造的な問題に起因する課題を明らかにし、第3節では、男女共同参画の視点から見た魅力ある地域づくりについて考察する。
1 若い世代における意識の変化については、「令和5年版男女共同参画白書 特集-新たな生活様式・働き方を全ての人の活躍につなげるために~職業観・家庭観が大きく変化する中、「令和モデル」の実現に向けて~」で分析している。
2 「令和6年版男女共同参画白書」特-3図を参照。
3 内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」(令和6(2024)年9月調査)
特集のポイント
第1節 人の流れと地域における現状と課題
- 東京都と埼玉県を除く全ての道府県で人口が減少。全都道府県で死亡者数が出生児数を上回る一方、都市では社会増加(転入・入国超過)、地方では社会減少(転出・出国超過)。
- 都道府県間の人口移動は10代後半から20代が中心となっている。また、東京圏のみ男女ともに転入超過が続いている。なお、女性は男性に比べて東京圏に留まる傾向がある。
- 教育環境、就業・雇用環境、生活環境は地域により異なっている。
- 各分野における女性参画の状況も、地域によって差がある。あらゆる分野において、政策・方針決定過程に男女が共に参画し、様々な視点が確保されることは、豊かで活力ある持続可能な社会の形成及びあらゆる人が暮らしやすい社会の実現につながる。
第2節 若い世代の視点から見た地域への意識
- 出身地域を離れた理由は、希望する進学先や就職先の少なさ。加えて女性は、「地元から離れたかったから」、「親や周囲の人の干渉から逃れたかったから」等も理由に挙げる。
- 「夫は仕事、妻は家庭」という考え方に反対する人の割合は上昇しているが、若い女性の25%が「家事・育児・介護は女性の仕事」等の固定的な性別役割分担意識等があると感じている。都市よりも地方の方があると感じている割合が高く、男女の意識差も大きい。
- 東京圏以外から東京圏に転出した女性は、出身地域において固定的な性別役割分担意識等があったと感じている割合が特に高く、地方から都市への転出につながり、また、地元に戻ることへの心理的障壁となっている可能性がある。
- 現住地域に満足している割合は、東京圏居住者で高く、特に仕事の選択肢の豊富さや収入面、生活の利便性の面で高い。女性は、多様な生き方・価値観の尊重、性別・年齢にかかわらず活躍できる環境の面でも、満足している割合が高い。また、仕事面では、仕事内容や昇進などに男女の差異が少ないことにも満足している割合が高い。
- 出身地域への愛着は女性の方が高く、出身地域に戻りたいと考えている女性も一定数存在する。親や兄弟姉妹の居住地と近いこと、ゆとりのある暮らしができそうであること、自然環境の豊かさなどがその理由。他方で、収入や仕事、利便性、仕事と子育ての両立などが不安要素となっている。
第3節 魅力ある地域づくりに向けて
- 全ての人が希望に応じて活躍できる社会の実現を目指し、全国津々浦々で地域における男女共同参画社会を実現することが重要。
- 地域の男女共同参画が進み、地域の活力が高まることが、日本全体の活力向上、ウェルビーイングの向上につながる。
- 多様な生き方・価値観が尊重され、全ての人が性別にかかわらず、個性と能力を十分に発揮できる環境の整備や魅力的な地域づくりの取組の推進が重要であり、そのような地域が、女性や若者にも選ばれる地域となるだろう。
- そのために優先すべき課題は次のとおり。
1.固定的な性別役割分担意識・無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)の解消
2.女性が活躍できる職場への改革と全ての人にとって働きやすい環境づくり
3.あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大
4.地域で学ぶ選択肢の増加
※ 本特集では、国内の地域及び3大都市圏について、以下の区分により記述している。
<地域ブロック>
北海道:北海道
東北:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
北関東・甲信:茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県
南関東(東京圏):東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
北陸:新潟県、富山県、石川県、福井県
東海:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国:徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄:沖縄県
なお、第2節では、九州と沖縄をまとめて「九州・沖縄」としている。
<3大都市圏>
3大都市圏とは、東京圏、名古屋圏、大阪圏をいい、各大都市圏に含まれる地域は次のとおり。
東京圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県
※ 本特集に掲載している地図は、我が国の領土を網羅的に記したものではない。