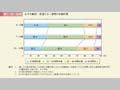本編 > 第1部 > 特集 > 第2節 女性の再就職・起業等の現状
第2節 女性の再就職・起業等の現状
ここでは,女性の再就職・起業等をめぐる問題点を整理し,希望に沿った再チャレンジがなかなか進まない状況を明らかにする。
1 再就職
(子どもの年齢が上がるにつれ再就職している実態)
厚生労働省の「21世紀出生児縦断調査」は,平成13年1月及び7月に出生した子について定期的に追跡調査している。平成17年に公表された第4回の調査結果では,第1回以来の母の就業割合の変化が分析されており,年数を経て子どもの年齢が上がるにつれ,母親の有業割合が上昇していることがわかる(第1-特-16図)。
(30歳代,高学歴の女性で低い再就職率)
日本労働研究機構が行った求職者調査より女性の再就職の状況をみると,求職者のうち実際に再就職した者の割合は,29歳以下で67.1%,40歳代で69.4%であるのに対し,30歳代で54.3%と低くなっている。男性と比べて特に30歳代での女性の再就職が困難である状況がうかがわれる(第1-特-17図)。さらに,第1-特-3図でみたように,女性の就業希望率は30歳代で最も高くなっており,希望と現実が大きく乖離している状況となっている。
女性の有業率を学歴,年齢階級別にみると,20~34歳では大学・大学院卒の有業率が最も高いが,40歳代では逆転し,他の学歴に比べて低くなっている(第1-特-18図)。大卒者等高学歴の女性が結婚・出産等でいったん離職した後,再就職せずに無業でとどまる者が相対的に多い状況にあるといえる。この理由は明らかではないが,また,大卒等の女性が結婚・出産前に就いていた職と比べ満足できる就職先を見つけることが難しいなどの現実があるのではないか。
(30歳代以降で高まる勤務条件面でのミスマッチ)
女性の就業希望者のうち,過去1年間に求職活動をしていたが,現在は求職活動をしていない者についてその理由をみてみると,30歳代を中心に「勤務時間・賃金などが希望にあう仕事がありそうにない」,「家事・育児のため仕事が続けられそうにない」とする者が多くなっている(第1-特-19図)。30歳代で再就職を希望する場合,仕事と家庭の両立が難しいことに加え,勤務時間等の条件面でのミスマッチが障害となっていることがうかがわれる。
第1-特-19図 女性就業希望者の非求職理由(過去1年間に求職活動のある者) ![]()

(高学歴の女性ほど知識や技能を社会で生かしたいと思っている)
現在無業で就業を希望する女性の就業希望理由は「収入を得る必要が生じた」が多いが,大卒等の女性では「知識や技能を生かしたい」,「社会に出たい」の割合が高まっている(第1-特-20図)。収入以外の要素をより重視していることが,高学歴女性の再就職を難しくしている要因の一つとなっていると考えられる。
第1-特-20図 就業を希望する女性の就業希望理由(学歴別) ![]()

(再就職女性のパート就業率は一層増加)
女性の雇用形態は多様化が進展し,かつては25歳以下の若年層のほとんどは正社員であったが,現在ではすべての年齢層においてパート・アルバイトの割合が増加している。なかでも,子育て期以降のパート・アルバイトの割合が増加しており,平成4年には60歳未満のすべての年齢階級で正社員の方が比率が高かったのが,平成14年には40歳以上のすべての年齢階級でパート・アルバイトが正社員を上回っている。これに対し,男性は平成14年にはパート・アルバイトの割合が増加しているものの,一貫してほとんどが正社員である(第1-特-21図)。
労働力率はM字型カーブであるが,正社員雇用者比率はM字の右肩に該当する部分がなく,いわば「への字型カーブ」となっている。M字型カーブの右肩部分について時系列でみると全体として上昇しているが,正社員については時系列でみてもほとんど変化がなく,M字型カーブの右肩部分の上昇はもっぱらパート・アルバイトの増加によるものであることがわかる。
このように再就職後の女性にパート・アルバイトが多いことに加え,依然正社員とパートの間に賃金格差が存在することが,男女の所得格差にもつながっていると考えられる。
末子年齢別の女性の就業状況の変化を平成4年と平成14年で比較してみても,平成14年では末子の年齢が高くなっても正規雇用があまり増えず,非正規雇用が大幅に増加していることがわかる(第1-特-22図)。
(子どもが高学年になるとフルタイム等30時間以上の就業を希望する女性が増える)
一方,これから就労したいと思っている,末子が4歳以上小学生までの子どもをもつ女性に希望する1週間の労働時間を聞くと,末子が10~12歳になると30時間以上の労働時間を希望する割合が高まってきており,40時間以上を希望する者の割合も高まっている(第1-特-23図)。このことから,末子が小学校高学年になるとフルタイム労働等を希望する女性が増えていくことがわかる。
子どもが小さいうちはパートタイムで就職し,大きくなったらフルタイム就職に変わりたいと考える女性も多いと推測できる。
(希望どおり正社員になれる女性は約半数)
再就業活動時に正社員を希望していた女性が実際に就業している形態をみると,希望どおり正社員となっているのは約半数にとどまり,約3割はパート,アルバイトでの就業となっている(第1-特-24図)。女性にとって,正社員での再就職が厳しいものである状況がうかがえる。
また,再就職に成功した女性のうち,育児のために転職した女性の離職期間をみると,3年以下の者が5割近くを占めており(第1-特-25図),離職期間が長くなるにしたがって割合が減っていく傾向がみられる。さらに,中断期間別に就業形態をみると,離職期間が長くなるほど正社員での再就職が減少しており,正社員での再就職を希望する場合は早期に行う方が実現しやすいといえる(第1-特-26図)。
(再就業に当たっての課題・不安は子育てとの両立,企業の採用行動の問題)
希望に沿った再就業が難しい要因としては,保育サービスが不十分であることや企業における働き方の問題などに起因する仕事と子育ての両立困難,また,年齢制限など企業側の採用行動の問題などが考えられる。女性の側の意識からみても,再就業経験のある者,又は今度再就業する予定の者が抱える再就業に当たっての課題,不安は,「子育てと両立できるか不安」,「年齢制限があり,応募できるところが少ない」,「条件のあう職場が見つからない」が上位を占めている(第1-特-27図)。
(企業の女性中途採用はまだ少ない)
企業の側の採用行動をみてみる。厚生労働省の平成12年の調査によると,中途採用者を採用した企業の中で,出産・育児期にいったん退職し,子育てが一段落した女性を採用した企業は,中途採用者を採用した企業のうち18.9%となっている。また,3年前と比べると,女性の中途採用が増えた企業は11.3%にとどまっている(第1-特-28図)。
2 起業
(子育て期の女性に多い起業希望者)
就業や転職を希望している女性のうち,自ら起業をしたいと考えている者を年齢階級別にみると,M字型カーブのボトムを形成する,子育て期にあたる30歳代に最も多くなっている(第1-特-29図)。
(高まる起業家に占める女性割合)
会社役員と自営業主の合計である自己雇用者数の推移をみると,女性が占める割合は増加を続けている(第1-特-30図)。起業を含む経営への女性の意欲が高まっていることがうかがわれる。
(事業継続に必要な支援)
実際に起業した者が開業後に直面した困難を男女別にみると,男性は商品開発,顧客開拓が難しいと回答した者が多いが,女性では経営知識の不足や,家事・育児との両立に関する困難を感じている者が多い(第1-特-31図)。経営面の支援と同時に,創業者それぞれの家庭における協力を得られることが重要であると考えられる。
3 NPO等の市民活動
子育てが一段落した女性が,就業だけでなく,様々な地域活動において活躍している事例もみられるようになってきている。市民活動団体におけるスタッフの構成を性別にみると,「女性だけ,あるいは女性がほとんど」が38.3%と最も高く,女性が積極的に市民活動に参加していることがわかる(第1-特-32図)。子育て後の女性の再チャレンジの舞台として,NPO等への参加がさらに進むことが期待される。
第1-特-32図 市民活動団体の活動分野別スタッフの構成(性別) ![]()

以上のように,女性が結婚・出産等でいったん退職し,子育てが一段落した後に再就職しようとしてもその壁は厚い。特に,正社員で再就職することは,中断期間が長くなればなるほど難しいのが現状である。早い時期から再チャレンジのための学習・能力開発や情報収集を進めておくことが望ましい。
企業側の女性の再就職受入れはまだ少数にとどまっており,募集・採用時の年齢制限の撤廃や再就職女性を含め子育て中の男女が仕事と子育てを両立することが可能な就業環境の整備などが求められる。
起業やNPO活動については,意欲の高い女性も多く,実際に独創的な成果を上げている例も多くみられる。日本社会の活性化のためにも,女性本人の自己実現のためにも,一層の活躍が期待される。