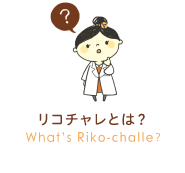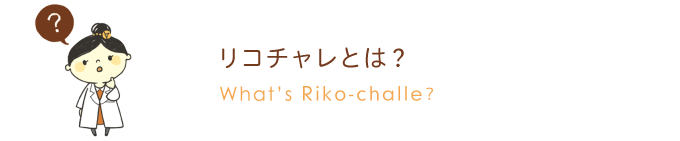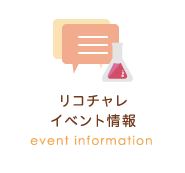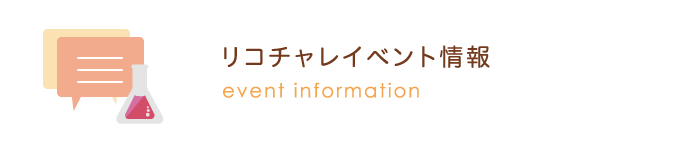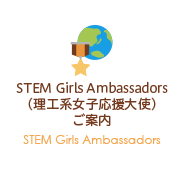先輩からのメッセージ

- 石原 恵子 さん
- 広島国際大学総合リハビリテーション学部教授
- 研究分野:人間工学、感性工学、リハビリテーション工学、高齢者支援:若くて元気な人だけでなく、高齢の方や女性、障がいのある方など、様々な人を対象に、ユーザーの身体や感じ方、行動などの特性を理解して、モノの設計を適合させることで、使いやすく、使って喜びを感じるものにする、というモノづくりです。
- 所属学会:International Society of Gerontechnology(国際ジェロンテクノロジー学会)、日本人間工学会、日本感性工学会、RESNA(北米リハビリテーション工学協会)など 広島国際大学総合リハビリテーション学部リハビリテーション支援
- 学科HP:広島国際大学

工学系分野を選択した時期・理由
【モノづくりへの興味】
小学校5年のとき、雑誌の付録にあった鉱石ラジオのキットに始まって、中学生の頃まで、当時、大学生の叔父が教えてくれたことが、工学系モノづくりへのきっかけになりました。お菓子づくりや編み物にも励みましたが、仕組みさえ分かれば、少しずつ変えて自分の作りたいものが作れることが楽しかったのだと思います。中学校の終わりには、仕組みを学んでモノづくりをしようと思い、工学部に行くつもりでした。
【大学で出会った工学系の仕事】
大学では、コンピュータのプログラミングが気に入って、これなら男性のような力も要らないし、会話するように見えるプログラムを作ったり、シミュレーションをしたり、ゲームを作ったりと、様々なことができるからです。
専門課程で人間工学の授業で人の特性に合わせた職場設計や機器設計を学び、人間工学実験では人間の生理特性や認知特性を測定しました。それまで自分だけの感覚でしかなかったことが、目に見える測定データになり、他の人たちと共有できることが感動的でした。そして、環境によって、人間の苦手なことも、特性を活かすこともできるとわかって、自分も人を活かすモノづくりがしてみたいと思うようになりました。
現在の仕事(研究)の魅力やおもしろさ
【モノづくりの研究と人づくりの仕事】
リハビリテーション工学の学科で大学の教員として、人間工学を中心とした研究開発に関わるところと、学生さんの教育に関わるところと、両方の仕事をしています。
【研究開発の楽しみ】
リハビリテーション工学は日本でこそ聞き慣れない言葉ですが、アメリカではリハビリテーション・エンジニア、またはアシスティブ・テクノロジスト(AT)の資格が必要となる、確立された分野です。怪我をした患者さんが入院して、うまく起きられないうちから、呼吸や食事のしやすい姿勢を保つ装置や、話すのが難しい人にはコミュニケーション・エイドを提供します。さらに、ゆくゆくはその人が家族のもとへ、仕事の場へ戻るために、身体が不自由でも安全に運転できる車や、予定や手順を忘れても助けてくれるロボット、仲間と楽しんでトレーニングできるゲームなど、身体や頭の働きを助ける装置や生活環境を提供する専門の工学者です。医療系の中でも、患者さんの症状を「治す」よりももっと長い「人生」に関わってきます。 このための技術や洞察力、ユーモアの精神などは、怪我をした人や障がいのある人に限らず、男性よりも力の弱い・体格の小さい女性や高齢の人なども含めて、多くの人が使いやすく、それを使うことで楽しくなる、やる気が出るためのモノづくりです。
地元企業の研究職・開発職・営業職の方々と一緒に商品コンセプトを考え、実験や分析をし、改良し、良いところを消費者にきちんと伝える方法を考えるお手伝いを楽しんで取り組んでいます。責任も大きいですが、よい商品を作る企業が利益を上げ、ユーザーにとって本当に使いやすく人生が豊かになる「モノづくり」がずっと続けられる「仕事づくり」が目標かもしれません。
【学生と協働する楽しみ】
「ひとが好き」「モノづくりが好き」「人の役に立ちたい」この思いさえある学生さんなら、研究としてやっている測定や実験、現場での試用にどんどん参加してもらいます。最初は大変ですが、いろいろな場面に入っていくうちに自信をつけて、顔つきも変わってきます。私のゼミは「イケメン、イケジョが育つゼミ」なのです(笑)。
女子中高生・女子学生の皆さんへのメッセージ
やってみたいと思ったことは、とりあえずやってみましょう。女性が受け入れられる環境は、どんどん広がってきています。結婚や出産は、確かに仕事上のハードルになります。でも、子どもを持ったら持ったで、また、違った世界が見えてきて、ひと味ちがった仕事ができるようになります。今しかできない、自分にしかできない仕事を、見つけて実行してください。