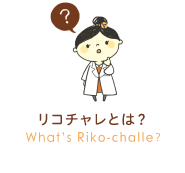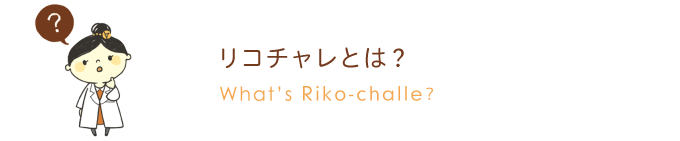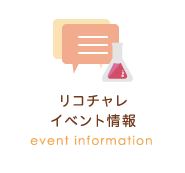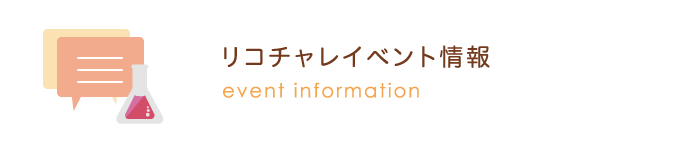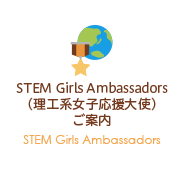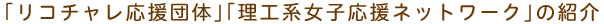「リコチャレ応援団体」
「理工系女子応援ネットワーク」の紹介

- 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立極地研究所
- National Institute of Polar Research
- 東京都立川市緑町10-3
-
国立極地研究所

組織概要
国立極地研究所は、「極地に関する科学の総合的研究及び極地観測を行うこと」を目的とした大学共同利用機関で、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構を構成する4研究所の一つです。研究者は100名程度、事務系職員を含めると250名程度の組織です。
南極大陸と北極圏に観測基地を擁し、日本の極域科学の中核機関として、極域科学を地球科学、環境科学、太陽地球系科学、宇宙・惑星科学、生物科学などを包含した先進的総合地球システム科学ととらえ、国内外の研究者との共同研究を進めています。また、大学及び研究機関の研究者等に南極・北極における観測の基盤を提供するとともに、資試料及び情報を提供しています。さらに、我が国の南極地域観測事業の実施中核機関として、計画の立案及び観測隊の準備、プロジェクト観測や基地の運営等も行っています。
なお、大学院教育では総合研究大学院大学複合科学研究科極域科学専攻(入学定員:5年一貫制2名、博士課程後期1名)を担当しているほか、他大学からの要請を受けて当該大学の教育にも協力して、幅広い視野を持った国際的で独創性豊かな研究者を養成しています。
理工系分野・部門の紹介
国立極地研究所には次の5つの基盤研究グループと、南極観測センター、国際北極環境研究センター、極域データセンター、極域科学資源センター及びアイスコア研究センターの5つのセンターがあります。
研究者は、主に5つの基盤研究グループに所属しています。南極や北極のフィールドに最も近い研究所であるため、大学院生も含めて、極地の現場での研究観測に直接触れる機会が多くあります。
- 【宙空圏研究グループ】
- 高度10km以上の成層圏から太陽系の惑星間空間までの広大な空の範囲が研究対象です。南極域や北極域に大型のレーダーや磁力計、全天イメージャなどを用いた広域多点観測ネットワークを展開し、オーロラ現象やその生成に関係する太陽風・磁気圏・電離圏相互作用メカニズムの解明を目指した研究を行なっています。
- 【気水圏研究グループ】
- 極域の大気圏(対流圏と成層圏)、雪氷圏、海洋圏を研究対象とし、現在どのようなことが起きているのか、過去の地球環境や気候はどのような状態であったのか、今後どのようになるのかを明らかにするため、相互に関連する気水圏の変動メカニズムに関する研究を主に現地観測と衛星リモートセンシングによって進めています。大気科学、気象学、雪氷学、海氷・海洋、古気候学などが研究テーマです。
- 【地圏研究グループ】
- 太陽系形成期時の46億年前から現在までの宇宙史や、地球の誕生から今日までの地殻進化変動史、氷床の消長に伴う第四紀環境変動史、現在の地殻変動や海面変動を、地質・鉱物学、地形・第四紀学、測地・固体地球物理学の手法で解明すべく研究を進めています。
- 【生物圏研究グループ】
- 南極や北極など極めて厳しい環境でどうして生き物が生きてゆけるのかを、生き物の棲んでいる場所や種類によって、(1)極地の海の小さな生物(植物プランクトン、動物プランクトンなど)、(2)極地の海の大きな生物(海鳥、ペンギン、アザラシなど)、(3)極地の陸上や湖沼の生物の、3つの研究対象に分けて研究しています。
- 【極地工学研究グループ】
- 極地で研究観測を行なう場合、厳しい寒さ・強風・積雪への対策が課題となります。また、輸送手段が限られているため、限られた燃料・食料・資材等をいかに有効活用するか、また最近では、周辺の環境への影響をいかに小さくするかも大きな課題です。極地工学では、これら極地観測に付随する様々な技術的課題の解決に取り組んでいます。
女子中高生・女子学生の皆さんへのメッセージ
南極・北極の観測や研究には、これまでも多くの女性が参加しています。特に、南極地域観測隊には隊員として延べ65名(越冬隊29名、夏隊36名)の女性が参加しています。しかし、まだまだ諸外国と比較すると日本のこの分野の女性研究者は少数です。南極・北極を飛び回り、将来の日本の極域科学研究を担う意欲のある女性を歓迎します。
あなたも是非チャレンジして私たちの仲間になりませんか。