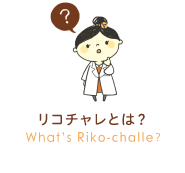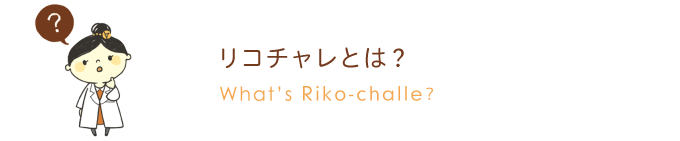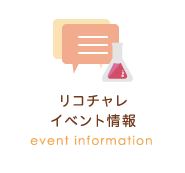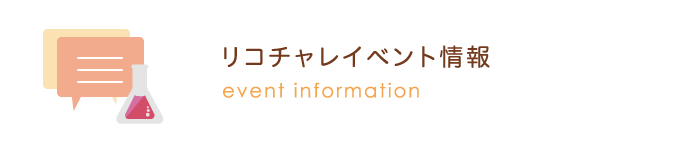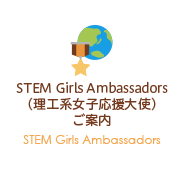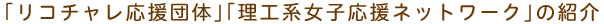「リコチャレ応援団体」
「理工系女子応援ネットワーク」の紹介

- 国立研究開発法人 防災科学技術研究所
- 〒305-0006
- 茨城県つくば市天王台3-1
-
国立研究開発法人 防災科学技術研究所

組織概要
防災科学技術研究所は、1959年(昭和34年)9月に我が国を襲って5,000名を超える死者を出した伊勢湾台風を契機として、1963年(昭和38年)4月に設立されました。その後、2001年(平成13年)4月に国立の試験研究機関から独立行政法人という組織に生まれ変わり、10年が経過しています。
防災科学技術研究所の基本目標は、災害に強い社会の実現です。すべての人々が安全で平和に暮らせる社会を創るために、災害に強い社会を実現するための科学技術を発展させることが私たちの使命です。
研究所全体の職員数は280名(うち女性115名)、研究者は125名(うち女性15名)です。
理工系分野・部門の紹介
防災科学技術研究所では、災害に強い社会を実現するために、様々な研究に取り組んでいます。 地震災害分野では、平成7年の阪神・淡路大震災を受けて整備が進められた全国的な地震観測網、および実大三次元震動破壊実験施設(E-ディフェンス)を用いて、様々な「ゆっくり地震」の発見や「緊急地震速報」の実用化、構造物の破壊過程解明や耐震性能の検証などを進めています。
また、火山災害分野では、我が国の主要な活動的火山に対する基盤的火山観測施設の整備を開始し、観測データの収集・発信を通じて気象庁における監視業務や全国の大学における火山研究に貢献する体制を整えつつあります。
気象災害分野では、当研究所が長年培ってきた気象レーダに関する技術が、近年大きな問題となってきている局地的豪雨の監視に威力を発揮することが実証され、浸水被害危険度の予測や土砂災害危険度の予測へと、その応用範囲を広げています。
雪氷災害分野においても、降積雪の予測から始まって、雪崩や地吹雪などの発生危険度を推定する「雪氷災害発生予測システム」がほぼ実用化のレベルに到達し、地方自治体や道路管理事業者等と協力して、試験的な運用を始めています。
さらに、全国各地の地震危険度や揺れやすさを示す「全国地震動予測地図」をはじめ、各種の自然災害に対するハザード情報の整備を進めると同時に、それを個人や地域にとってのリスク情報に変換し、国民一人ひとりに届けることができる環境の整備を目的として、社会科学的なプロジェクトも開始しています。
このような数々の成果を受け、また、文部科学省や総務省・財務省との協議を経て、平成23年度からは、新しい5ヵ年計画である「第3期中期計画」に沿って、研究所の業務を進めています。
これに合わせて、研究所の組織については、研究部門を観測・予測研究領域、減災実験研究領域、社会防災システム研究領域の3つに再編成し、管理部門からは経営企画室を独立させるなど、効率的に業務を遂行できる体制としました。また、研究成果の社会還元と国際連携を一層強化するため、新たに「アウトリーチ・国際研究推進センター」を設け、日々防災の研究・成果の発信に取り組んでいます。
女子中高生・女子学生の皆さんへのメッセージ
防災科学技術研究所は、女性研究者が、様々なライフステージにおいて、その能力を十分に発揮しつつ研究活動に取り組める環境作りや、そのための役職員の意識改革などに取り組んでいます。
たとえば、妊娠・育児期間中の環境作りとして、フレックスタイム制、産前産後休暇、育児期間中の勤務時間短縮等の制度の活用を推進して、女性の働きやすい環境作りに取り組んでいます。
職場の状況を考慮した妊娠・育児期間中の支援制度の導入や、出産・育児を考慮した業績評価に係る評価基準の設定を図るとともに、さらに、ワークライフバランス(仕事と生活の調和)の実現の観点から、研修等を通じて、男女ともに働きやすい職場環境作りを推進する取り組みを行っています。
防災科学技術研究所で、日本の未来を守る防災の研究に取り組んでみませんか。