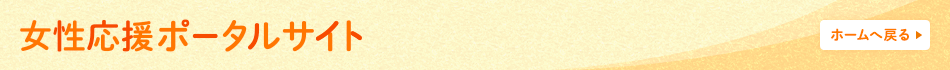子育て・介護など安心して妊娠・出産・子育て・介護をしたい
子育ての支援
![]() 主に女性向け
主に女性向け
![]() 主に男性向け
主に男性向け
![]() 企業や団体の経営者や管理部門の方向け
企業や団体の経営者や管理部門の方向け
![]() 地方自治体や行政機関の方向け
地方自治体や行政機関の方向け
- 子ども・子育て支援制度
-
-
-
概要
『子ども・子育て支援制度』とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度であり、すべての子ども・子育て家庭を対象に、幼児教育・保育・地域の子育て支援の質・量の充実を図るものであり、平成27年4月1日から施行しました。 さらに、令和元年10月から、3歳から5歳までの子供及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもについての幼稚園、保育園、認定こども園等の費用が無償化となりました。
子ども・子育て支援制度は、
- 子育て中のすべてのご家庭を支援する制度です。
- 幼児教育・保育・地域の子育て支援の質・量の充実を図ります。
- 「認定こども園」への移行を支援します。
- 多様な保育の確保により、待機児童の解消に取り組みます。
- 地域の様々な子育て支援を充実します。
- 令和元年10月から、3歳から5歳までの子供及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもについての幼稚園、保育園、認定こども園等の費用が無償化となりました。
新制度の詳しい内容や子ども・子育て会議等の詳細をご覧いただけます。
担当省庁
こども家庭庁
成育局保育政策課
03-6771-8030(代表)
- 育児・介護休業法の履行確保
-
-
-
概要
育児・介護休業法の履行確保により、育児や介護を理由とした離職を防止して継続就業できる職場環境を整備します。
育児・介護休業法が遵守されるよう、事業主及び労働者に対し、法の周知・徹底を図るほか、事業主に対する指導、労働者と事業主との間の紛争を迅速に解決するための調停等を行います。
また、企業において、育児・介護休業法に基づく両立支援制度が利用しやすい職場環境が整備されるよう支援を行います。
事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。関連サイト
担当省庁
厚生労働省
雇用環境・均等局 職業生活両立課
03-5253-1111(代表)
- ひとり親家庭等日常生活支援事業
-
-
-
概要
ひとり親家庭が必要なときに、家庭生活支援員を派遣し、児童の世話や生活援助を行います。
ひとり親家庭に対し、次の場合に家庭生活支援員の派遣等を行います。主に、児童の生活指導や食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品等の買い物、医療機関等との連絡、その他必要な用務が対象となります。
(1)修学や疾病、冠婚葬祭などにより、一時的に家事援助、未就学児の保育等の支援が必要となる場合
(2)乳幼児又は小学校に就学する児童を養育している家庭であって、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる場合等に定期的に生活援助、保育サービスが必要となる場合ひとり親家庭等日常生活支援事業について
(https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/hitorioya-seikatsu-shien/)
担当省庁
こども家庭庁
支援局 家庭福祉課
03-6771-8030(代表)
- 居宅訪問型保育事業
-
-
-
概要
子ども・子育て支援制度において、ひとり親家庭で夜間の勤務がある場合など必要性が高い場合に保護者の自宅で1対1で保育を行う事業です。
子ども・子育て支援制度では、ひとり親家庭で夜間の勤務がある場合や障害、疾病等により集団保育が著しく困難な場合等で、市町村が必要を認めた場合に、居宅訪問型保育事業を利用することが可能です。
子ども・子育て支援制度(https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/outline)

担当省庁
こども家庭庁
成育局保育政策課
03-6771-8030(代表)
- 新子育て安心プラン
-
-
-
概要
できるだけ早く待機児童の解消を目指すとともに、女性(25歳~44歳)の就業率の上昇に対応するため、「新子育て安心プラン」に基づき、令和3年度から令和6年度末までの4年間で約14万人分の保育の受け皿を整備します。
新子育て安心プランでは、地域の特性に応じた支援、仕事・職場の魅力向上を通じた保育士確保の推進、幼稚園・ベビーシッターを含めた地域のあらゆる子育て資源を活用します。
「新子育て安心プラン」について(https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/shin-plan/)

担当省庁
こども家庭庁
成育局保育政策課
03-6771-8030(代表)
- 放課後児童対策
-
-
-
概要
放課後児童対策を一層強化し、こどものウェルビーイングの向上と共働き・共育ての推進を図るため、こども家庭庁と文部科学省がとりまとめた「放課後児童対策パッケージ」に基づき総合的な取組を推進します。
全ての児童が放課後等を安心・安全に過ごし、多様な体験・活動を行えるよう、校内交流型・連携型による放課後児童クラブ及び放課後子供教室の計画的な整備等を進めます。
- 放課後児童クラブ(こども家庭庁)・・・共働き家庭など留守家庭の小学生に対して、学校の余裕教室や児童館、公民館などで、放課後に適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図ります。
- 放課後子供教室(文部科学省)・・・全ての子供を対象として、地域住民等の参画を得て、放課後や週末等に学校の余裕教室等を活用して、学習活動や様々な体験・交流活動等の機会を提供する取組です。
関連サイト
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)
(https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/houkago-jidou/)
学校と地域でつくる学びの未来(https://manabi-mirai.mext.go.jp/)

開始時期
継続
担当省庁
こども家庭庁
成育局成育環境課
03-6771-8030(代表)文部科学省
総合教育政策局 地域学習推進課
03-5253-4111(代表)
- ベビーシッター等の子どもの預かりサービスへの対応
-
-
-
概要
ベビーシッターなどの子どもの預かりサービスについて、届出制やマッチングサイト運営者が遵守すべきガイドラインに関すること等について、利用者に子どもの預かりサービスを安心して利用していただくための情報提供等をします。
ベビーシッターなどの子どもの預かりサービスについて、親しい知人の子どもを預かる場合などの一部の例外を除き、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設、訪問型の事業に届出義務が課されていることや、マッチングサイト運営者が遵守すべきガイドラインの内容のほか、各サイトのガイドラインへの適合状況について周知すること等により、利用者が子どもの預かりサービスを安心して利用できる環境を整備します。
ガイドライン適合状況調査サイト(https://matching-site-guideline.jp/)

開始時期
継続
担当省庁
こども家庭庁
成育局保育政策課
03-6771-8030(代表)
- 女性が変える未来の農業推進事業のうち地域における女性活躍推進事業(女性農業者の育児と農作業のサポート活動)
-
-
-
概要
女性が働きやすい環境整備のため、女性農業者の育児と農作業のサポート活動を支援します。
女性を雇用する農業法人の事務所や子育て世代の女性農業者がいる地域の空きスペース等における託児スペースの設置、保育者等による託児、地域の女性農業者に対する地域住民等による農作業サポートを支援します。
農林水産省HP「女性の活躍を応援します」
(https://www.maff.go.jp/j/keiei/jyosei/index.html)
開始時期
継続
担当省庁
農林水産省
経営局 就農・女性課
03-3502-6600
- 「ベビーカーマーク」の普及促進
-
-
-
概要
公共交通機関等においてベビーカーを安心して利用でき、乳幼児と外出しやすくなるよう「ベビーカーマーク」の普及啓発活動を実施しています。
公共交通機関等における子育てにやさしい移動環境の整備に向けて、関係者で必要な事項の協議を進めるため「子育てにやさしい移動に関する協議会」を設置し、ベビーカーの安全な使用やベビーカー利用への理解・配慮を求めるポスターやチラシを活用した普及啓発を実施しています。
関連サイト
開始時期
継続
担当省庁
国土交通省
総合政策局バリアフリー政策課
03-5253-8111(代表)
- 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
-
-
-
概要
育児と仕事の両立支援に取り組む事業主を支援するための助成金です。
育休復帰支援プランを策定し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた場合、復帰後仕事と育児の両立が特に困難な時期の労働者の支援に取り組んだ場合の中小企業事業主に助成金を支給します。
関連サイト
都道府県労働局所在地一覧(厚生労働省HP)
(https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/)
開始時期
継続
担当省庁
厚生労働省
雇用環境・均等局 職業生活両立課
03-5253-1111(代表)
- 両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)
-
-
-
概要
育児休業や短時間勤務の期間中の業務体制整備に取り組む事業主を支援するための助成金です。
育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合の中小企業事業主に助成金を支給します。
関連サイト
都道府県労働局所在地一覧(厚生労働省HP)
(https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/)
担当省庁
厚生労働省
雇用環境・均等局 職業生活両立課
03-5253-1111(代表)
- 民事法律扶助におけるひとり親支援の拡充
-
-
-
概要
日本司法支援センター(法テラス)では、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、民事法律扶助として、無料法律相談を行ったり、裁判等に必要となる弁護士費用等の立替えを行っています。
養育費を必要とするひとり親の方もこれらを利用でき、法テラスが立て替えた弁護士費用等の償還免除を受けられる場合があります。
令和6年4月には、一定のひとり親の方に対する償還免除の範囲が拡大されるなど、支援の拡充が行われました。
ご利用には、収入や資産が一定基準以下であることなどの条件が必要ですので、まずはお問合せください。以下にお問い合わせください。
【法テラスサポートダイヤル 0570-078374(おなやみなし)】
・受付時間 平日午前9時~午後9時、土曜日午前9時~午後5時(祝日・年末年始休業)
・IP電話からは03-6745-5600
・法律相談の場合は、お住まいの最寄りにある法テラスの事務所へ取り次ぎます。民事法律扶助におけるひとり親支援の拡充について
(https://www.houterasu.or.jp/soshiki/15/hitorioyashien.html)
開始時期
令和6年4月
担当省庁
法務省
司法法制部・司法法制課
03-3580-4111(代表)
- 両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)
-
-
-
概要
育児を行う労働者が柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入した事業主を支援するための助成金です。
育児を行う労働者が柔軟な働き方に関する制度を選んで利用できるよう、制度・措置を導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により労働者を支援した中小企業事業主に助成金を支給します。
関連サイト
都道府県労働局所在地一覧(厚生労働省HP)
(https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/)
担当省庁
厚生労働省
雇用環境・均等局 職業生活両立課
03-5253-1111(代表)