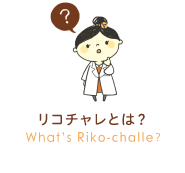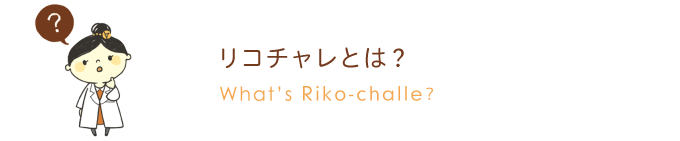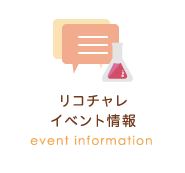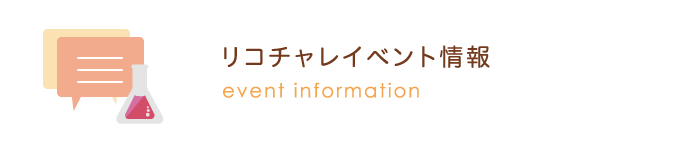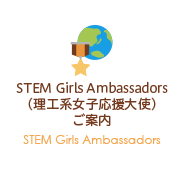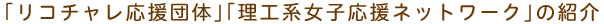「リコチャレ応援団体」
「理工系女子応援ネットワーク」の紹介

- 独立行政法人 労働安全衛生総合研究所
- 清瀬地区(本部):東京都清瀬市梅園1丁目4番6号
- 登戸地区:神奈川県川崎市多摩区長尾6-21-1
-
労働安全衛生総合研究所

組織概要
労働安全衛生総合研究所は、働く人の安全と健康の確保に資することを目的として、爆発火災や土砂崩壊といった工場や建設現場で発生する事故・災害の防止、環境中の有害物質の測定・評価、化学物質等による健康障害の発生機序の解明及び予防等に関する総合的な調査・研究を行っています。また、大規模災害等については、調査チームを編成し、原因究明のための科学的調査を行っています。
研究所の組織は、研究部門として安全研究領域、健康研究領域及び環境研究領域の3研究領域体制としており、この他総務部、研究企画調整部、労働災害調査分析センター及び国際情報・研究振興センターの2部2センターが設置されています。
- 組織図
-
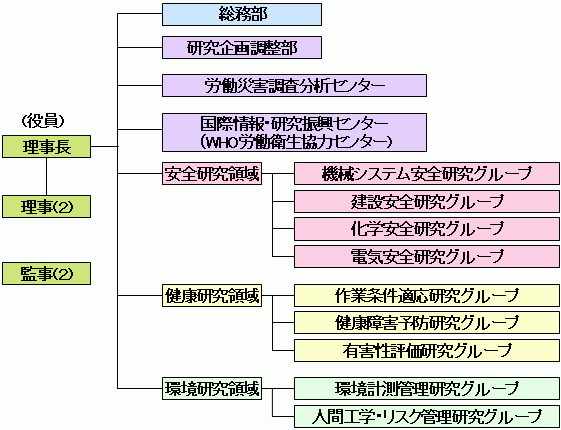
役職員数は約120名で、このうち100名弱が研究員として、理学、工学、医学等の専門性を活(い)かした研究活動に従事し、その成果を論文発表、内外の学会での口頭発表等を通じて公表しています。また、研究成果は、労働安全衛生法令に基づく安全衛生基準・各種指針やJIS(日本工業規格)、ISO(国際標準機関)等の規格・基準等の制定・改正に当たっての科学的エビデンスとして広く活用されています。
当研究所は、大阪大学、三重大学、長岡技術科学大学等国内7大学と連携大学院協定を締結し、大学との共同研究、大学院生の受け入れ・研究指導を通じて労働安全衛生分野の研究者の養成及び研究の振興にも取り組んでいます。
さらに、当研究所はWHO(世界保健機関)の労働衛生協力センターとして、国際的な枠組みの中で働く人の健康に関する研究に協力するとともに、米国立労働安全衛生研究所(NIOSH)、英国立安全衛生研究所(HSL)等9カ国11機関・大学と研究協力協定を締結し、国際共同研究の実施や国際シンポジウムの開催、研究員の相互派遣などを行っており、研究員の活動の舞台は世界中に広がっています。
理工系分野・部門の紹介
(1)3研究領域の概要
安全研究領域には、機械システム安全研究グループ、建設安全グループ、化学安全研究グループ及び電気安全研究グループの4研究グループが置かれ、主として機械・材料科学、土木・建築、化学、電気・電子・情報等の分野の研究員が活動しています。主な研究テーマは、構造部材等の疲労強度評価、機械フェールセーフ技術の確立、土砂崩壊の発生機序の解明と崩壊予知技術の開発、可燃性ガスの爆発現象の解明、電磁ノイズによる誤作動防止技術の確立などです。
健康研究領域には、作業条件適応研究グループ,健康障害予防研究グループ、有害性評価研究グループ及び実験動物管理室の3研究グループ・1室が置かれ、主として医学、保健衛生、化学・生命科学等の分野の研究員が活動しています。主な研究テーマは、動物実験を用いた化学物質等の毒性評価・評価指標の開発、肺内アスベスト小体の計測・評価技術の確立、作業関連疾患の予防、職場におけるメンタルヘルス対策の確立などです。 環境研究領域には、環境計測管理研究グループ、人間工学・リスク管理グループの2グループが置かれ、主として化学・生命科学、計測工学・環境科学、人間工学等の分野の研究員が活動しています。主な研究テーマは、環境中浮遊粒子状物質の測定技術の開発、ナノマテリアルのハザード評価、小規模事業場における安全衛生リスク評価手法の開発、騒音・振動による健康影響の評価手法の確立などです。
(2)活躍が期待される多様な人材
以上のように、当研究所における調査・研究は、機械、電気、化学、建設、生命科学、医学、保健衛生、人間科学等さまざまな学問分野をベースとしており、また、学際的な調査・研究も多いことから、理工系大学・大学院を卒業・修了した方であればその専門性にかかわらず活躍の場があると言えます。
また、研究員のうち女性の数は、化学、生命科学、医学、保健衛生等を中心に10名となっていますが、女性の社会進出が飛躍的に拡大した今日、女性の視点から働く人の安全と健康を考え、研究を深めていくことが必要になっています。例えば、過重労働による健康障害防止対策や職域におけるメンタルヘルス対策、不安全行動による事故防止、労働衛生保護具の開発等については、女性の視点からの問題提起や調査がこれまで十分に行われてきたとは言えません。当研究所としては、女性研究員を一人でも多く採用し、その活躍を期待したいと考えています。
女子中高生・女子学生の皆さんへのメッセージ
当研究所の特徴は、機械、電気、化学、建設、生命科学、医学、保健衛生、人間科学等さまざまな学問分野の出身者が集まっており、異なる分野の研究員が共同で研究を行い、また、お互いに切磋琢磨(せっさたくま)していることが上げられます。さらに、当研究所における研究テーマの多くが労働現場という「働く人」が存在する実社会を対象としていることも特徴と言えます.細分化された専門を深く追求する研究機関や自然界の現象を対象とする研究機関とは以上のような点で性格を異にしています。
このような特徴を考えると、当研究所には、理工系分野の人材の中でも人間及び経済・社会への関心が高く、かつ、専門性に拘(こだわ)らず何でも見てやろう、やってやろうという好奇心旺盛な方に来ていただきたいと思います。
また、一人でも多くの女性研究員を確保し、研究テーマやそのアプローチの多様化・深化を進めたいと考えています。
当研究所は、もともとは厚生労働省の附属研究所(国立研究所)として発足としたものであり、男女の均等処遇、少子化対策といった厚生労働省の施策については先進的な取組を行ってきました。これまでにも何人かの女性の研究部長を輩出し、家庭と研究生活を両立させている女性研究員も少なくありません。
当研究所は、見学を随時受け付けていますので、関心をお持ちの理工系分野の女子学生、保護者におかれましては、是非一度御来所いただき、進路の一つとして御検討いただきたくお願い申し上げます。