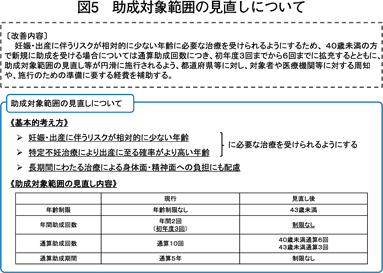「共同参画」2014年2月号
特集1(その1)
不妊に悩む方への特定治療支援事業のあり方等について
厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課
日本人の平均寿命は延びています。20~30歳代は、仕事を始めたり、家庭を持ったり、社会の中で自分の役割が充実する重要な時期です。ライフプランを考える中で、子どもを持つ時期についても、早くからよく考えておく必要があります。
1.不妊症とは
不妊症とは、「妊娠を希望している夫婦が2年以上避妊を行わず一般的な夫婦生活を送っていても子どもができない状態」と定義されています。
月経周期が順調な人なら年間12~13回の排卵があります。その中で妊娠に結びつくような周期は3割程度と考えられています。避妊をせずに性交渉を続けた場合、1年で80%、2年で90%が妊娠すると言われています。
2.不妊症の原因
妊娠が成立するためには、卵子と精子が出会い、受精して着床する過程で、多くの条件が整う必要があります。不妊症は、これらの過程のいずれかが障害を受けることで起こります。
不妊症の原因は、男性側が24%、女性側が41%、両方にある場合が24%、原因不明が11%と言われています。原因に応じて、排卵日を診断して性交のタイミングを合わせるタイミング法、手術や投薬、生殖補助医療などの治療が行われますが、必ずしも全ての方で妊娠が成立するわけではありません。
3.男性・女性ともに妊娠・出産には適した年齢があります
「いつでも子どもは持てる」と思いがちですが、女性の年齢が上がるにつれて、不妊治療を受けても妊娠しにくくなっていくことや、不妊治療によって妊娠に至っても流産してしまう確率が上昇してしまうことが分かっています(図1、図2)。
○ 女性について
妊娠・出産には適した年齢があります。女性の卵子は、加齢とともに質・量共に低下する(図3)ため、30歳を超えると妊娠率が徐々に低下し、35歳を超えると明らかに低下します。
○ 男性について
加齢とともに、妊娠率が低下するとの研究報告があります。
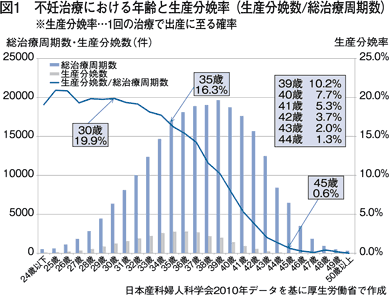
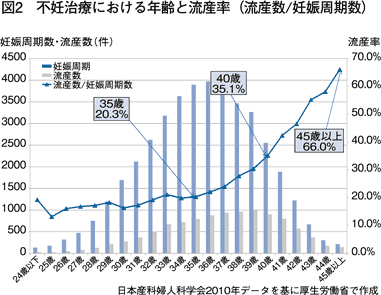
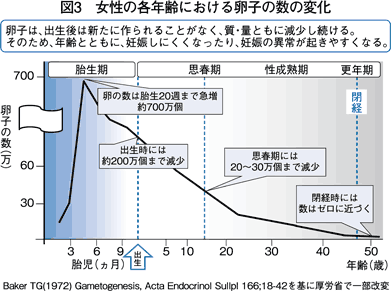
4.不妊に悩む方への特定治療支援事業について
近年、我が国においては、結婚年齢や妊娠・出産年齢が上昇しており、平成24年には、平均初婚年齢が男性30.8歳、女性29.2歳となり、第1子出産時の女性の平均年齢が30.3歳となっています。
このような変化と医療技術の進歩に伴い、体外受精をはじめとする不妊治療を受ける方は年々増加(図4)してきており、体外受精及び顕微授精により出生した子の数は、全体の出生数の約3%(平成22年)を占めています。
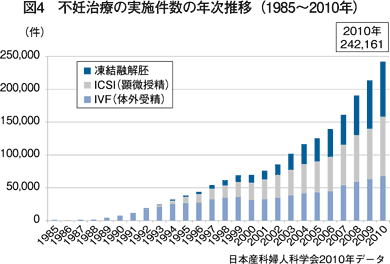
また、体外受精などの生殖補助医療を受ける方の年齢も上昇しており、一方で、一般的に、高年齢での妊娠・出産は、様々なリスクが高まるとともに、出産に至る確率も低くなることが医学的に明らかになっています。
体外受精や顕微授精は1回の治療費が高額です。
その経済的負担が重いことから十分な治療を受けることができず、子どもを持つことを諦めざるを得ない方も少なくないです。
このため、国としては、平成16年度よりその経済的負担の軽減を図ることを目的として、体外受精及び顕微授精に要する費用の一部を助成する、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」(以下「特定治療支援事業」といいます。)を実施しています。
5.特定治療支援事業等のあり方について
最新の医学的知見も踏まえ、本人の身体的・精神的負担の軽減や、より安心・安全な妊娠・出産に資するという観点から、平成25年5月に「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」(以下「検討会」といいます。)を設け、より適切な特定治療支援事業等のあり方について検討しました。
検討会において、年齢別の妊娠・出産に伴う様々なリスク等について分析・評価を行った結果、安心・安全な妊娠・出産に資するという観点から、助成対象範囲の見直しを行うことが適当であることが同年8月にとりまとめられました。
なお、検討会の報告書及び年齢別の妊娠・出産に伴う様々なリスクや医学的知見等の詳細につきましては、厚生労働省ホームページに掲載してあります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000022024.html
6.特定治療支援事業の助成対象範囲の見直しについて
厚生労働省では、検討会の報告書を踏まえ、特定治療支援事業のうち、(1)助成対象年齢、(2)年間助成回数、(3)通算助成回数、(4)通算助成期間について見直し(図5)を予定しています。
7.不妊専門相談センターについて
不妊について悩む夫婦等を対象に、現在、全国61か所(平成24年度)の不妊専門相談センターにおいて、専門的知識を有する医師等が医学的な相談や心の悩みの相談に応じるとともに、不妊治療に関する情報提供を行っています。
なお、厚生労働省ホームページに全国の不妊専門相談センターの一覧を掲載してあります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken03/
また、一部の不妊専門相談センターの取組事例についても厚生労働省ホームページに掲載してあります。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-hoken/shien/dl/torikumijirei.pdf![]()