「共同参画」2009年 7月号
特集
男女共同参画の10年の軌跡と今後に向けての視点
― 平成21年版男女共同参画白書の公表 ―
内閣府男女共同参画局推進課
内閣府男女共同参画局では、本年5月29日(金)に、平成21年版男女共同参画白書を公表しました。今回は、特集編のうち、特に今回新たに公表したインターネット調査(※)の結果を中心に、その内容をご紹介します。
(※)平成21年2月実施。20歳代から60歳代の全国の男女を対象としたインターネットによるモニター調査。回収数10,000サンプル。
1.男女共同参画推進の取組や体制の変化
本年5月29日(金)に、平成21年版男女共同参画白書を公表しました。
男女共同参画白書は、男女共同参画社会基本法に基づいて毎年国会に提出するもので、今年で10回目になります。
今回は、「男女共同参画の10年の軌跡と今後に向けての視点 -男女共同参画社会基本法施行から10年を迎えて-」を特集として取り上げており、男女共同参画社会基本法が施行されてから現在に至る10年間について、男女共同参画を推進する様々な主体の取組や推進体制の変化及び実態上の様々な分野における変化について概観・分析を行い、今後の男女共同参画社会の実現に向けた取組の在り方を展望しています。加えて男女共同参画社会の形成の状況や施策について記述しています。
ここでは、特集編のうち、特に今回新たに実施したインターネット調査(平成21年2月実施。20歳代から60歳代の全国の男女を対象としたインターネットによるモニター調査。回収数10,000サンプル。)の結果を中心に、その内容をご紹介します。
2.男女共同参画をめぐる実態と課題
1.のように、男女共同参画推進の取組や体制は整備されてきていますが、実態をみると、依然として様々な課題があり、また、新たな課題も生じています。
【男女共同参画社会基本法の理念についての進捗状況】
男女共同参画社会基本法の5つの基本理念の進展状況について、10年前と比較すると「どちらかと言えば前進した」と考える者が最も多くなっています。男女別にみると、いずれの基本理念も男性の方が女性よりも前進していると考えています(図1)。
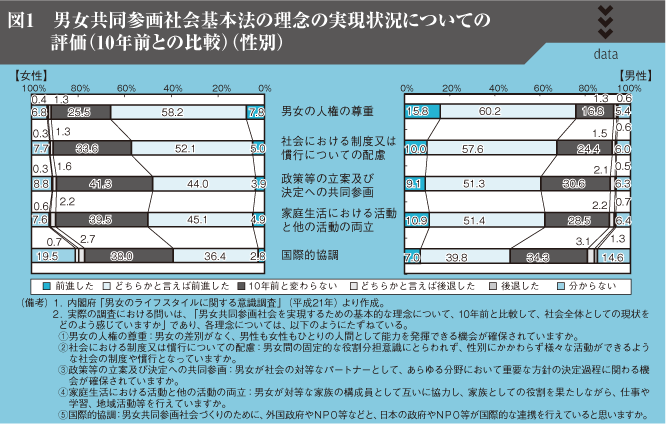
【緩やかに上昇する女性の政策・方針決定過程への参画割合】
政策・方針決定過程への女性の参画状況について、10年前と比べると緩やかではありますが、それぞれの分野において女性の割合は上昇しています。しかし、国際的にはまだ低い水準です(図2)。
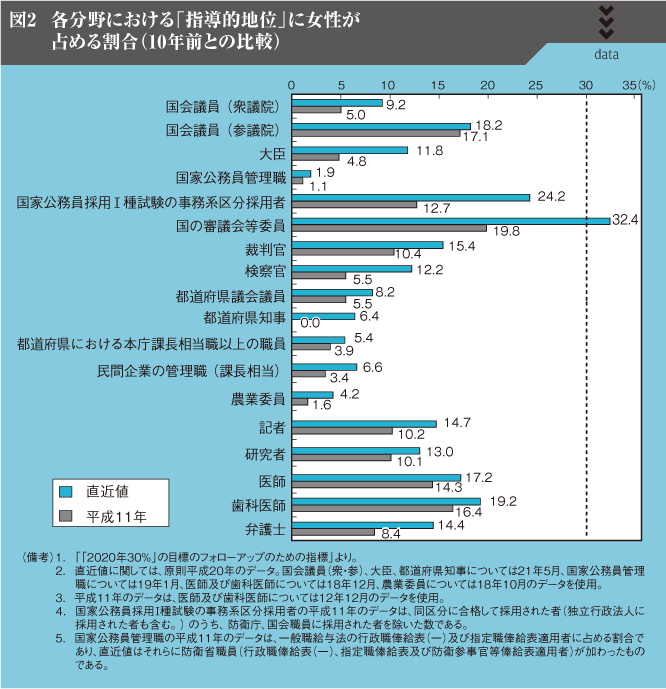
社会において、女性の参画がもっと必要だと思う分野としては、男女ともに政治家が最も多く、企業・団体の幹部層が続いています。また、男女別でみると、特に医師や弁護士・裁判官・検察官、政治家について、女性の方が男性に比べて女性の参画がもっと必要であると回答している割合が高くなっています(図3)。
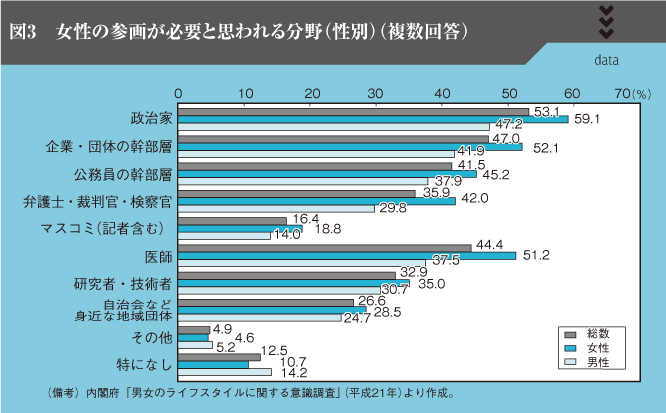
【女性の労働力率は向上しているが、国際的にはまだ低い状況】
就業をめぐる変化としては、20歳代後半から30歳代後半にかけての女性の労働力率は上がってきています。しかし、台形型に近くなっている国が多いのに対し、日本は子育て期に仕事を辞めている女性が少なくなく、依然として「M字カーブ」を描いている現状にあります。
【管理職女性は特別な存在であり、遠い存在であると感じている女性が多い】
一般論として「管理職として働いている女性は、女性の中でも特別な存在であり、普通の女性が管理職になることは難しいと思いますか」という問いに対して、「そう思う」または「どちらかと言うとそう思う」と考える人が合わせて約半数に上り、特に女性でそのように感じる人が多くなっています(図4)。
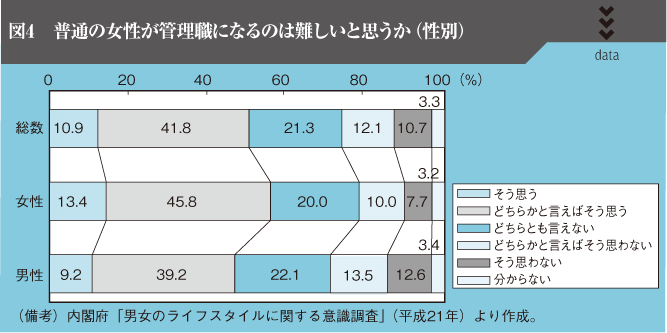
女性のキャリア形成について、「10年後に現在よりも高い職責にあったり、難しい仕事を行っていると思うか」という問いに対して女性のうち半数を超える人が「いいえ」と回答しています。雇用形態別にみると、正社員・正規の職員の場合、男性は「はい」が最も多く、女性は「はい」が約2割にとどまっています。また、非正規職員については、男女とも「いいえ」が多くなっています(図5)。
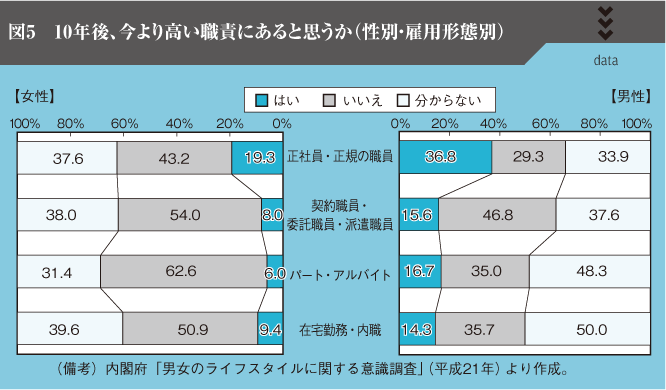
10年後に現在よりも高い職責にあると思う人は、その理由として、男性は、「職場においてキャリアパスが示されている」が最も多く、女性は「今後自分の能力開発を行っていこうと考えているから」が多くなっています(図6)。反対に、高い職責にないと思う人は、「昇進する見込みのない仕事に就いているから」が最も多く、特に女性の場合「キャリアパスが不明確だから」「家事・育児・介護等やストレス等で辞めるかもしれないから」も多くなっています(図7)。
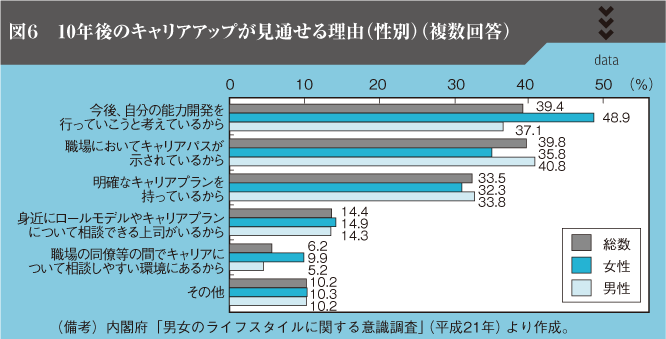
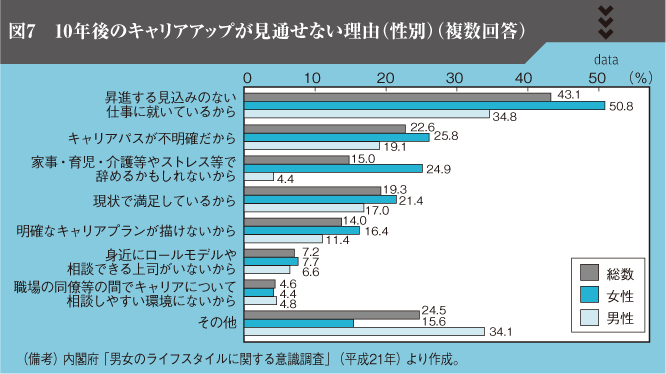
「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」といった考え方を“固定的役割分担意識”と呼びます。全体としては、賛成と反対がほぼ同数ですが、性別でみると、男性ではまだ賛成側の方が多い状態です。しかし、男性の中でも若い世代になると賛成側と反対側が拮抗してきます。他方、女性は20歳代などの若い世代において、40歳代や50歳代と比べて賛成が多くなるなど男性とは異なる傾向もみられます(図8)。
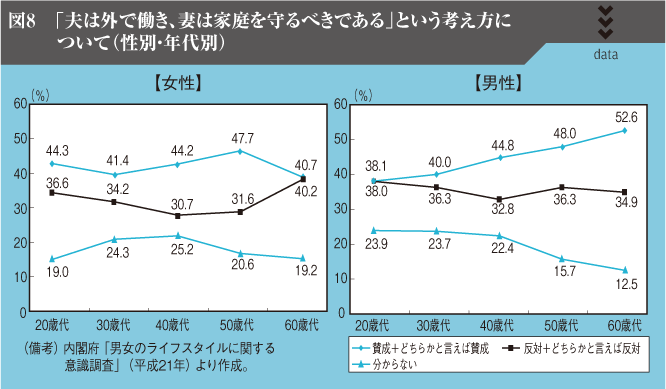
この固定的役割分担意識を理由として、自分の希望とは違う選択をしたことがあるかという問いに対して、「ある」と回答した男性は約1割であったのに対して、女性は約3割の人が「ある」と回答しており、固定的な性別役割分担意識が特に女性の希望を阻害する場合があることが分かります。特に女性の場合には、「仕事を続けたかったが辞めざるを得なかったことがあった」を挙げる人が多くなっているのが特徴です(図9)。
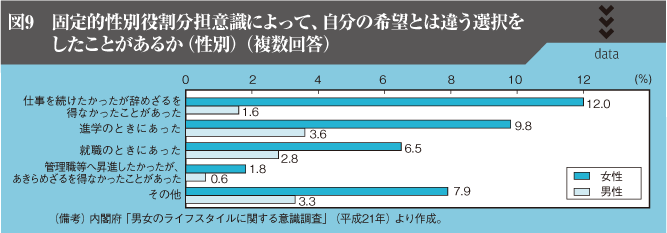
【子育て世代の男性は、家事や育児・介護への参画が必要だと考えている】
図7をみると分かるように、若い世代の男性は他の世代の男性に比べて、固定的性別役割分担意識について反対する割合が高くなっていますが、家事や育児・介護の参画状況についても、20歳代から40歳代の子どもがいる男性は約8割が何らかの形で家事や育児・介護に関わっており、同世代の子どもがいない男性の参画割合である約4割や他の世代を含めた男性全体である55%と比べても参画している割合が高くなっています(図10)。また、育児休業制度や短時間勤務制度を利用したいと考えている男性も少なからずいます。
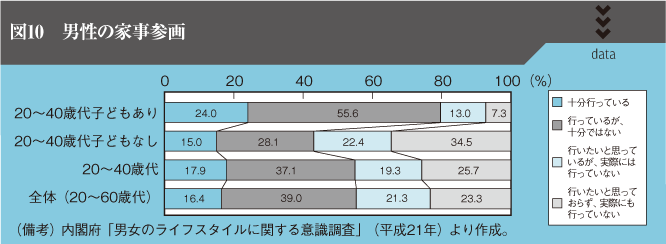
【男性の家事等への参画により、女性の継続就業率が増加】
男性が家事等へ参画することにより、女性の継続就業にも影響があります。
夫婦のうち、この5年間に子どもが生まれ、出産前に妻が仕事をしていた夫婦について、出産後の夫の平日の家事・育児時間別に、妻の出産後における「同一就業継続」の割合をみると、「家事・育児時間なし」で39.1%、「4時間以上」では66.7%となっており、夫が平日家事・育児に参画している家庭では、妻が同じ仕事を続けている割合が非常に高くなっています(図11)。
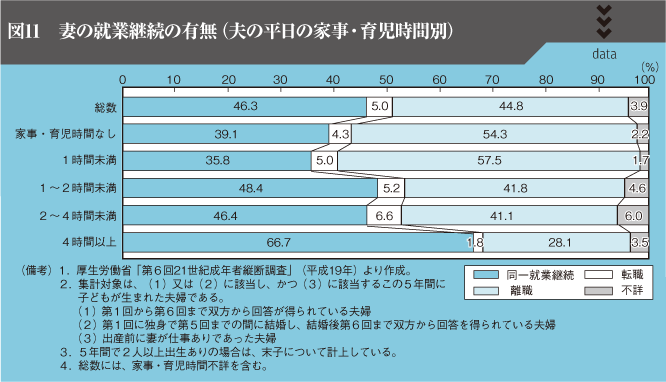
【妻に偏る家事分担の状況】
しかし、全体でみるとまだまだ家事分担は妻に偏っているのが現状であり、家事の夫婦間での分担状況については、「妻が行う」、「妻が中心となって行うが、夫も手伝う」が約9割に上り、「半分ずつ分担して行っている」夫婦は約7%にとどまっています。また、これを妻の就業状況別にみると、夫婦ともにフルタイムで働いている家庭においても、「妻が行う」、「妻が中心になって行うが、夫も手伝う」が約75%を占めており、「半分ずつ分担して行っている」夫婦は約2割にとどまっている状況です(図12)。
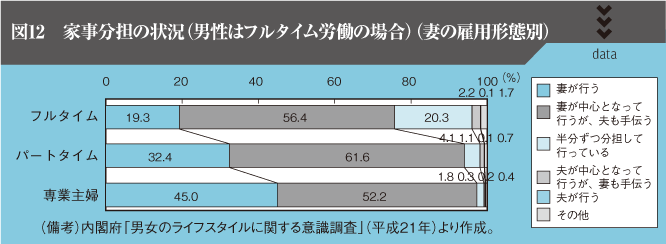
【女性が地域社会で活躍するために最も必要なことは家族の理解】
地域で女性が活躍するために必要なこととして、家族の理解を挙げる人が多くなっています。女性が地域において能力を十分に発揮するためには、男性を含む地域社会全体の理解と協力が不可欠ですが、地域における女性の活躍を妨げる要因としては、いまだに「世帯や組織の代表は男性」に代表される固定的な役割分担意識が存在することが考えられます(図13)。
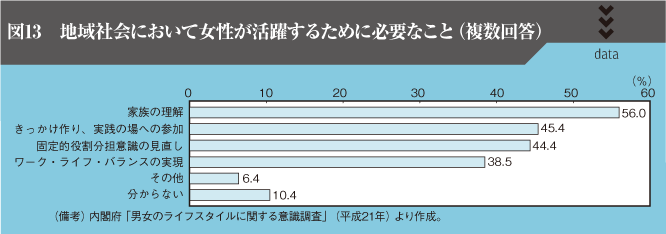
【新たな社会情勢の変化に伴う生活困難を抱える人の増加】
家族の変化、就業をめぐる変化、グローバル化等の変化の下で、経済的困難に加え、日常生活の困難や地域社会における孤立等の社会生活上の困難を含めた「生活困難」を抱えている人が増加しています。特に、女性は妊娠・出産等のライフイベントの影響、非正規に就きやすい就業構造、女性に対する暴力、固定的役割分担意識等の要因から、生活困難に陥りやすい状況があります。また、男性についても孤立や日常生活自立の困難や男性役割のプレッシャーという特有の状況がみられます。
3.男女共同参画社会の実現に向けて
これらを踏まえ、男女共同参画社会実現に向けた取組を推進するに当たって、重要と考えられる方向性は以下の4点です。
(1)「仕事と生活の調和」、「女性のキャリア形成支援」、「意識改革」の一体的な取組
「仕事と生活の調和」、「女性のキャリア形成支援」、「意識改革」の3つの取組はそれぞれ密接不可分に関連しており、一体として捉えた上で有機的に進めていくことが必要です。
(2)新たな社会情勢の変化に伴う生活困難を抱える人の増加への対応
昨今の急激な社会情勢の変化の中、生活困難を抱える人が増加しており、その背景にある男女共同参画をめぐる問題に着目することが重要です。生活困難を抱える人々の支援に当たっては、女性のライフコースを通じたエンパワーメントの視点に立ち、個人を一貫して総合的に支援する仕組みの構築とともに、次世代への連鎖を断ち切るための支援が必要です。
(3)地域における多様な主体のネットワーク化による連携・協働
様々な分野における多様な主体のネットワーク化による連携・協働を進めることにより、問題解決に向けた大きな流れをつくっていくことが重要であり、様々な主体が連携・協働して課題解決型の実践的な活動を中心とした取組を行い、地域における男女共同参画を推進していくことが必要です。
(4)国際的な枠組みの下での連携・協働
2010年に予定されるAPEC女性リーダーズネットワーク会合等の開催といった機会を十分に活用し、国際的な連携・協働や相互の対話・情報発信に努めることが必要です。
21世紀の最重要課題として、男女共同参画社会の実現を提起した男女共同参画社会基本法施行から10年を経た今、男女共同参画社会実現の意義について改めて認識する必要があります。経済社会の大きな変化の中、これまでの手法や枠組みでは実態や新たな課題に対して十分対応できない場面が様々な分野において生じているところです。こうした局面において、一人ひとりの個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現のための取組は、社会において生じている様々な具体的な課題解決に道筋をつけ、一人ひとりが豊かな人生を送ることを可能にし、組織を活性化し、ひいては持続可能で活力ある社会に向けての大きな原動力となり得ます。
男女共同参画社会の実現を目指して様々な取組を進めていく際、多様な主体のネットワーク化による連携・協働の下で、具体的な課題解決のための実践的で社会のニーズに応じた取組を推進する大きな流れを作っていくことが重要です。多様な主体の連携・協働の下での実践的な取組は、人々に意識変革や更なるエンパワーメントをもたらします。
今後、男女共同参画社会実現に向けての取組は、より実践的な「第二ステージ」へと進んでいくよう取り組んでいかなければなりません。

