本編 > 男女共同参画白書の刊行に当たって

内閣府特命担当大臣(男女共同参画)
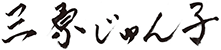
男女共同参画社会基本法が制定されてから25年が経ちました。基本法では、法の前文において、男女共同参画社会の実現を「21世紀の我が国社会を決定する最重要課題」であることをうたっています。
基本法の制定以来、政府においては、配偶者暴力防止法や、女性活躍推進法、政治分野における男女共同参画推進法の施行等を通じて各種制度の整備を進めてきました。その結果、現在では、女性の就業者数は増加し、いわゆる「M字カーブ」の問題は解消に向かいつつあり、上場企業の女性役員数も近年大きく増加しています。また、政党により女性候補者の割合の向上に向けた取組が行われるようになるなどの変化が見られ、セクシュアルハラスメントや性犯罪・性暴力に対する社会の受け止め方も大きく変わりました。
しかしながら、出産を契機に女性が非正規雇用化する、いわゆる「L字カーブ」の問題や男女間賃金格差の問題があるほか、女性役員及び女性管理職、女性議員の割合は諸外国に比べると低い水準にとどまっています。さらに近年は、若い世代、特に女性において、進学、就職等を機に地方から都市へ転出した後、都市に留まり地方へ戻らないという現象が起こっています。
こうした課題の背景については、職場、家庭、地域社会など様々な場面で表出する固定的な性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)の存在が要因の一つとして指摘されています。
少子高齢化や人口減少が急速に進行する中、全国の各地域の取組により、「家事・育児・介護は女性の仕事」、「地域や親戚の集まりでの食事の準備やお茶出しは女性の仕事」といった固定的な性別役割分担意識を変え、地域の男女間の不平等を解消し、性別に関係なく個性と能力を発揮できる魅力的な地域づくりを進めていくことが必要となっています。
このような問題意識の下、今回の白書では、「男女共同参画の視点から見た魅力ある地域づくり」を特集テーマとしました。この中では、全国的な人口移動の状況や男女の時間の使い方、意思決定層への女性の参画の状況に関する都道府県別の状況を分析しているほか、若い世代の視点から見た地域への意識を分析し、魅力ある地域づくりに向けた考察を行いました。
この白書が、国民の皆様に広く参照され、我が国の男女共同参画の現状に関する理解を深める一助となるとともに、全国各地の男女共同参画の更なる推進につながることを願っております。
令和7年6月