巻頭言
被害者にも加害者にも傍観者にもならない
内閣府調査によると、配偶者等からの暴力を受けながらも被害にあった女性の約4割、男性の約6割は、「相談するほどのことではない」等と考えて、誰にも相談していないことが分かっています。逆に言えば、被害を相談したことがある女性は約6割、男性は約4割となります。そして、被害を相談したことがある人のうち半数以上が「友人・知人」に相談をしています。このため、周囲の人たちの理解が重要となります。「知人・友人」は、当人の日常生活圏にいる身近な人たちのことです。見渡せる空間のなかにいる被害者の変化に気づき、声かけし、相談に応じること、これを「近助(きんじょ)」といいます。自助・共助・公助に加えた言い方です。DVや虐待について正確な情報を持ち、援助につなげていく架け橋のような役割を果たすことができます。
見て見ぬふりをするだけではなく、「そんなことは喧嘩でよくあること」といってしまうことは加害者に加担していることになります。傍観者といいます。二次被害・二次加害も起こりかねません。傍観者としてではなく、「善き隣人として最初の支援者」になることは誰にでもできることです。第三者にできることはたくさんあります。例えば、「よく話をしてくれました」と応答するだけでもいいのです。DV被害の専門機関の情報を伝えることもできます。
さらに、加害者対応です。DV被害者支援の一環として加害者プログラムの対応をしている自治体が複数あり、プログラムを実施している民間団体も存在しています。一部ですが、暴力を振るう人も加害者向けの相談にやってくるようになりました。
そして、何よりも次の世代に向けた予防です。ストーキング行為、DV、子ども虐待、高齢者虐待等にかかわる法律が2000年以降、数多く制定されてきました。現在20歳代までの若者はこうした時期の中を成長してきた世代です。家族体験が親の世代とは異なるのです。自らの家族生活を振り返りながら暴力や虐待についてとても敏感になっている世代です。特に男子がそうです。これから家族形成期に入っていく若い世代は、加害者にも被害者にも傍観者にもなりたくない脱暴力の意識をとても大事にしています。その様子が私たちの取り組む男性相談から垣間見えるのです。
被害者支援、加害者対応、傍観者対策、予防的啓発がひとつになって暴力の解決が可能となります。できることから取り組んでいきましょう。
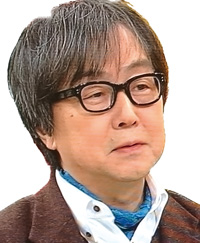
中村 正
Nakamura Tadashi
立命館大学特任教授
一般社団法人UNLEARN代表理事
